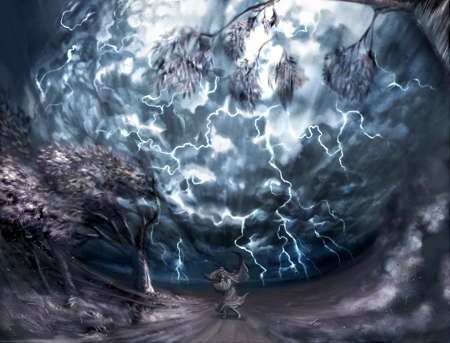力−一人一人−
マスター名:村木 采

|
|
|
■開拓者活動絵巻
1
|
| ■オープニング本文 前回のリプレイを見る ● 無数の硬い爪が、岩を叩く音がする。門の無い南北から、百足が入り込んでいるようだ。 「馬手が逃げたって事は‥‥勝ったのか?」 「逆だ。村を虫が蹂躙するに任せ、自分一人で逃げた」 櫓から落ちて外れたのか、老鍛冶に肩を入れてもらいながら、弓使いが忌々しげに言う。 「弓は引けそうか」 老鍛冶の問いに、弓使いは折れた弓を蹴飛ばすと、倒れた仲間から弓を借り受けた。 「全力は無理だ。が、引く以外なさそうだな」 にわかに、西門が騒がしくなり始めた。虫が上がってきたのだろう。 富士額が、老鍛冶の顔を見た。 「爺さん。どうすんだ」 「どうするもこうするも、戦うほかあるまいが」 老鍛冶は険しい顔で、馬手の消えた東の方角を睨んだ。 妙案でも思いついたか、富士額が指を鳴らす。 「バリケードを移したらどうだ」 「今から、箪笥や岩を一つ一つ動かすのか? 笑えん冗談だ」 富士額の言葉を、弓使いが一蹴する。 と、その傍へ巨大な影が舞い降りた。一つ。二つ。三つ。 姫百合の子供達だ。殆ど空を飛ぶ事も適わない生活から、突然の長時間の飛行だ。余程疲れたのか、荒い息をついて広場にうずくまってしまう。自らの火に焦がされ、牙は一本残らず真っ黒だ。 東の空の雪喰虫は、大半が魔の森へと帰ったようだ。が、なお小さな雲のごとく、村の上空にはその一部が滞留している。 「姫百合。大事無いか」 老鍛冶が、未だ姫百合の表皮に残る雪喰虫をはがし、草鞋で踏み潰す。 (死にはすまい) 姫百合は門前にうずくまったまま、柿色にくすんだ翼を軽く広げて見せた。 皮膜は穴だらけで、所々に蟷螂の鎌や刀による裂傷が入っている。痩せた首と肋骨の浮き上がった胴には、深い傷跡が刻まれていた。 (見ての通りだ。この翼で馬手を追う事は適うまい) 大儀そうに後肢を踏み出し、重い身体を引きずって門の内側を目指す。 (だが、門を越えてくる虫共を焼き払う砲台くらいにはなれよう) 姫百合が、広高に裂かれた顎を歪める。笑ったらしい。 その時だった。 「おじいさん!」 場に全くそぐわない、気丈な少女の声が響いた。 ぎょっとして老鍛冶が振り向くと、木箱を抱えて油断無く辺りを見回している光広と、その手を引いて堂々と歩いてくる雲雀の姿が目に飛び込んでくる。 「坊ちゃん、嬢ちゃん! 百足に襲われたらどうする」 老鍛冶が義足を引きずり、苦労して二人へ近寄った。 「大丈夫。光広兄ちゃんもいるし、お守りもあるもん。ね!」 光広は、聖女と称される巫女に渡された焙烙玉を大事そうに懐から取り出した。 「静かになったと思って、様子を見に来たのですが‥‥まだ終わっていないのですね」 「うむ‥‥虫が最後の攻勢を掛けてきよった」 老鍛冶は、からからに乾いた口で苦労して唾を飲み込む。 「何か、手伝わせて!」 雲雀が小さな拳を振り上げた。 「嬢ちゃん達が、一体どうやって戦うと言うんじゃ」 「ケガの手当てくらいならできるもん! 新しく、火薬玉も作ってきたし! 光広兄ちゃんが!」 雲雀が背伸びをし、老鍛冶の顔をにらみ上げた。 一瞬の沈黙が、門の前に降りる。 (全く。広高も裸足で逃げ出す無鉄砲だ) 苦笑混じりの声が、姫百合の低い唸り声と共に聞こえてきた。 ようやく四頭の龍に気付き、雲雀は目を丸くする。 「あなたは?」 (姫百合。古き英雄、広高を背に乗せて戦った老いぼれだ) ゆっくりとその首を伸ばし、姫百合が雲雀と光広に目の高さを合わせた。 (その勇気は、尊い。しかし、足手まといになっては本末転倒だ) 「‥‥はい」 姫百合に言われ、雲雀は肩を落とす。 (だが、これだけの負傷者だ。癒し手も足りるまい。避難している場所があるなら、そこで手当は頼まれてもらいたい) 「うん!」 雲雀の顔が、ぱっと明るくなった。 光広が、幾度目かの大きな息をついた老鍛冶に肩を貸す。 「お爺さんも相当なお怪我と見えます。手当を」 「何を」 老鍛冶は杖代わりにしていた斧を担ぎ上げようとし、身体を支えきれずに盛大な尻餅をついた。 「爺さん、無理をするな。せめて武器が振るえる身体になってこい」 「馬鹿を言え」 まるで聞き入れようとしない老鍛冶に、弓使いは舌打ちを漏らす。 「なら、このガキ共を二人だけで避難所に帰らせるのか」 言われ、老鍛冶はぐっと言葉に詰まった。 「構わんぞ、俺は。枯れ木も山の賑わいだ」 「ええい、解ったわ。行けば良いんじゃろう、行けば。火薬玉は置いていく、坊ちゃんに感謝して使え」 半ばやけばちになり、老鍛冶は叫ぶ。 弓使いは皮肉っぽく唇を歪めた。 「言っておくが、戦える様になったらすぐに戻れよ。武器を振るえる奴は一人でも欲しいんだ」 「ふん、せいぜい儂が戻る前に全滅せんようにな。戦いが終わったら、お前たち侍どもには言いたい事が山程あるんじゃ」 老鍛冶は吐き捨てるように言い、弓使いに背を向ける。そして、気遣わしげに姫百合の傷跡を指でさすっている雲雀と、その傍の光広を招き寄せた。 「坊ちゃん、嬢ちゃん。避難している家で、ありったけ湯を沸かすぞ。清潔な布と酒も準備せにゃならん。重傷者の手当を手伝ってくれ」 「わかりま‥‥」 「わかった!」 光広よりも先に、雲雀が声を上げた。 弓使いは頷くと、隣に立つ富士額に視線を移す。 「おい禿」 「誰が禿だ!」 富士額は顔色を変えて怒鳴った。 「禿は禿だ。比較的傷の浅い連中と協力して重傷者を運べ。終わったらすぐ戻れよ」 「俺は禿じゃねえが、引き受けた」 「今は禿でも貴重な戦力だ。急げよ」 「誰が禿だか知らねえが、力は貸してやる」 弓使いと富士額は一瞬睨み合い、引きつった様な笑みを浮かべて互いに踵を返す。 門を潜ろうとした姫百合が首を曲げ、門前にうずくまる三頭の子龍に声を掛けた。 (我が子らよ。谷に潜み、森に隠れ、奪われし空を見上げるにも飽いたろう) 村の巫女に治療を受けていた三頭が、僅かに首をもたげる。 (ゆけ。蒼天の玉座を汚した罪、虫共に贖わせる時は今ぞ) 三頭の龍が、広がりつつある雪喰虫の群れを見上げた。 (天は我らの首を、下に向くよう創った。世を見下ろし、刃向かう愚者を叩き落とす事こそ我らが天分) 「姫百合。何を言っている」 訝る老鍛冶をちらりと横目で見やり、姫百合は開拓者達を顎で指した。 (我が子らに乗れ。鞍も何もありはせぬが、馬手を追うだけならできぬことはあるまい) 姫百合は眩しそうに目を細める。 (新しき者達よ。英雄の世ならざる世の者達よ。お前達に襷を渡せただけでも、我の生まれた甲斐はあった。戦った甲斐があった) 子龍達の首が、再び持ち上がった。爛々と光る両目が、上空で蠢く雪喰虫の群れを睨み上げる。 三頭が着陸したことで、雪喰虫は少しずつその高度を下げていた。散々炎を浴びせられて虫なりに学習したか、篝火が無く光と熱を感じられない辺りは、家々の屋根の辺りにまで虫が降りてきている。 (お前達の襷だ。見事守って見せよ) |
| ■参加者一覧 17歳・女・巫 27歳・男・志 20歳・女・騎 21歳・女・シ 16歳・女・砲 27歳・男・シ  熾弦(ib7860)
熾弦(ib7860)17歳・女・巫 |
| ■リプレイ本文 ● 「ここで馬手を逃がす訳にはいきませんの。逃がせば回復した上で、援軍を連れてくるのは目に見えてますの」 愛銃「クルマルス」の銃口に流し込んだ火薬を突き固めながら、厚司織に外套を羽織っただけという軽装の神威人、十砂魚(ib5408)が呟いた。 「全く、行動がいちいちいやらしいですの。村の防衛も必要なのに、戦力を分けざるを得ませんの」 黒髪の中から生えた黄金色の狐耳を軽く伏せ、うんざりした様子で呟く。腕輪に填め込まれた紅玉が、篝火の明かりを受けて一際赤く輝いている。 「俺が残ろう」 家の影に溶け込むような忍装束に黒い外套を纏ったウルシュテッド(ib5445)が手を挙げた。 「往くも留まるも心が残る‥‥だからジル、俺の心の半分をお前に預ける」 「任せとき。テッドさんの気持ちは持っていく」 弓掛鎧の上からローブを羽織り、茶色い髪が目に入らないよう頭にストールを巻いた青年、ジルベール(ia9952)はウルシュテッドと拳の甲を打ち合わせた。 「姫百合と、あんたらの気持ちもな」 青い瞳が、姫百合と侍達を見回した。 「その太刀で必ず馬手を討て。それは新しい時代の刀‥‥だろ?」 ウルシュテッドは、ジルベールが腰に佩いた真新しい太刀を指す。 「古の英雄の志を踏み躙った奴などに、負けるなよ」 それ以上言葉を交わす事なく、ウルシュテッドは弓を手に東門を潜った。 「私も残りましょう‥‥治癒役も必要だと思いますし‥‥」 金色の長杖を小脇に抱え、巫女袴にローブを羽織った銀髪の少女、柊沢霞澄(ia0067)が小さく手を挙げた。 侍達がめいめいに拳を握り、俄に活気づく。 「よっしゃ、こいつぁ勝てるぜ」 「おい梵露丸持ってこい! 別嬪の巫女さんに使ってもらえ」 霞澄は気恥ずかしそうに俯き、上目づかいに侍達を見わたした。 「頑張りましょう‥‥、『縁』という襷を渡せるよう、受け取れるよう‥‥」 『応!』 すっかり勝った気になった侍達が、それぞれの獲物を高々と掲げて吼えた。 小さく頷き、杖を握り締める霞澄の胸に、幾つもの酒瓶が放り投げられた。霞澄が、慌ててそれらを一つずつ受け止める。 「これは、‥‥お酒?」 瓶を放り投げたのは、白く輝く板金鎧に身を包んだ銀髪の騎士、アルクトゥルス(ib0016)だった。 「馬手の首級を挙げて帰ってきたら、コイツで祝い酒といこうぜ」 猟犬と交差する斧槍と剣の家紋があしらわれた胸甲をガントレットで叩き、炎を模した赤い面頬の奥で笑う。 狐に摘まれたようなかおをしていた霞澄だったが、やがてそっと微笑み、頷いた。 「ええ‥‥誰一人欠けることなく、皆で‥‥」 (馬手を追うのは五人か。どう分乗する) 目を細めて侍達を眺めながら、姫百合が鼻から息を吐いた。 全身を漆黒の忍装束に包んだ若き女シノビ、桂杏(ib4111)が、面頬の顎に当てていた人差し指を立てて言う。 「私とジルベールさんが、一人ずつ。最速で追いつき、足止めをする‥‥という形でどうでしょう」 「せやな。一人じゃ足止めしきれんし、二人ずつ乗っとったら追いつくのに時間が掛かりすぎるわ」 ジルベールが即答する。 残る開拓者達が頷き、桂杏は最初に目が合った小豆色の子龍に歩み寄った。 「同じ事が繰り返されないよう、取り逃がす事だけは避けねばなりません。それに指揮者を失った下級アヤカシの群れは高い確率で足並みを乱します」 龍は嬉しそうに一声啼き、自ら首を前へ差し出した。 「よろしくお願いします」 面頬の奥で優しく目を細め、桂杏は鐙も無しに龍の背へ駆け上がった。 「馬手は白い水干を纏っています。それを頼りに追ってください」 桂杏に背を撫でられ、子龍は大きく翼を打ち下ろす。 ジルベールは桂杏の龍よりも幾らか色の明るい、茜色の子龍に跨った。 「志体持ちも所詮ちっぽけな人間に過ぎへん。自分が英雄やないことに失望したこともある」 猛る茜色の龍は天に向かって勢いよく炎を吐いた。ジルベールは村の侍達を見回した。 「でも、俺らは決して無力やない。力を束ねれば岩であろうと穿てる筈。村を頼むで」 「さっさとはっ倒して、戻ってこいよ」 侍達が笑った。 アルクトゥルスが、景則の一太刀を受けた肋の辺りを指で指す。 「馬手が持ち逃げした太刀には気をつけろ。流石の山家‥‥だったか? 胴田貫の本家本元だけあって、切味抜群だ」 桂杏は頷いた。 「戦い様については‥‥」 「道中、俺が教えるわ。行くで」 ジルベールの乗った子龍が一声吼え、炎を吹いて雪喰虫の群れへと突っ込んでいく。 「お願いします」 桂杏の手が子龍の首を叩き、ジルベールに続いた。 「私達も、行きましょうか」 雪喰虫に隠された空の下、千羽鶴を模した髪飾りがちりりと鳴る。神衣の裾をはためかせ、銀髪の女修羅、熾弦(ib7860)の高下駄が岩盤を叩いて軽やかな音を立てた。 「誰かを寄る辺にするのでなく全員で立つことを知った村を潰させるわけにいかない‥‥共に立たずに同胞を切り捨てた馬手に、その行動の結末を見せてあげましょう」 残る一頭、緋色の龍が平伏すようにして首を差し出す。熾弦が、砂魚が、その背に跨った。 (飛び立つ瞬間に、足に掴まるといい。背に三人乗るよりは、安定するだろう) 姫百合の言葉に頷き、アルクトゥルスは革張りの小盾を握り締めた。 ● 「ほら、薪が足りないわよ」 鍋に張った水を沸かす茶店の女将が大声を上げ、その息子達がせっせと薪を割っている。 薪を割る音に、鉄扉が開く音が混じった。避難所の人々がぎょっとしてそちらを見る。 「おう、男前が持ってきた符水貰って行くぜ」 立っていたのは、血だらけの侍だった。扉を開いた光広がすぐに閂を掛け、侍はその場に座り込んでしまう。 「無駄遣いするでないぞ。あとこいつも持っていけ」 丁度刀の白研ぎを終えたばかりの老鍛冶が、符水の入った革袋と共にその刀を放り投げた。 「悪い、助かる」 符水を喇叭飲みし始めた侍に、女将が声を掛けた。 「怪我治ったら、店に行って深鍋持ってきて。こんな小さい鍋じゃあ話になんないわよ」 侍が頷いて立ち上がり、怪我の様子を確かめるや、避難所の鉄扉を開いて外へ走り出ていく。 奥の座敷に寝かされている重傷者が、襖を開けて顔を出した。 「何か、手伝う事はあるか」 「怪我人は茶飲んで寝てなさい。お嬢ちゃん、茶出してあげて」 「うん!」 薬研で薬草をすり潰していた雲雀が元気よく返事をし、立ち上がった。柄杓で手早く鉄瓶に湯を注ぎ、箱から出した茶葉を放り込む。 別の鍋を竈に掛けながら女将が不気味な笑みを浮かべた。 「ついでに薬草も入れてやって頂戴。少しは治りも早くなるでしょ」 「うん!」 雲雀は満面の笑みを浮かべ、自分がすり潰していた薬草を鉄瓶に放り込む。 「お、おい、その薬草、飲むもんじゃねえぞ」 「多分だいじょうぶ! いつものお礼だよね、おばさん!」 「お嬢ちゃん、良く解ってるわねえ」 雲雀は玉虫色の泡を立てる茶を湯呑みに注ぎ始め、重傷を負った侍達が青ざめた。 ● 西門から、景気の良い爆発音が聞こえてくる。 東門前の道に一人仁王立ちしたウルシュテッドは、四尺五寸の黒い湾弓を引き絞り、道を這い上がってくる虫達に狙いを定めた。 風は南向き、弱風。狙いは先頭に立つ蟷螂の足の付け根だ。 鋭い弦音を立てて放たれた矢は煌めきの尾を曳き、蟷螂の背に突き刺さる。眉一つ動かさず、ウルシュテッドは第二、第三の矢を放った。 ウルシュテッドの後方で、怒鳴り声が上がる。 「離れろ、この野郎」 「調子こいてんじゃねえ」 村に入り込んでいた百足が、物陰から侍達に襲い掛かったらしい。三人一組で動いていた残りの侍が百足の甲殻の隙間に刀をねじ込み、百足は反射的に体を捩った。その隙に下に敷かれた侍が脱出する。 途端、つかず離れずにいた別の三人組が押し寄せ、百足を足で押さえつけて袋叩きにし始める。 「上出来だ」 ウルシュテッドは苦笑を漏らして矢を放った。 今度こそ、矢が蟷螂の足の付け根に突き刺さって体勢を崩させる。踏ん張ろうとした足は道を踏み外し、蟷螂は斜面を滑落し始めた。 「守りましょう、一人一人の力を尽くして‥‥」 微かに霞澄の声が聞こえ、閃癒の柔らかな光が東門近辺に漏れる。 道の下を睨み下ろしながら、ウルシュテッドが声を上げた。 「霞澄の支援ある内は強気で攻めろ!」 その声に呼応するかの如く、岩山の斜面すれすれを黒い影が掠めて通り過ぎた。首を竦めたウルシュテッドの耳に、聞き慣れた声が届く。 「精霊達、ちょっと疲れるけど我慢してね」 龍の背に跨った熾弦の、深みのある、朗々とした歌声が上空から辺りへと放射された。一帯に潜む精霊達が励起され、緩やかに、次第に速度を速め、踊り出す。 道に立つウルシュテッドの背筋に、寒気が走る。髪がざわつく。肌が粟立つ。精霊達の乱舞が始まった。 精霊達の口から漏れる叫びが瘴気を小刻みに揺るがし、炉に放り込まれた雪のように雪喰虫の群れが蒸発し始めた。地上の虫達が大混乱に陥り、仲間を巻き添えにして斜面を滑落していく。 「後は任せた」 既に精霊達を鎮める歌に切り替えている熾弦に代わり、龍の足に掴まってクロークをはためかせたアルクトゥルスが怒鳴る。ウルシュテッドは右手を軽く挙げ、雪喰虫の雲にぽっかりと空いた穴へと突っ込んでいく龍を見送った。 ● 「野郎、来るんじゃねえ」 西門の櫓二つに上った射手達が、弦も切れよ、骨も折れよとばかりに弓を引き、固まった虫に火薬玉と焙烙玉を投じている。 と、櫓の弓使いが後方の叫びに気付き、振り向いた。二匹の百足を前に、侍二人が必死に防戦している。その後ろの血溜まりに、もう一人の侍が転がっていた。 弓使いは痛みを堪えて弓を引き、立て続けに三本の矢を放った。一本は甲殻に弾かれたが、二本は見事甲殻の隙間に矢羽根まで突き刺さる。 「開拓者の話を聞いてなかったのか。動けなくなる前に避難所に下がれ」 弓使いが櫓から怒鳴る。叫びを聞いて駆け付けた二人組の侍が手負いの百足に襲い掛かり、残る二人は倒れた侍を担ぎ上げた。 射手の一人が、不安げに門を見下ろす。 「おい、門の音、大丈夫だろうな」 弓を構えた侍が舌打ちを漏らした。蟷螂や蟹の体当たりで揺れる門の音が、長く響くようになっている。 「まだ大丈夫だ。閂か門扉がやばくなったら、中の連中が声を掛けてくれる。限界前には退く、安心しろ」 弓使いは両手で抱えた火薬玉に篝火の火を移すと、門前に群がる虫へと投げつけた。 「どうせだ。残ってる火薬玉、全部放り込んでやれ」 「いいのか」 「中に入ったら、こんなに密集していてはくれんぞ」 弓使いに言われて櫓の侍達は頷き、手元の火薬玉と焙烙玉に一斉に火を点けた。 ● 夜風に髪を嬲られながら森を見下ろしていた桂杏が、ふと目を細めた。 「あれですね」 夜闇に浮かび上がる白い水干が、木の根や幹を蹴り、一目散に東へと向かっている。木々が邪魔になり、鎧虫で一足に長距離を跳ぶ事はできないようだ。 身体に張り付いた雪喰虫を剥がして握り潰し、ジルベールが左手を外套の裾から出した。 「回り込みます」 「よろしゅう」 短く言葉を交わし、二頭の龍がその軌道を変えた。 アームクロスボウが鋭い音を発し、疾駆する馬手の動きが変わる。 「帰るんか? 馬手の坊ちゃん」 「また貴様か」 眼前に突き刺さった矢を避けて大きく跳躍した馬手が、茜色の龍を見上げて忌々しげに舌打ちをする。 「もうちょい遊んで行きぃや」 ジルベールは長い外套を翼の様に広げて宙へ身を躍らせた。落下しながら木々の枝に手を掛け、落下の勢いを殺し、方向を変えて、たたらを踏みながらも無事森の地面に着地する。 直後、鶴の鳴き声を思わせる高い風切り音が馬手に襲い掛かった。 桂杏の散華だ。木々の合間を縫い、針の穴を通すかの如き正確さで、三枚の手裏剣は馬手の右目、喉、胸を狙っていた。 だが三枚のうち二枚は空を切り、残る一枚も、馬手の腿を掠めただけに終わる。馬手は宙から鎧虫を伸ばし、木の幹に食らいつかせてその空間に静止した。 「追ってきたのは、精鋭二人‥‥という所か」 馬手は木陰から析出されるように現れた桂杏を見て、ゆっくりと地に降り立つ。 桂杏は右手で忍刀を抜いた。左手の二指から五指の間には、三枚の手裏剣が挟まれている。 「たかだか二人とは。儂も舐められたものよの」 「無茶は承知でもやったるわ。お前を逃したら村で闘ってる皆に合わす顔があらへんからな」 鯉口を切るジルベールの周りに、朧気に発光する花弁が漂いだした。 辺りに増援の気配が無い事を確かめた馬手は、口元を歪める。 「案ずるな。あの世で嫌でも顔を合わせる事になる」 「馬手、お前だけで何が出来る」 花弁が、刀身に吸い込まれた。暗闇に、薄紅色の残光が踊る。 馬手の太刀「景則」が「古釣瓶」の斬撃を鎬で外し、そのままジルベールの顔面を襲った。だがその刃が肌に到達するよりも早く、花弁を纏い翻る刀が馬手の首を狙った。景則が軌道を変えて古釣瓶を受け止め、放たれた鎧虫がジルベールの胴をまともに捕らえる。 だが後方へ運ばれ始めたジルベールが木に叩きつけられるよりも早く、闇に溶けた桂杏の追い突きが鎧虫に突き刺さった。鎧虫が大きく震えて刺さった鋒を払い、馬手が空いた桂杏の腹を蹴り上げる。桂杏はそれを左膝で受けて後方へ跳んだ。 「人は手を携えることで一の力を十にも百にも出来る。見損なうなや」 ジルベールは軽く咳き込みながらも体勢を整え、再び身体の回りに赤い花弁を撒き散らす。 「高々二人で、十なり百なりにできるならやって見せよ」 地を蹴った馬手が、木々の葉を撒き散らしながら桂杏に肉薄した。 その右手に、刀が握られていない。桂杏は首を竦め、馬手の右拳を肩で受け止めた。反動で下がる馬手の胸目掛けて、大きく踏み込みながら忍刀を突く。 飛び退いた馬手は、空中で血塗れの太刀を掴み取った。 「頭を割ったつもりだったが。悪く無い反応よの」 桂杏に傷はない。忍刀は、馬手の脇腹に刺さって一筋の体液を流させている。 だが、桂杏は顔色を変えた。 「ジルベールさん!」 背後から肩口を深々と斬り裂かれたジルベールが、片膝を付いている。 鎧虫が太刀を咥え、防御のできない死角からジルベールを襲ったのだ。 「ラヴィ‥‥すまん、帰れへんかも‥‥」 まだ立てる。戦える。だが、脳髄が灼き切れそうな痛みがジルベールの意識を朦朧とさせていた。 馬手の足が、宙に浮いた。 ● 西から、早くも門の限界を伝える狼煙が上がっているのが見える。雪喰虫の群れは明かりの無い一帯に降り立ち、家々を白く埋め尽くしていた。 「くそ、一気に来やがった」 「下がれ! 下がれ」 東門の侍三人が、叫びながら後退する。 一人は刀を失い、脇差も折れ、肩から止めどなく血を流している中、四体の百足が、まとめて路地を突進してきたのだ。 刹那、百足達のど真ん中に黒い影が舞い降りた。 「あ」 影が地に片手を付き、夜風が影に吸い込まれていく。渦巻く大気に外套が舞い上がった。のし掛かろうとした百足の前半身が、風圧に押されて横に傾く。 風圧が不可視の刃となり、四体の百足を出鱈目に切り刻んだ。 「下がれ、五丈後ろは霞澄の閃癒の範囲内だ! 古い刀が家の前に転がっている、拾え!」 影、ウルシュテッドが怒鳴った。のしかかる百足の下から間一髪で逃れ、置き土産とばかりにその腹を忍刀で突く。 「わ、悪い、助かる!」 「言ったろう、共に足掻くってな」 風神で百足四体を更に切り刻み、ウルシュテッドが前方へと身を投げ出す。途端、篝火を焚いた家の屋根から数本の矢が降り注ぎ、百足の身体に突き立った。 「精霊さん、みんなの傷を癒してあげて‥‥!」 霞澄の声と共に、後方へ下がった侍達を白い光が包み込んだ。 「ウルシュテッドさん‥‥! 西門が限界のようです、一度‥‥」 「頼んだ!」 岩造りの家越しに、ウルシュテッドが叫ぶ。 「お願いします‥‥皆さん、戻ってくるまで、できるだけ傷を受けないように‥‥! 少しずつ、撤退戦を‥‥!」 悲痛ささえ漂う霞澄の声と共に、草履の音が遠ざかっていく。 ウルシュテッドは新たな敵を求めて路地を駆け出した。 「頼むぞ、ジル‥‥!」 ● 轟音が森を揺らし、鳥達が一斉に空へと逃げ始めた。 「その首、置いてけえぇぇっ!」 雷鳴の如き大音声と共に、白い稲妻と化した一太刀が地面に突き刺さった。 ブーツの足首まで森の地面にめりこみ、振り下ろした刀身を物打ちまで食い込ませたアルクトゥルスが、舌打ちと共に顔を上げる。 転倒していた馬手の顎がぱっくりと裂け、原色の体液をとめどなく流し始めていた。 「ちっ」 舌打ちと共に引き抜かれた同田貫に、アルクトゥルスの全身から発せられるオーラが圧縮され、松明のように輝き始める。 「おのれ小娘」 「ジルベール君!」 熾弦の扇から放たれた光の塊が膝をついたジルベールの身体を照らし出す。 「‥‥熾弦さん?」 「間一髪ね」 着地の衝撃で地面にめり込んだ高下駄の歯を引き抜き、熾弦が安堵の息をつく。 不意を突いた砂魚の空撃砲が馬手の身体を薙ぎ倒し、そこをアルクトゥルスの渾身の一太刀が狙ったのだ。 追いつく場所が近ければ、後続との時間差も小さい。馬手は、自らの読みが外された事を知った。 馬手の判断は迅速だった。 「退かせてもらうぞ。儂を追える者を潰してからな」 その複眼は、手負いの桂杏を捉えていた。 中央に、東を向く馬手。その東西南北にそれぞれ、桂杏、砂魚、ジルベールと熾弦、アルクトゥルス。 馬手が地を蹴った。砂魚のクルマルスが火を噴く。空気の塊に痛打されて馬手の跳躍の軌道が変わり、着地点が大きくずれる。 早駆で闇に溶けた桂杏が馬手の背後に現れ、その頸椎に刀を突き下ろした。 咄嗟に身を捩った馬手の肩に、忍刀の鋒が突き刺さった。が、馬手の右手が桂杏の膝裏を掬って体勢を崩し、鋒が馬手の身体から外れる。 盾を翳したアルクトゥルスが猛然と馬手目掛け突進した。馬手は鎧虫を伸ばして迎え撃つが、その勢いは全く止まらない。 「一人では英雄たりえぬ者、されど英雄のあるべきを知る者。その行く先を切り開く力たらんと‥‥!」 朗々たる熾弦の歌声が木々の葉を震わせた。翡翠色の精霊力の粒子が撒き散らされ、アルクトゥルスの胸の紋章が淡い緑色に輝く。 左足で大きく踏み込み、輝く同田貫を袈裟懸けに振り下ろす。馬手の鎧虫が甲殻の丸味を利用して受け流す。後足を蹴り、右へすれ違いざま同じ軌道で斬り上げる。鎧虫の甲殻が叩き割られ、体液が飛び散った。馬手はすれ違うアルクトゥルスの膝を駆け上がって顎を蹴り上げ、後方へ鎧虫を伸ばす。 踏み込んだジルベールは、アルクトゥルスの身体に遮られて進めない。 馬手の降り立つ先には、体勢を崩された桂杏がいた。景則が桂杏の腿に突き刺さる。血飛沫を上げながら、桂杏の身体が鎧虫に薙ぎ倒され、茂みの中へと突っ込んだ。 「流石に五人相手に遊んではおれぬわ」 馬手は地を蹴ろうとし、破裂音と共に大きく体勢を崩して、頭から木に叩きつけられた。 「逃がしませんの」 練力を火薬代わりに放った、砂魚の空撃砲だった。 ジルベールとアルクトゥルスが、熾弦の歌声に炯々と目を輝かせ、地を蹴った。 ● 西門目掛けて走る霞澄の周囲に、篝火の明かりが届かなくなった。 屋根の上から霞澄へと、百足が落ちかかってきたのだ。躱そうと横に跳んだものの、ローブの裾へと百足の身体が落ち、霞澄は派手に転倒してしまう。 ローブの裾を足で手繰り寄せるように、百足が霞澄に近付こうと動き出した。 「伏せて下さい!」 叫び声に続き、爆音が家々を揺るがした。鉄菱と爆風を浴びて地面に薙ぎ倒された百足へ、霞澄の焙烙玉が放られる。 反射的に百足は霞澄の焙烙玉に齧り付こうとし、一撃で頭を吹き飛ばされた。 「光広さん‥‥どうしてここに‥‥?」 霞澄が目を丸くした。避難所で負傷者の手当をしているはずの光広が、百足に焙烙玉を放ったのだ。荒い息をついている光広は、気の毒なほど顔が青く、足が震えている。 「かか火薬玉が新しくできたので、西へ届けようと」 「ああ‥‥それで‥‥」 霞澄は納得した。共に西門を目指して鉢合わせたのだ。 「でも、外に出るなら侍さんと一緒に出て下さいね‥‥? 火薬玉は、私が届けますから‥‥」 「お、お願いしま、します」 光広は、震える手で霞澄に火薬玉の入った木箱を手渡す。 霞澄は辺りを見回し、虫の気配が無い事を確かめると、そっと光広の前に屈み込んだ。 「光広さん‥‥」 「は、はい」 「‥‥自棄に、なっていませんか‥‥?」 光広の黒い瞳を、霞澄の銀色の瞳が覗き込んだ。 「‥‥繋がりが無いなんて言わないで‥‥絆は、例え遠く離れても、仲違いをしても心のどこかに残るのです‥‥」 光広は一瞬きょとんとし、先刻雲雀の事を任された時の事を言われていると気付いたか、はっとした。 「大丈夫、ちゃんと繋がっていますよ‥‥雲雀さんも重邦さんも、他の皆もそして私も貴方を一人になんてしません‥‥」 霞澄が、ひたと光広の目を見据えて言う。 「貴方はもっとわがままに、『我』がままに‥‥自分の思う道を進みなさい‥‥」 光広は、こっくりと頷き微笑んだ。 霞澄は微笑み返し、光広の両肩をそっと掴む。 「いいですか、戻ったら、避難所でできるだけ、松明を作って下さい‥‥」 「松明? ですか」 「松明です‥‥上を見て‥‥」 霞澄は、視線を上へ向けた。 「雪喰虫は、龍の炎を浴びて火を避けるようになっています‥‥だから」 「なるほど。わかりました」 光広は頷くと踵を返し、左右を慎重に窺いながら、避難所へと戻っていく。 確かに無事光広が避難所の扉へと消えていったのを確認し、霞澄は再び西門へと走り出した。 ● 「生き延びろ、敵を討て! 一人も欠ける事無く朗報を待とう!」 傍の民家の屋根から、ウルシュテッドの叫び声が聞こえてくる。 (広高。見ているか) 姫百合は牙を打ち鳴らし、黒く焦げた表面の象牙質を叩き落とした。 (それぞれが自らの足で立つ者達の、何と力強く、美しいことか) 姫百合の口が大きく開いた。山吹色の業火が蟷螂の身体を包み込む。蟷螂は炎の中で暫くもがいていたが、じきにただの薪と化した。 (我々は英雄になったつもりで、その実、信じていなかったのではないか。人を、他者を) 蟹が、その鋏で侍を捕らえた。途端、その胴に猛然と姫百合が噛みつく。 遠雷の如き唸りを上げ、姫百合が蟹の甲殻を噛み砕いた。蟹は侍を放し、虚しく六本の足と二本の腕を宙で泳がせる。 (何という、恥ずべき怯懦ではないか。かくも力強き者達が、我々の傍にはいたのではないか) 姫百合は思い切り首を振り回し、蟹の身体を岩盤に叩きつけた。眼柄を叩き折られた蟹は、虚しく藻掻くだけの奇怪な置物と化する。 「ここで終わりじゃないぞ、姫百合」 姫百合が首をもたげると、屋根の上に立ったウルシュテッドが、姫百合と同じ目の高さで笑っていた。 「新しい世とは皆が共に築くもの。襷の行く末を見届けてくれなくては」 姫百合は目を細め、新たな敵を見つけて飛び出していくその背を見送った。 ● 「さあ馬手童子、たった一人のあなたに、これを超えることができる?」 熾弦の高らかな歌声が生み出す翡翠色の光の粒子は辺り一帯に遍く広がり、アルクトゥルスとジルベールの動きに合わせて波濤のように踊っていた。 盾を翳して突進するアルクトゥルスの左手が霞む。毛皮で覆われた小盾が放られ、馬手の顔面に掛かった。馬手は額でそれを叩き落とし、体を開く。 全身全霊を込めて振り下ろされた同田貫が、鋒だけで馬手の腹を浅く斬り裂いた。 全く怯まず、馬手が逆袈裟に斬り上げる。熾弦の歌に背を押され、アルクトゥルスは臆せず踏み込む。太刀のはばき元が鎧の表面に食い込み、物打ちが空中で止まった。刃は、アルクトゥルスの腰骨を僅かに削って止まる。 馬手の身体が、宙に浮いた。白銀のガントレットが、馬手の水干の胸倉を掴み上げているのだ。 同田貫を捨てたアルクトゥルスは獅子の如き咆哮を上げた。手甲に覆われた右手が緑の光跡を曳き、馬手の身体に深々と突き刺さる。 その手には反りの浅い短剣が握られていた。馬手の鎧虫が万力の如き力でアルクトゥルスの兜に食らいつき、水干を引きちぎって白銀の鎧を引きはがす。鎧虫はアルクトゥルスの頭を咥えたままその身体を振り回し、地面に、木の幹に叩きつけた。 ジルベールが緑の光と赤い花弁を纏い、地を蹴った。逃れようと馬手は鎧虫を伸ばし、木に食らいつかせる。 「油断は」 砂魚のクルマルスが、火を噴いた。 馬手は咄嗟に足を砂魚の方向へ出し、衝撃に備えて身体を前傾させる。 その複眼に映る銃口の異変に、馬手はまだ気付いていない。 「‥‥大敵ですの」 銃口から噴き上がった火は、瞬き一つせぬ間に爆発的に巨大化し、殺意の火球となって鎧虫目掛け驀進を始めていた。 馬手は自らの迂闊さを呪った。砂魚が空撃砲しか撃たない事から、空撃砲の他に今使える技とは限らないのだと勝手に思いこんでいたのだ。 火球は鎧虫の先端に食らいつき、呑み込み、牙を粉砕し、喉の奥を焼き尽くしながら、その先端四尺を一撃の下に炭化させた。 鎧虫が、酒に落ちた泥鰌の様に激しくのたうつ。 「綺麗な華には、棘がありますの」 膝射の姿勢で、砂魚が囁く。 「おのれ。おのれ!」 怒り狂った馬手の鎧虫に薙ぎ払われ、砂魚の身体は吹き飛ばされて地面で跳ねる。 「砂魚さん!」 ジルベールが叫ぶ。だが、砂魚は受け身を取り、柔らかな狐尾を下敷きに尻餅をつきながら、更なる火薬を装填していた。 馬手は頭を失った鎧虫を伸ばし、木の幹に絡みつかせる。 刹那、闇が蠢いた。 木陰から、ぬらりと妖しく光る銀色の刀身が生える。 それはまるで獲物を襲う蛇の牙の如く、鎧虫の付け根に差し込まれた。刀身は厚い装甲の隙間から半ばまで抉り込まれ、銀光を曳いて捻り抜かれる。 鎧虫に弾き飛ばされ茂みに突っ込んだ桂杏が、失神したふりをして馬手の意識から外れ、符水で傷を癒し、早駆で先回りしていたのだ。熾弦の歌が光となり、ジルベールとアルクトゥルスの援護をしていた事もまた、馬手の意識を桂杏から外させていた。 「貴様!」 頭を失った鎧虫が放たれる。炭化した鎧虫の先端に左手を置き、桂杏の身体が上下逆転する。がら空きになった馬手の左肩、鎧虫の付け根へ、全体重を掛けた忍刀が突き刺さる。抉り込まれる。捻り斬られる。 重い音を立て、鎧虫が地に落ちた。悲鳴を上げて地を蹴った馬手の前に、丈高い人影が立ち塞がる。 「俺らはな、みんなの気持ちを持って来とんねん」 ジルベールだった。反射的に、最短距離を最速で、景則の鋒がジルベールの左胸を突く。 熾弦の歌を聴き高揚したジルベールの意識は、興奮状態を越え止水の如く澄み渡っていた。馬手の姿勢、視線、太刀の反り、角度、全てを視界に収めながら、硝子細工を扱う様にそっと刀を左脇に構える。 刺突に適さない猪首鋒が、鎧の表面を削り、滑り、左鎖骨と頸動脈の上を掠め、耳を裂き、後方へ抜ける。 古釣瓶が、閃光と化した。 椿が落ちるかの如く、右腕が地に落ちた。 腕ごと右顔面を断ち割られ、馬手は驚愕の表情のまま両膝を地に付く。 乾いた破裂音が、森を揺らした。 「私たちが居る時に襲ってきたのが、そもそもの間違いですの」 練力を使い果たした、砂魚の銃撃だ。水干の胸に、じわりと体液の染みが広がり出す。 支えるものを何一つ持たない馬手は、あっさりと、地に倒れ伏した。 ● 雪喰虫の群れは、子龍達の炎を嫌ってあっさりと魔の森へと散り始めている。 「私たちだけが勝っても仕方ありませんの。急いで戻らないといけませんけれど‥‥」 砂魚が地面にぺたんと座り込み、見え始めた星空目掛けて息を吐いた。 「刀探しの筈が、連戦に継ぐ連戦で、もうくたくたですの」 「結構危ない所やったしな」 ジルベールが大きく息を吐き、ぴくりとも動かず瘴気を発して消え始めた馬手を見下ろす。 「テッドさんや霞澄さん、村のみんなも、大丈夫やろか」 熾弦は、木々の間から見える西の岩山を見て、口元をほころばせる。 「間に合わない心配は要らないでしょう。あそこには仲間が2人、いえ、もっと多くの勇士が守っているのだから」 閃癒の暖かい光が、仲間達の傷をみるみる癒していく。 「‥‥東門の前の虫が、完全に烏合の衆になっています。一部残敵の掃討は必要でしょうが、問題ない数でしょう」 桂杏が目を細め、岩山の様子を観察している。 「凱歌を上げる位しか仕事が残っていないかもね」 「勝利の美酒に酔う仕事も残ってるぞ」 アルクトゥルスが笑い、右手を大きく回した。 それを見た子龍達は鳴き声を上げ、翼を広げて着陸できる場所を探し、旋回を始めた。 ● ‥‥いつの時代とも知れぬ、青空の下。 まばらに立つ木々の下、鮮橙色の花が一面に咲き誇っていた。 「この遺跡さ、あんまり使われなかったんだろうな」 花畑から突き出した岩山を下り、一人の男が呟く。後に続く女が首を傾げた。 「昔、この辺りに魔の森があったって言うじゃない? 作られてすぐ、アヤカシに滅ぼされたとか」 「それにしちゃ、破損が少ないぜ。作ったけど、数十年から百年で捨てたって感じだ」 岩山を降りた男が、咲き乱れる花の中の突起物につまずき、軽くよろめく。 「何で要らなくなったわけ?」 「さあ‥‥不便だったか、魔の森が無くなったか‥‥」 二人は言いながら、岩山を背に歩き出す。 「百合の花か」 「姫百合の花ね。花言葉は、誇り」 岩山の前で一面の姫百合の花に埋もれていたもの、それは錆に覆われ半ばで折れた、兜の前立てだった。 |