力−暴−
マスター名:村木 采
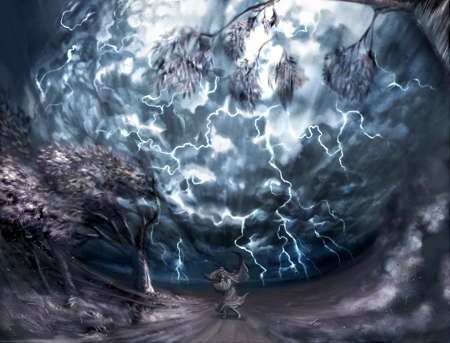
|
|
| ■オープニング本文 前回のリプレイを見る ● 開拓者のいない村は、時ならぬ騒ぎに包まれていた。 飛来する矢のことごとくが水干を貫いて硬い音を発し、停止する。 針鼠のようになった童子は、大きく「左」手を振った。途端、刺さっていた矢が力なく地面に落ちる。 「畜生‥‥!」 侍達は歯噛みした。 襟元に覗く首も、袴の裾から覗く足も、黒い甲殻に覆われている。水干の左袖からは、同じく甲殻に覆われた人型の腕。その掌には、淡く白い輝きを放つ宝珠が乗っている。 馬手童子とは逆だ。左腕、弓手だけを持っている。 「下らぬ」 弓手童子とも呼ぶべきアヤカシの右袖から、分厚い鎧を纏った芋虫が飛び出した。芋虫は十五丈近くその体を伸ばし、岩造りの庇に噛みつくや、本体の童子を引き寄せた。童子は空中で引き戻した鎧虫を、大弓を構えた侍へと放つ。 侍の身体が岩造りの建物に叩きつけられ、五人張りの強弓が地面に転がった。 「シンギョクが無いなら、貴様等なぞただの餌よ」 壁に押しつけられた侍は必死に足掻き、鎧虫の口を僅かに押し返す。岩を砕くほどの力は、この鎧虫には無いようだ。 「しんぎょく‥‥?」 「知らぬ者は、死ね」 鎧虫が大きく脈動し、その喉から深紅の炎が噴き出した。悲鳴を上げて身を捩る侍の髷に火が移り、髪と肉の焦げる臭いが漂い始める。 その時、爆音が轟いた。 「おじさん! こっち!」 傍の鉄扉が五寸ほど開き、小さな手が侍を呼んでいる。童子は咄嗟に宙へ舞い上がり、鎧虫の顎が侍の身体から外れていた。 侍は必死に岩盤の上を転がって鎧虫から距離を取り、身体に点いた火も消しきらぬまま、鉄扉へ走り出した。 その背に迫った鎧虫目掛け、鉄扉から出た老人の腕が、子供の頭ほどの大きさをした白い玉を投げつける。 再度爆音が轟き、侍を追う鎧虫の軌道が僅かに逸れた。 侍が転がり込むや鉄扉が閉じられ、その脇の壁を鎧虫の牙が削る。 「面白い物を使うな、ヒトよ」 鎧虫の甲殻に、焦げ跡がついていた。弓手童子は鎧虫を袖へ戻し、灰色の舌で唇を舐める。 「未だ心は折れぬか。箱の中の餌と、幾許かの戦士と‥‥どちらを狩り、どちらの戦意を削ぐべきかの」 童子は掌に乗せた宝珠に力を込めた。 宝珠の放つ光が脈打ち始め、村の中に侵入した百足は、村の外壁を這い上がって外へと撤退を始める。 固く閉ざされた鉄扉を見やり、童子は歪な笑みを浮かべた。 「まあ良い、時間は稼いだ。後は開拓者さえ居らねば、餌が残るのみよ」 ● 「どこかへ行ったようです。百足も」 村に逗留している少年、野込光広が安堵のため息をつく。閂を掛けた両手は震え、膝は笑っていた。 老鍛冶と家主に身体の火を叩き消された弓使いが、床に転がって荒い息を吐いている。 「符水を貰うぞ」 老鍛冶は、長持ちを勝手に開けて中を漁り出す。 「あやつ、馬手童子に似とったが、能力は全く違うの。鎧虫が非力だが、恐ろしく長い」 額に浮かんだ汗を拭い、家主の男が侍を見下ろして呟いた。 「何でわざわざ助けるんだ、こんな連中」 「当たり前でしょ、このおじさん達がいなかったら、アヤカシと戦えないんだから」 光広の妹、襷で小袖を縛った雲雀が、両手を腰に当てて唇を尖らせる。 志体持ちの光広が震えているのに比べ、志体の無い雲雀は落ち着いたものだ。 「それともおじさん、代わりにアヤカシと戦ってくれるの?」 睨まれ、家主は口籠もった。 「いや‥‥そりゃあ‥‥」 鎧を脱いだ弓使いが、傷が痛むのか顔を歪めた。 「あの爆発は、火薬か」 「はい。開拓者の方の焙烙玉が効いているようでしたから、作ってみました」 光広が答えた。 「もちろん、あの方々の攻撃には比べるべくもありませんが」 「‥‥その、助かった。礼は言っておく」 「いいえ」 光広は微笑んだ。 弓使いは頭を掻き回し、老鍛冶の顔を見上げた。 「それより爺さん。シンギョクとかいうのを知っているか。馬手もどきが探していた」 「心玉‥‥心玉じゃと」 老鍛冶は目を丸くする。 「確かにそう言っとったのか」 「知ってるのか」 侍は身を乗り出した。 「姫百合が儂等との意思疎通に使っとった宝珠が、心玉じゃ。何故アヤカシが心玉を知っとる」 老鍛冶は口を真一文字に引き結び、床を睨んで思案を巡らせている。 「姫百合? 広高が乗ってたとかいう龍か」 「心玉の名前を知っとるのは‥‥」 老鍛冶は立ち上がると、義足を引きずって壁に立てかけた斧を取った。 「おじいさん、どこ行くの」 雲雀が慌てて立ち上がる。 「見張り櫓じゃ。あのアヤカシの、時間を稼いだという台詞が気になる」 鉄扉を開けると、老鍛冶は返事も待たず外へと飛び出して行った。 ● 西の空が、僅かに赤味を帯び始めている。 梯子の軋みと荒い息づかいが櫓を上がってきた。驚いて見張りの侍が見下ろすと、血相を変えた老鍛冶の姿が目に飛び込んでくる。 「寄越せ」 櫓に上がるや、老鍛冶は侍の手から遠眼鏡をもぎ取った。 「何しやがる、この爺」 「やかましいわ」 老人の視線は東の魔の森から南の谷、西の森へと移動し、そして西門から岩山を下ったその下で止まった。 「どうした」 老人の視線の先を追った二人の侍は、言葉を失った。 南東から、二体の屍龍が岩山へと近付いていくのが見える。 岩山にほど近い木々の陰には、僅かに蠢く人影があった。良く見れば十や二十ではきかない、錆びた鉄の鈍い光沢が見える。 その中に、分厚く傷だらけの鎧兜を身に着けた人影があった。 村を見上げながら、ただ一口ぎらりと光る刀を振るって屍人に身を隠すよう指示をしている。操られているような、ましてや理性の無い者の動きではない。 その姿は、老鍛冶の脳裏に刻まれていた記憶の一部に酷似していた。 「広高‥‥!」 屍人の鎧。刀。鞘。身の丈、身振り。どれ一つ取っても、記憶の中の英雄、広高のそれと寸分も違わない。 嘗ての英雄が、アヤカシを率い、自らもアヤカシとなって村に攻め寄せてきたのだ。 「北! 北だ!」 遠眼鏡を覗く侍が怒鳴った。 百足、蜘蛛、蟹、蟷螂。数多のアヤカシが、街道のある北側から東西へと展開し、岩山を包囲しつつあった。包囲の薄い南側は、谷が横たわっている方向だ。 侍が、櫓から村へと怒鳴った。 「村が包囲されてるぞ! 全員、今すぐ戦闘態勢を」 「おい!」 遠眼鏡を覗いていた侍が、裏返った声を発する。 西門から村を挟んで一里東、魔の森から白煙が立ち上っていた。侍が、手渡された遠眼鏡を片目に当てる。 煙は風に流されることなく、緩慢に広がっていた。 「雪喰虫だ‥‥」 針を獲物の体に刺して血を啜るだけの、一体一体は子供でも手で叩き潰せるような、正に虫同然のアヤカシだ。 だがその数が尋常ではない。まさに雲霞の如き雪喰虫の群れが、魔の森の上空へと広がりつつあった。 東西の門の前には、アヤカシとなった英雄と、弓手童子。空に広がりつつある、雪喰虫の群れ。 逃れようのない死の予感に、侍達は恐慌に陥った。 |
| ■参加者一覧 17歳・女・巫 20歳・女・騎 21歳・女・シ 16歳・女・砲 27歳・男・シ  熾弦(ib7860)
熾弦(ib7860)17歳・女・巫 |
| ■リプレイ本文 ● 開け放たれた東門を、家具や岩、瓦等が満載された荷車が通り抜けていく。 櫓から弓の届く距離に造られた即席バリケードの両端には、油に浸された藁が積まれつつあった。 門を潜ろうとした男が、顎で後ろの荷車を指す。 「古箪笥を持ってきたが、いいのか? こんなもんでも」 「何でも使ってくれ。跨ぎ越せぬ高さと、数で押し切られぬ程度の強度は欲しいからな」 口の端に漆黒の髪紐を咥えた黒い外套の青年、ウルシュテッド(ib5445)がくぐもった声で呟く。 「刀探しに来た筈がな‥‥どうやら俺達は彼に呼ばれたらしい」 その両手は癖のある茶色い髪が邪魔にならぬよう後ろで束ねていた。 「悪い予感は当たるものですね‥‥」 巫女装束の上にローブを羽織った銀髪の少女、柊沢霞澄(ia0067)の面持ちは沈痛だった。榊の杖と黒絹の魔法帽を持つ両手が、きつく握り締められている。 「そうね。やはり、広高君が‥‥」 神衣の上に透き通るローブを羽織った銀髪の女修羅、熾弦(ib7860)は音も無く鉄扇を閉じ、桜色の下唇に当てて形の良い眉を顰めた。 「‥‥とはいえ、広高君と共にいた筈の姫百合が持つ宝珠が消えた、という新たな謎が出来たわけね。今は真相を確かめる暇もないけれど」 「そこ、両側2mは通り道として残しておくんだ」 ウルシュテッドの声が、バリケードへ飛ぶ。 「通り道を限定できればいい。道を塞げば、屍龍に吹っ飛ばされかねない」 髪を束ね終えたウルシュテッドは、喉に下げていたマスクを頬骨の高さへと上げた。 そこへ、櫓の上から声が返ってくる。 「俺達は打って出なくとも、バリケードを越させない、門を開けさせない。これでいいんだな」 東門に作られた小さな櫓二つには、四人ずつが登っていた。弓を持つ者はまだいるが、これ以上は空間的にも重量的にも上がれないようだ。 「それから‥‥仮に敵が下がっても、深追いはなさらないように‥‥門の防衛に専念するようお願いします‥‥」 霞澄が、遠慮がちに櫓へ声を返す。 「あと、壁を越えてくる百足にも注意を‥‥」 「攻め、受け、支援ができる人達で役割を分担して。少しでも効率を上げるように」 熾弦が霞澄の言葉を継ぐ。 その時、白い玉の詰め込まれた木箱を抱えた少年が、その重量に足をふらつかせながら近寄ってきた。 「ウルシュテッドさん。できました」 光広だった。ウルシュテッドは穏やかに目を細め、木箱を受け取って地面に下ろす。 「早いな。ありがとう」 「それは‥‥焙烙玉か?」 侍達が、こぞって木箱の中身を覗きに来る。 「そんなところだ。斜面や壁を上がってくる百足を、これで叩き落とせる」 「そりゃ助かる。櫓からの射撃だけじゃ心許なかったんだ」 侍が火薬玉を手に取ると、櫓の上の仲間へと投げ上げ始めた。 「光広、手間を掛けて済まないが火薬の多い分を二つ、少ない分を三つ、西に届けてくれ」 「はい」 光広は即答し、五つの玉を残した木箱を抱え上げる。 「ああ、それとは別に、光広自身の判断で、火薬の多い方を三つ使ってもらいたい」 「僕がですか」 光広が目を丸くした。 火薬玉を三つ木箱の中に放り込みながら、ウルシュテッドが頷く。 躊躇っている光広に、鈴の鳴る様な声が掛けられた。 「光広さん、私からもお願いします‥‥」 霞澄だった。足を止めた光広の前へ歩み寄り、膝に手をついて腰を屈める。 「これも。お守りです‥‥」 その右手が差し出したのは、光広が作った物よりも一回り大きな焙烙玉だった。 「雲雀さんを守ってくださいね‥‥」 霞澄は焙烙玉を木箱の中に入れ、そっと光広の頭を撫でた。 光広は暫し焙烙玉を見つめて迷っていたが、やがて霞澄の銀色の瞳を正面から見つめ、頷いた。 「分かりました。繋がりは無くとも、妹ですから」 霞澄は大きな目を瞬かせた。光広は焙烙玉を抱えて東門を見上げる。 「光広さん‥‥?」 「村の皆さんがどこかにまとまっていた方が、皆さんとしても守りやすいでしょうか」 「‥‥あ、はい、村の中心近くに大きな家があれば、そこに纏まって避難して頂くのが良いかと‥‥それから、雪喰虫への対応も‥‥」 違和感に捉えられていた霞澄は、少ししどろもどろになりながら答える。 「隙間を目張りしておけば良いでしょうか」 「そう、ですね‥‥あ、すぐ閉められるようにした空気穴を残しておいて下さいね‥‥?」 「わかりました」 光広は力強く頷き、開拓者達に背を向けて走り出す。 「あの、‥‥」 慌てて霞澄が声を掛けると、ぴたりとその足が止まった。 光広はくるりと振り向き、両手で焙烙玉を胸に抱えたまま、 「御武運を、お祈りしています」 深々と頭を下げ、角を曲がって路地裏へと消えていく。 胸に掛かる銀髪を指に絡め、じっと考え事をしていた霞澄に、ウルシュテッドが声が掛けた。 「霞澄、どうした」 「‥‥いえ、‥‥今は、村の防衛に専念しましょう‥‥」 疑念を振り切るようにして、霞澄は顔を上げた。 「雲雀さんや光広さん、そして今生きている人達を守る為に‥‥」 ● バリケードを築く騒音に包まれた東とは対照的に、固く閉ざされた西門は奇妙な静けさに包まれていた。 神威人の愛用する厚司織に皮の外套を羽織っただけという軽装の少女、十砂魚(ib5408)が、弾丸と薬包の数を確かめながら愛らしく唇を尖らせる。 「似た様なのがもう一匹。面倒が増えましたの」 その尻から生えた黄金色の尾は、傾きだした陽の光を浴びて橙色に輝いている。 「ま、隠密組が動き易い様に派手に立ち回って、あわよくば弓手討ち取りを狙おうか」 身の丈六尺近いアルクトゥルス(ib0016)の白い鎧の上に、鷲の頭を象った兜が乗る。細く凛々しい眉と切れ長の目が、赤い面頬の裏に隠れた。 「おい、あんたら‥‥立ち回るって、何の話をしてる」 侍に聞かれ、アルクトゥルスはさらりと答える。 「ん? 殻に籠って守ってばかりは性に合わん。打って出る」 『打って出る!?』 目玉を剥いた侍達の声が唱和する。 「俺達もかよ」 「あんた、正気か?」 「死ねってのか」 「どう戦う?」 アルクトゥルスがひょいと肩を竦め、胸甲と肩当てが擦れて音を立てた。 「籠城ってのは、外から救援が来るからこそ意味があるのだしな」 「‥‥そりゃ、そうだが‥‥」 「あの中に切り込むってのは‥‥」 侍達は兜の下で互いの顔を窺っている。 だが、 「囲まれたら終わりですの」 砂魚の一声で、一同はぴたりと口を噤んだ。 銃口に流し込んだ火薬を突き固めながら、普段の大人しく穏やかな様子からは想像もできない、断固たる口調で砂魚は言う。 「ここが、勝負所ですの」 「心配しなくても、怪我は私と霞澄君がまとめて治療してあげられるから」 彼らの迷いを読み切ったかのように声を掛けたのは、東門に指示を与え戻ってきた熾弦だった。その隣を、高下駄の分だけ身の丈が低い霞澄が歩いている。 砂魚が、一尺ほども身の丈の違う熾弦を見上げた。 「東門の準備はもう終わりましたの?」 「村の巫女に治療や支援はお願いしてきたわ。バリケードも焙烙玉もあるし、打てる手は打った筈」 「お疲れ様ですの」 整備と装弾を終えた愛銃「クルマルス」を肩に担ぎ、砂魚は居並ぶ侍達の方へと向き直った。 「それから、この状況で賞金目当てに馬手に突っ込む人は居ないと思いますけど」 その一言で、抜け駆けを狙っていたか、或いは町に攻め込んできた所を狙うつもりでいたらしい侍が二〜三名、視線を泳がせた。 あきれ顔で、砂魚はしっかりと釘を刺す。 「額は魅力的ですけど、受け取る前に確実に死にますの」 砂魚は、確実に、の部分に力を込めた。 「協力と団結をお願いしますの」 「‥‥分かったよ」 渋々と、図星を衝かれた侍が頷く。 「個人でバラけず2〜3人で組んで戦っておけ。虫に捕まった時、お互い助け合える」 鎧の留め金を一つ一つ入念に確認しながら、アルクトゥルスが助言を与える。 「死んだら金も貰えんし酒も呑めんぞ」 「玉砕するってんじゃ、ないんだよな‥‥?」 「自分次第だ。それが戦だろうに」 アルクトゥルスは威勢良く言い、侍の背を思い切り叩いた。 「それが嫌なら各自奮励しやがれ」 「痛えな!」 抗議の声を右から左へ聞き流し、アルクトゥルスは西門の門番に目で合図を送る。 西門が、ゆっくりと開き始めた。 「それから櫓に上がる人に、これを渡しておきますの」 砂魚は、雲雀達に命を救われた弓使いに狼煙銃を二丁手渡した。 「雪喰虫に動きがあれば白、馬手が現れたら青、それ以外の緊急事態なら赤でお願いしますの」 弓使いは神妙な面持ちで狼煙銃を受け取り、深く頷く。 「雪喰虫の、何かを待つ様な動きが怖いですの。包囲完了後に一気に襲ってくる気なのかも知れませんの」 言われ、侍達は一斉に東の空を見る。 東の空は、申の刻を間近に控えて暗くなり始めていた。 「広域を俯瞰できる人は重要ですの」 「解った。何かあった時は頼む。お前達が来ると思えるだけでも、士気は大分変わってくるからな」 砂魚と弓使いは頷き合う。 「東門は、何とか守る‥‥ように努力する」 「お願いしますの」 腹を括ったか、弓使いは大きく息を吐いて東門へと歩き始めた。 日陰に立って東の空を凝視し、微動だにせずにいた桂杏(ib4111)がぽつりと呟いた。 「蟲を操る両童子を倒したとして」 その顔と絞られた肢体は忍面と忍装束で守られ、その上に草木に紛れやすいよう蓑を着けている。外から見える部分に金属は一切纏っておらず、動かずにいるだけで影に同化するかのようだ。 「集められたアヤカシの群れはその後どうなるのでしょう」 誰もが想定していなかった疑問に、一同はふと口を噤んだ。 桂杏が続ける。 「宝珠で統率されているとして、それを失ったあと大人しく魔の森に帰るとも思えません。バラバラに行動を始めるものを、個別に撃破していくことになるはずです」 「‥‥け、けどよ、今のこの状況よりはマシだよな」 すがるような口調で、侍の一人が言う。桂杏は静かに頷いた。 「勿論、村を包囲しているアヤカシについてはその通りです。しかし雪喰虫の大群相手にその手法が取れるかと言ったら‥‥」 侍達の顔が引き攣った。 「しかしだな」 アルクトゥルスが口を開く。 「結果として村は包囲されつつある訳だが、こいつら連携を取っているのかな?」 「と、言うと」 聞き返す桂杏の顔を、面頬の奥から赤い瞳がちらりと窺った。 「心玉とやらを巡ってアヤカシ間の派閥争い的な事に巻き込まれてやしないだろうな?」 言われ、桂杏ははたと考え込んだ。 「あり得ない話では、ありませんね」 「まあ、どちらにせよ今やる事は変わらないわけだが」 西門が開ききった。まだ岩山の道にも斜面にも虫の姿はない。 熾弦が懐から金の懐中時計を取り出した。開拓者が事情を聞いてから、既に半刻。いつ虫達が侵攻を開始してもおかしくない時刻だ。 開拓者達は視線を交わし合うと二手に分かれ、三人が侍達を率いて門を潜り、三人は村の外壁沿いに走り始めた。 ● あと一度道を曲がれば岩山につけられた道を抜けようというその時、熾弦の高下駄の音が止んだ。やや遅れて、侍達が足を止める。 「どうした」 「やっぱり、包囲は完了してたみたいね」 熾弦が閉じた鉄扇で道の先と周囲の岩場を指す。 「角の先にいるわ。想像してた数よりも多いから、気をつけて」 アルクトゥルスが同田貫の鯉口を切り、逆五角形の盾をかざしてゆっくりと角へ近付いていく。 風に鳴る葉擦れの音が、遠い潮騒のようだ。喩えようもない禍々しさが辺り一帯に漂っている。 「その割には、静かだぜ。本当にいるのかよ」 「いるわね」 断言する熾弦を、侍達が見る。 「何で解る」 「余所見しないで」 熾弦の鋭い叱責で、一斉に侍達が前方に向き直った。 「瘴索結界に反応があるわ。上から降ってくるから、大きな岩や太い木を背にしないように。アルクトゥルス君が言った通り二人か三人一組になって、背中はお互いが守り合って」 侍達がうそ寒そうに、手近な大岩を見上げる。 その瞬間だった。薄暗がりに紛れる黒い甲殻が、無数の足を蠢かせて猛然と岩陰から飛び出してきた。 先陣を切った一匹が前を横切った瞬間、アルクトゥルスの右手から走った銀光が百足の胴を薙ぎ払う。 「戦と美酒があれば世はコトもなし!」 アルクトゥルスはどこか楽しそうに吼え、百足の胴を蹴飛ばした。 「ええい、ちゃんと治してくれよ!」 侍の一人が怒鳴るや、残る侍もそれぞれに獲物を掲げ、半ば自棄とも思える勢いで虫達に突っ込んでいく。 勢いはあるが無策な突撃に、アルクトゥルスが呆れ顔を見せた。 「根性あるのやら無いのやら‥‥っと」 殺気を感じ取ったアルクトゥルスは盾を翳し、そこへ錣を思わせる黒い筒が激突した。盾に食らいついた筒は、そのまま持ち主の胴へ牙を打ち込もうとする。 鎧虫だ。 「貴様等が開拓者か」 黒い甲殻に覆われた弓手童子本体は岩の上に姿を現していた。 刹那の押し合いの後、アルクトゥルスは突如盾を引き寄せられてつんのめった。 虫達の只中へと彼女を引きずりながら鎧虫が脈動し、その口から炎を噴き出した。 が、アルクトゥルスの左足が力強く大地を踏みしめ、引きずられていた身体がその場に止まる。 鎧虫の収縮は止まらず、引き寄せる者と引き寄せられる者が逆転した。 横薙ぎに振るわれる刃を弓手は左腕で受け流し、白銀の胸甲を蹴飛ばして後方へ飛ぶ。アルクトゥルスは激しく首を振り、兜から零れる銀髪についた火を消した。 直後、着地した弓手の周囲の風景が歪んだ。 「虫と同じようにはいかない、か」 若干背の高い銀髪の侍が小首を傾げ、前立ての欠けた兜を放り捨てる。金属の折り鶴を連ねた簪が、涼やかな音を立てた。 侍に扮していた熾弦が、力の歪みを放ったのだ。弓手の水干に緑色の体液が滲み始め、赤い複眼が熾弦の黒い瞳を睨み付ける。 「小賢しい!」 鎧虫が一つ脈動し、熾弦へと伸びた。アルクトゥルスが地を蹴る。 光の粒子が鎖となって鎧虫に絡みついた。 「精霊さん、熾弦さんを守って‥‥!」 霞澄が、榊の杖を目の前に翳している。神楽舞だ。光は鎧虫を伝い、まさにアルクトゥルスの一太刀を受け止めようとする本体にまでその先端を伸ばして、その身体を締め上げた。 鎧虫から吐き出された炎は熾弦の左足を焼いただけに終わり、同田貫の一振りが弓手の額を削る。 夕刻の空を、火線が横切った。 一拍遅れて届いた轟音に、虫と戦い始めた侍達が跳び上がった。 炎を吐き終えた鎧虫が急激に向きを変えて大岩に食らいつくと、開拓者のいない方向へと弓手の身体を引き寄せていく。 アルクトゥルスと岩との中間点に着地し、弓手は舌打ちを漏らした。 「味な真似を」 厚司織に皮の外套、足袋。腕輪一つを除き反射性の高い素材を殆ど身に着けていない砂魚が、岩陰に潜んで弓手の左腕を狙撃したのだ。 左肘を半ばまで強弾撃の火球に抉られながらも、弓手の掌は宝珠を離していない。 東門から、重い音と怒号が聞こえてくる。 ● 「来たぞ」 開拓者達が西門を出て数分と経たない内に、櫓で弓使いが怒鳴った。 東の森からは隠れる事を止めた屍人や虫が併せて六十以上、岩山を登りだしていた。南北の森の縁には、木陰に潜みきれない虫達が顔を出し始めている。 先頭に一頭の屍龍。その後に百足、蟹、蟷螂がしめて三十ほど。そして三十前後の骨鎧と屍龍に守られた広高が続く。 一町半にも及ぶ、アヤカシの大行列だ。 「敵数、屍龍二、百足二十、蟹十、蟷螂十、死人三十。まだ火矢は射るなよ。普通の矢だ」 定数を超えて櫓でひしめき合う、残り七名の侍達が頷く。 彼らの矢筒には、松脂に浸した布が巻かれた火矢とただの矢が雑多に詰め込まれていた。 「頭数が違いすぎるぜ」 侍が弱音を吐くと、弓使いは引き攣った笑いを浮かべた。 「足の数の違いに比べれば、それくらいどうって事ないだろう」 「なあに、手の数なら負けてねえ」 誰かが震える声で軽口を返す。 「畜生、全然笑えん」 弓使いが歯を食いしばり、手の震えを力で押さえ込もうとする。 屍龍が蜥蜴の様に身体をくねらせ、四肢を回転させるようにして突進してくる。尾骨に跳ね飛ばされた石が岩を動かし、不運な骨鎧が一体押し潰された。 どうやら屍龍を先頭に立たせ、頭数を温存する気らしい。 道幅三丈の中央を突進していた屍龍が、築かれたバリケードを見てその歩みを止めた。全長一丈半、横幅八尺はある体躯が、バリケードの左右に作られた七尺ほどの隙間に頭を突っ込む。 「放て!」 弓使いの号令に従い、八人の斉射が始まった。 ● 東から、立て続けに爆音が響き始めた。斜面を這い上がる百足を、光広の火薬玉で叩き落としているのだろう。 「しつこい奴め」 吐き出される炎を突っ切り、蟷螂と百足を空気の様に無視し、盾を掲げて猛然と駆け抜けてくるアルクトゥルスに、弓手は鎧虫を放った。 「逃がさんよ」 鎧を傷だらけにしたアルクトゥルスは姿勢を低くして蟷螂の一振りを躱し、百足の緩慢なのし掛かりを置き去りに、弓手へと追いすがった。鎧虫を盾で受け止め、同田貫を振りかぶる。弓手はアルクトゥルスの盾を支点として更に後方へ下がる。 その身体は最初の狙撃地点から見えぬ方向、熾弦から離れる方向へと向かっていた。一人で複数の開拓者を相手にする気はないようだ。熾弦と霞澄は、虫に阻まれてそれを追えない。 結果として一人突出したアルクトゥルスが、虫達から両手に余るほどの傷を受けているにも関わらず、巫女達が回復できる範囲外で孤立していた。 「ど畜生! 開拓者がおっ死んだら、死ぬしかねえぞ」 その事実に気付いた侍の一人が怒鳴り、じりじりと前進を始めた。 「回復してもらえんのは俺達だけだ」 「羨ましいか、ざまあみやがれ」 破れかぶれで声を上げ、残る侍達も気力を振り絞って虫の群れを押し返し始める。 「やればできるじゃねぇか」 アルクトゥルスは突進の勢いを緩めず、面頬の奥で口元を緩める。 三度炎と鎧虫の攻撃を突っ切り、二度の蟷螂の捕獲と百足ののし掛かりを躱し、幾度もの攻撃を盾と鎧で受け止め、遂に黒い甲殻の塊と白銀の鎧とが接近した。 アルクトゥルスは右足で地を蹴り、倒れ込まんばかりの前傾姿勢から体を開いて左足を踏み出す。弓手は舌打ちと共に黒い左腕を掲げ、衝撃に備える。 刃肉豊かにつく同田貫の刀身が、精霊力による光跡を曳いて襲い掛かった。 岩山の前に、目も眩むような火花が散る。 「虫も炎もお構いなしとはの」 黒い甲殻に覆われた童子の左腕に、深い切れ込みが入っていた。緑色の体液が一筋、二筋、肘を伝い落ちる。 「戦場での脇目は身を滅ぼすんでな」 アルクトゥルスは更に踏み込もうと一瞬身体を沈み込ませ、それに反応して弓手が後方へ跳ぶ。 「脇目も振らなかった結果、一人突出しておるが良いのか」 森の前へ着地した弓手の唇に、嘲りの笑みが浮かぶ。 が、アルクトゥルスの口の端にもまた、不吉な笑みが浮かんでいた。危険を感じた弓手が地を転がるのと、その肩口から緑色の体液が迸るのとが、全く同時だった。 「すみません、仕留め損ないました」 まるで濡れているかのような光沢を放つ忍刀が、橙色の空を写してぎらりと光る。 侍達に先んじて南の斜面から降り、忍装束と蓑で、夕刻の森に完璧な同化を果たしていた桂杏だった。 「おのれ」 弓手は、斬り裂かれ垂れ下がった右袖を引きちぎって放り捨てる。桂杏が僅かに腰を落として踏み込む素振りを見せ、それを迎え撃つべく鎧虫が炎を吐いた。 と同時に、岩陰で重い音が響いた。弓手が弾かれたように振り向き、桂杏を狙っていた炎は明後日の方向へと散っていく。 そこには、岩の上から降ってきた百足がいた。 「らしくないな、ウルシュテッド殿」 弓手に追いすがろうとしていたアルクトゥルスが、面頬の奥で赤い目を丸くする。 「すまん、躓いた」 黒い外套を纏ったウルシュテッドの長身が、岩の影から析出されるようにして現れた。青い宝石の埋め込まれた金属製の十字架が、その胸元で夕陽を反射しながら僅かに揺れている。 岩陰に同化し、弓手の背後を狙える絶好の位置にいたのだが、不運としか言い様がない。岩と影で死角になった小石で体勢を崩し、百足に気付かれたものらしい。 ウルシュテッドはのし掛かろうとする百足の巨体を難なくいなした。 「すぐそちらへ向かう」 易々と百足の頭節の付け根に忍刀を突き込み、抉り抜く。振り回される尾を肘で上方へいなし、たった今作ったばかりの傷跡へもう一突きを加える。 弓手は唸った。 「最初から、これが狙いか」 潜伏した砲術士による狙撃。弓手の不得手とする力の歪み。後衛に近付く事を物理的・心理的に阻害する神楽舞。アルクトゥルスの強引な突出。開拓者一人一人の一挙手一投足すべてが、甲殻を無化できるシノビ達が待ち構える方向へと弓手を誘導していた。 「そこでは届きません‥‥! あと五尺近付いて‥‥!」 岩山から聞こえる剣戟の音に、霞澄の声が混じった。続いて、辺りを柔らかい光が照らし出す。 途端、 「凄え、痛くねえ」 「村の腐れ巫女とは月とスッポンだ」 早くも気弱になり出していた侍達の声が勢いを増し、剣戟の音が岩山から森へと動き始めた。 「ちっ」 弓手の鎧虫が、森へと伸びる。逃がさじと、桂杏が滑空する猛禽の如くそれを追う。アルクトゥルスはそれに背を向け、鎧虫の伸びる先、本体が逃げる先での迎撃に走る。 鎧虫が木の幹に牙を打ち込む。桂杏が体を閉じ、逆手に握った忍刀を胸の前へ隠す。弓手の両足が、地面から浮き上がる。アルクトゥルスが、空中からの攻撃に備えて盾を上へかざす。 二つの爆音が、森と岩山を震わせた。 ● 屍龍はバリケードと岩の間に肋骨をつかえさせ、苛立たしげに身体をよじっている。 バリケードを乗り越えて近付きつつある百足に、立て続けに矢が射込まれる。いくらかは甲殻に弾かれているが、節に刺さった矢の数々は確実に百足の動きを奪っていた。 屍龍がバリケードを突破するのを待っていた蟹と蟷螂の一部が、バリケードの右端に張り付いた。 「火矢、放て!」 バリケードの両端に仕込まれた木箱に、幾本もの火矢が射込まれた。積まれた藁が燃え始め、一瞬の間隙を挟み、爆音と共にバリケードの両端が吹き飛ぶ。 横倒しになった屍龍は、斜面を滑落し始めた。歓喜の声が櫓から上がる。 右端に張り付いていた蟷螂と蟹は、四体が半丈ほども吹き飛ばされて一緒くたになり、小さな岩雪崩を起こして猛然と岩山を転がり落ちていった。 屍龍の身体は曲がりくねった道の一点で停止していたが、左の大腿骨と上腕骨を砕かれて真っ直ぐに進めず、道を外れて更に滑落を始める。 地面に激突した虫は全て岩に押し潰され、力無く足を動かすばかりになった。 同時に、 「火薬玉、種切れだ」 「こっちもだ」 侍達が叫ぶ。 「百足落とせ、おい、落とせ」 櫓に乗った侍達が、弓を下に向け始めた。食い止めきれなかった百足が、櫓めがけて壁を上がり始めたのだ。 弓使いはウルシュテッドに託された焙烙玉に点火し、四つ数えた所で下へ投げ落とす。 爆裂した焙烙玉は、櫓の骨組みを一部砕きながら、這い上がる百足を吹き飛ばした。 「入ったぞ」 門の裏で待ち構えていた富士額が怒鳴り、壁を越えた百足を六人がかり取り囲む。 バリケードを越えて門の前に虫達は集まりつつあり、巨大な鎌や鋏による攻撃が門に加えられ始めていた。 屍人を率いる広高が、ぎらりと光る刀を振るう。それに呼応し、残る屍龍の瘴気弾がバリケードを粉砕し始めた。 ● 東から届いた爆音が辺りに木霊し消えていく中、森に向かって跳躍した弓手の身体は、桂杏の脇に着地していた。 意表を突かれた桂杏だったが、逆手に握った忍刀の棟を前腕に宛がい、猿臂の要領で零距離での斬撃を見舞う。 だが、それ以上に意表を突かれていたのは、弓手自身だった。自らの額と上顎を吹き飛ばされた鎧虫から体液を撒き散らし、後方へ倒れ込んで致命傷を避けるのが精一杯だ。 東の爆音に重なった轟音は、砂魚の強弾撃だった。 「外殻が硬くても、伸びた状態なら薄くなる筈ですの」 鎧虫の先端が本体を引き戻すために固定される一瞬を、初手の一射から今まで、岩陰に身を隠して待ち続けていたのだ。 狙撃手の仕事は待つ事。その至言を体現した一射だった。 後退する弓手を桂杏は追わず、空いた左手で印を結んだ。弓手は地面で後転し、左手一本で後方へ跳ねて桂杏から距離を取る。 桂杏の右人差し指と中指が柄から立てられた途端、その眼前に半透明の薄い円刃が生まれた。忍刀の一振りに合わせて円刃は虫の羽音にも似た音を立てて回転を始め、鎧虫に襲い掛かる。 「効かぬわ!」 弓手の赤い複眼が光り、その身体を中心として炎が渦巻いた。桂杏と後方から近付いていたアルクトゥルスが跳び退る。 直後、弓手の身体を取り巻いていた炎は赤い光に吹き飛ばされ、辺りへと弾け散った。 「待たせてすまない」 炎は、ウルシュテッドの放った不知火の炎だった。桂杏の水流刃とウルシュテッドの不知火、双方を弓手の発した衝撃波が薙ぎ払ったのだ。 残っていた水干の左袖が水の刃に切り落とされている。が、甲殻に覆われた左腕にも、右肩から生えた鎧虫にも、これまで以上の傷は与えられていない。 「こちらの間合いまで踏み込まないと、お話になりませんね」 桂杏が、アルクトゥルスの左斜め前へ動く。ウルシュテッドを含め、三方から弓手を包囲する格好だ。 ウルシュテッドが忍刀を順手に握り、地に手がつくほどまで体勢を低くした。まるで、跳躍に備え身体を撓ませる猫のようだ。 「同感だ」 桂杏とウルシュテッドの姿が夕闇に溶けた。 「寄るな!」 鎧虫が矢のような勢いで伸びながら回転した。が、近寄る者全員を薙ぎ払う筈の一撃はシノビ二人に受け流され、盾を掲げて前進するアルクトゥルスの鎧に巻き付いた。瞬時に巻き戻ろうとする鎧虫を、アルクトゥルスが鎧の脇に抱え込む。 「離せ!」 鎧虫が不吉な脈動をする。 面頬の奥に、アルクトゥルスの白い歯が覗いた。 「お断りだ」 鎧虫の口が大きく開き、アルクトゥルスの兜を呑み込まんとする。 だが、弓手の赤い複眼は隼の速度で襲い来る二つの影を視界の端に捉えていた。アルクトゥルスの身体ごと鎧虫を引き戻し、その場を離れようとする。 しかし蓑を翼のように広げた黒い影は、重武装の騎士を一人抱えた弓手にいとも容易く肉薄していた。 水干の両袖は切り落とされ、その胴は薄暗がりにもはっきりと露出している。苦し紛れに側頭部を狙う蹴りを、桂杏が肩で受ける。鍼師が経穴に針を打ち込むかの如く、肩の付け根に忍刀の鋒を差し込む。渾身の力で抉り込む。捻り斬る。重い音を立て、鎧虫が地面に転がった。 絶叫を上げる弓手の左腕を、真紅の火球が通過する。 瞬時に装弾を終えて呼吸を整え、狙撃の瞬間をひたすらに待っていた砂魚の三度目の強弾撃だった。射出された火球は、初撃で半ばまで抉られた左肘を完全に粉砕し、地面に突き刺さる。 左上腕だけを残し両腕を失った弓手が、後方へ跳躍した。地面に降り立ったその肩を、大きな手が掴む。 反射的に隣を見上げた弓手の複眼に、身の丈六尺を越えるウルシュテッドの分厚い胸板が映った。 鎧虫を切り落とされた傷口から、忍刀が突き込まれた。 刀身は肩口から胸を貫き、左上腕の甲殻にぶつかる。内部から上腕を持ち上げられた姿勢で、弓手の身体が動きを止めた。 忍刀が抉り抜かれ、噴水の様に体液が噴き出す。 「馬手、まさか、貴様」 その頭が壊れた器械人形のように東を向き、赤い複眼がその周囲から徐々に白く濁っていく。 「勝てぬと承知で、儂を‥‥」 数秒の後、完全に活動を停止した弓手童子はゆっくりと地面に崩れ落ちた。 ● 弓手が倒れた効果は覿面だった。 西門を目指し侍達の前線を突っ切っていた虫は人の臭いに引かれて変わらず岩山を上がっているが、侍と戦っている虫は露骨に統制を乱し、傷の深い個体から森へと逃げ出し始めている。 そして砂魚の狙撃で撃ち落とされた左腕と宝珠は、弓手が活動を停止した途端、煙の如く瘴気を立ち上らせていた。 身体に巻き付いた鎧虫を解いて放り出し、アルクトゥルスが近付いてくる。 「どうだ」 「‥‥縮んでいる」 宝珠の傍に屈み込んだウルシュテッドは碧眼を細め、裏返した紋入胴乱で宝珠を掴み、元に戻して軽く口を縛った。僅かに空いた隙間からは変わらず瘴気が立ち上っている。 「一応、持っておくか」 「縮んでも、消えるかどうかはわからんしな」 二人は頷き、岩山を見上げた。 この一戦で絶大な信頼を得た二人の巫女の下へ、手負いの侍達が我先にと群がっている。 「傷の深い方から順に、こちらへ‥‥動けない方へは、こちらの薬草と包帯を使って下さい‥‥」 「練力はまだ十分に残っているから、焦らないで」 立て続けに三度、閃癒の光が満ち溢れた。 のし掛かった百足に急所を噛まれた者、蟹の鋏に腕を断ち切られた者は治療を受けても身動きできず、仲間に背負われている。 だがその二人を除く侍と開拓者達は、傷一つない所まで回復していた。 「おい、これなら勝てるんじゃねえか」 「ちょっと東の連中の手伝いでもしに行くか」 放置すれば命に関わりかねない傷でさえ完治させられ、侍達はお互いの身体を見て明るい声を上げている。 しかし、 「おい」 侍の一人が岩山の上を見て目を剥いた。 盛大に焚かれた篝火に照らし出され、日が落ちて暗くなった空へと二筋の煙が上がっている。 「狼煙だ」 煙の色の一つは、雪喰い虫が動き出した事を示す白。 そして今一つは、馬手が動き出した事を示す青ではなく、想定外の事態を示す赤だった。 |


