絆―疑心―
マスター名:村木 采
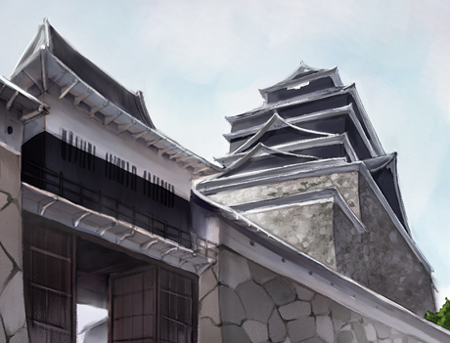
|
|
| ■オープニング本文 前回のリプレイを見る ● 紅樺色に染まる薄暗い部屋の中央に文机を置き、その前に一人正座して、細身の少年が書き物をしている。 少年の名は、元儀光。名目上は武天の使番、嘉木典膳の婿養子だったが、半ば以上は人質だった。 そう、人質だった。 人質として息子を差し出した筈の儀光の父、元儀忠が反旗を翻し、典膳と儀光、儀光の許嫁である待姫の居城へと押し寄せたのだ。 開拓者達の活躍で三名は無事落ち延びたが、最後まで城に立て籠もったもう一人の使番組頭、眉原啓治の行方は杳として知れない。眉原衆は多くが討ち死にし、残った者も散り散りになってどこかへ潜伏しているとも言われていた。 儀忠は躍起になって典膳と待姫の行方を捜しているという。 ● 「儀光さま」 囁き声と共に、障子に小柄な少女の影が映り込んだ。 「入っておくれ」 儀光の声と共に、音もなく障子が開き、振り袖姿の少女、待姫が滑り込んでくる。 「あの‥‥」 待は静かに障子を閉め、儀光の前に小さく正座をした。 「ごめんなさい、儀光さま。お父さまも、気が立っているのです」 「‥‥父を、攻めるのだろう」 待姫は答えない。唇を真一文字に引き結び、何かをじっと堪えている。 「いいんだ。待が気にすることじゃない」 「ごめんなさい、儀光さま。待は儀光さまが大好きなのに」 「わかっているよ」 儀光は筆を置き、そっと待の前にいざり寄った。 「私も、待のことが大好きだ」 途端に、待の瞳から大粒の涙が溢れ出した。 儀光に頭を撫でられながら、待はしゃくりあげつつ、声を絞り出す。 「ごめんなさい。お父さまを止められなくて、ごめんなさい」 「いいんだ。父は、それだけのことをしたんだ」 儀光もまた、苦労しながら声を吐き出した。 「そう思うしか‥‥仕方ない‥‥じゃないか」 少年の声もまた、涙に濡れていた。 「ごめんなさい。儀光さま、ごめんなさい。儀光さまのいいなづけなのに、お力になれなくて、ごめんなさい」 「いいんだ。‥‥待、いいんだ」 年若い恋人達は、互いに膝をつき合わせ、互いの肩に顔を埋め合って、ひたすらにむせび泣いていた。 ● 「待」 青紫色に染まりつつある部屋の中で、自分の背におぶさるようにしがみついている待を、儀光は呼んだ。 「はい」 「‥‥また、夢を見たんだ」 「はい」 「民草のため、逆心を抱く者が二度と出ないよう、断固たる態度を示すべきだと‥‥いずれ牙をむくかも知れないと。私を斬るべきだと、義父上は夢の中でおっしゃっていた」 待は目を開けた。 「そんな!」 「しっ」 儀光は鋭く言った。 「秘密でここに来ていることを、忘れてはいけないよ。本当は、私には誰も会ってはいけないんだから」 「はい」 待は慌てて口を抑え、頷いた。 「そんなこと、待がさせません。ぜったいです」 「無理さ。だって‥‥」 儀光は何かを言おうとし、口を噤んだ。 「だって‥‥何ですか?」 「うん‥‥」 儀光は言葉を濁し、ふと目を遠くへやった。 夜の冷たい風が障子を小刻みに震わせ、乾いた音を立てる。 「父は夢の中で、義父上に討たれていた。義父上は‥‥眉原殿が討たれたと‥‥怒り心頭に発しておられた」 「眉原どのは、おなくなりになっていたのですか」 儀光は、曖昧に首を振った。それが、否という意味だったのか、不明という意味だったのか、待は量りかねた。 だが待が更に聞くよりも早く、儀光はぽつりと呟いた。 「でも、私達を連れて逃げて下さった開拓者の皆さまなら、何とかして下さるかも知れない」 「開拓者の‥‥玲璃さまや神咲さまのことですね?」 「待は、開拓者の皆さまが好きかい」 「はい。儀光さまの次に好きです」 儀光は、仄かな笑みを口の端に浮かべた。 文机に手を伸ばし、自らの書いていた紙を小さく折り畳んだ。 「ここに、風信術の使い方が書いてある。この通りに風信器を使って、神楽の都に連絡を取っておくれ。開拓者の皆さまに父の本意を質して頂き、もし‥‥」 再び、儀光の目が潤む。 「‥‥もし私をまだ我が子と思って下さっているのなら‥‥生きていて頂きたいと。故郷の勒戒村なら‥‥父を、受け入れてくれるかも知れないと。そして」 儀光の手が、肩にしがみつく待の手に触れた。 「そして‥‥」 待の手が引き寄せられ、儀光の両手に握りしめられた。その甲に、涙がこぼれ落ちる。 「私を‥‥見捨てていないのだと‥‥忘れていないのだと‥‥まだ、愛しているのだと‥‥示してほしい‥‥」 待は、きつく儀光の背にしがみついた。その目からは、再びとめどない涙が溢れ出していた。 「大丈夫です。儀光さまは、何も悪いことは、なさっていないです。大丈夫。大丈夫」 待は泣きじゃくりながら、いつまでも大丈夫と繰り返していた。 |
| ■参加者一覧 17歳・男・吟 20歳・男・シ 21歳・女・シ 30歳・男・泰 20歳・女・サ 20歳・男・サ |
| ■リプレイ本文 ● 丸太を担いだ兵達が、掛け声と共に城門へ突撃を掛ける。重い音、怒鳴り声、そして城内から射られた矢を受けた者の悲鳴が、城の前には充ち満ちていた。 面頬から覗く紅潮した顔が、ふと冷静さを取り戻し、意外そうな表情を浮かべる。 「お主が、何故ここに?」 「待姫様のお父上がお立ちになると聞き、駆け付けました」 典膳の視線の先には、身の丈五尺ほど、真鍮製の純白の杖を手にしたローブの人物が立っていた。 「よろしければ、お手伝いさせて頂きたく存じます」 一見女性にも見えるその人物、玲璃(ia1114)は、丁寧に頭を下げる。 「義理堅い者達だ。元の素っ首叩き落とした暁には、何か礼をせねばな」 不敵に笑い、典膳は城門を攻める兵達を眺めた。 「抜け道は仲間達が抑えています。私は典膳様達の支援に回りたく存じます」 「気が利くな。では、抜け道の入り口に配置している兵どもに知らせておこう。蔵の制圧まで、抜け道の監視は任せて良いか」 「元よりそのつもりでおります。それから早速ですが、負傷兵達の治療に回りたく思います。傷ついた者達をこちらへ」 「助かる。‥‥負傷兵をこちらへ! 特に重傷の者だ!」 典膳の指示で、包帯や止血剤などで応急的に手当をしていた兵士達、それも自力では歩けない者や意識を失った者達が、一斉に運ばれてくる。 「負傷者を八名ずつ、私の傍へ。戸板を使って、回転効率をあげましょう」 玲璃の指示を受け、兵士達は慌ただしく動き始める。 表門が丸太で打ち破られる、雷鳴の如き音が城の前に響いた。 扉が破られることを察知していた城兵達は既に後退を始めている。決戦までは兵力の消耗を最低限にする腹だろう。嘉木兵達が、鬨の声を上げて城内へとなだれ込んでいった。 残るは、一の門、二の丸、二の門、そして蔵だ。 ● 剣戟の音が反響する蔵。 薄闇に浮かび上がるかの如く、白い光が踊っていた。 長大な斬竜刀を担ぎ、筒袖の上に外套を羽織っただけという軽装の美女、雪刃(ib5814)だ。白髪から覗く銀色の獣耳、尻から伸びる柔らかく太い銀の尾が、光の正体だった。 刀槍の存在を意に介さず、如何に効率良く敵を薙ぎ倒すかの一点に特化した雪刃の戦い方は、兵達を明らかに浮き足立たせていた。 雪刃の薄紅梅の唇が、一文字に引き結ばれる。窓から射し込む朝の光に、斬竜刀の刃がぎらついた。 「儀光がいるのに、儀忠は攻め込んできた。その事は、許せない」 紺碧の大きな目が細められ、細い肢体に秘められた筋肉が張り詰めた。 斬竜刀の間合いを計りきれず踏み込めない男達目掛けて、唸りをあげて閃光が走る。数打ちの刀が二口、甲高い音を立てて折れ飛んだ。 「や、やっぱ駄目だ、志体持ちじゃねえと!」 背を向けて逃げようとする兵の足を峰で払い、雪刃の身体が蔵の入り口へとにじり寄っていく。 「でも、その儀光が儀忠を救う事を望んでる‥‥」 「謎だらけで困ってしまうね」 大鎧に陣羽織、鉢金を巻き面頬を付けた青年、九法慧介(ia2194)が長く呼気を吐いた。 「八寒地獄の第七、鉢特摩の蓮華よ」 その手指から吸い取られた練力が鬼神丸の霊気と混ざり、真紅の光となる。 見る者の目に鬼神丸の軌道を刻み込むかの如く、刀身が残光を曳いて薄闇の蔵に舞った。 横薙ぎに払われる刀を潜って右腕一本で切り上げ、敵の顎を割る。 「お、女だ! まず女をやれ、長物なら隙ができるだろ!」 「言うだけなら、ただだけど」 雪刃は口許だけで薄く笑い、天墜を横薙ぎに振るった。兵の一人が刀と篭手に体重を掛け、骨の中程までを断たれながらもその軌跡を食い止める。 「い、今だ‥‥!」 雪刃の横手から斬りかかろうとした男が、突如その場に出現した紅い円弧に腹から突っ込んだ。薄闇の中に血飛沫が上がり、刀を振り上げた姿勢のままで男が崩れ落ちる。 円弧は、慧介の円月だった。 振り抜いた刀に紅い残像が追いついた瞬間、慧介は身体ごと回転し袈裟懸けに刀を振るう。同じ軌道で斬り上げながら振り向き、袈裟懸けに斬る。左を斬り上げ、正面を斬り下ろす。 横手から振り下ろされる刀を打ち落としながら、敵の肩口を斬る。身体を開いて袈裟懸けの一刀を避け、振り下ろされた手首を斬り飛ばす。 時と共に慧介の目は深く暗く沈んでいき、振るう剣はますます冴え渡っていく。 「応援は来ないのか!」 「無理だ、表と裏に殆どが回ってる! 死ぬ気で止めろ!」 怒鳴り合う男達だったが、既に蔵の四隅に固まりつつあった。 その時だった。 「今だよ!」 叫び声と共に、笠を被った人物が抜け穴から飛び出した。更に頭巾を被った細身の人物、そして神威人だろうか、群青色の髪から狐色の耳を覗かせた青年が。 「まずい、外に出すな!」 蔵の入り口を塞ごうとする男達の叫びを掻き消すかのように、高く澄んだ咆哮が蔵に反響した。 声は、雪刃の細い喉から発せられていた。その身体が大きくうねり、長い銀髪が弧を描く。 大きく開いた足を踏ん張り重心を下げ、天墜の長大な刀身で、慧介の円月が描いたそれを上回る巨大な殺意の弧を描く。 狼の遠吠えを思わせる雪刃の声に射竦められた男達が、回転切りの衝撃波をまともに浴びて薙ぎ倒され、吹き飛ばされた。 雪刃の他に誰も立っていない空間を、三つの人影が駆け抜けていく。 「無理しないで下さいね、お二人とも!」 「三人も」 慧介の目の光が一瞬緩み、三人を見送る。 その身体が、男達が塞ごうとしていた入り口を逆に塞いだ。 「追いたいかい」 慧介の鬼神丸が、再び紅い輝きを帯びる。 「追わせないけど、ね」 自らの血と返り血に染まった袖で、雪刃が顔を拭う。銀髪に囲まれた白い肌が、途端に真紅に染まる。 蔵の外では一の門が破られたか、一所に留まっていた兵達の声が、動き出した。 残るは二の丸、二の門、蔵。 ● 厚司織に外套を羽織った身の丈八尺ほどの青年、後家鞘彦六(ib5979)が、二の丸の裏手、本丸と白壁の合間に垂らされた麻縄を蜘蛛のように上っていく。 蔵では、まだ慧介と雪刃が戦っているようだ。 「まさか、自分が城に忍び込むとは思ってなかったよ」 彦六は耳まで口の裂けた鬼面頬の奥で呟いた。 太くはないが無駄もないしなやかな筋肉を張り詰めさせ、出窓式の石落としの上に膝をついた蓮蒼馬(ib5707)が、彦六ごと縄を回収していく。その脇には、何が入っているのか、大きな麻袋が転がっていた。 「僕はどうも眉原殿が臭くてしょうがないんだよね」 「啓治が?」 「そう。アヤカシが引き起こす事件にしては謀事が巧みな気がしてねえ‥‥」 荒縄を登り切った彦六が石落としに手を掛け、何とか上半身を通り抜けさせる。大鎧でも着ていたら、脱がざるをえない所だったろう。 「暗殺の噂から叛乱、そして今回の件。全て仕組まれてるとしか‥‥」 二人が囁き合う傍らで、忍び帷子に薄く透ける外套を着た細身の女性、神咲輪(ia8063)は、石落としの前で一人目を閉じている。 「輪?」 耳に練力を集中し、聴力を強化した輪がちらりと二人を見る。 「私が石落としに取り付いたとき、伝令が天守に向かっていました。多分、そこに儀忠様が」 「なるほど‥‥!?」 彦六の下半身を石落としから引き抜こうとした蒼馬が突如手を離した。輪は既に腰の菊一文字を抜き、床を蹴っている。 見回りなのか、伝令なのか、足音が近付いてきたのだ。 場所は廊下だ。襖は遠い。身を隠す時間はない。 彦六も石落としを抜けようとしたが、床に手をついた所で動きを止めた。床が、軋みを立ててしまう。下半身を石落としからぶら下げたまま、彦六は息を殺して事の次第を見守ることにした。 近付いてくる足音は三つ。角に背を貼り付かせた二人は顔を顰めたが、共に獲物を軽く握り、攻撃の姿勢を取る。 足音が、角に差し掛かった。 輪の姿が城内に吹き込む風に溶け、三人の背後に出現する。振り向きざまに振るわれた菊一文字の峰が、寸分違わず見張りの頸椎を打って昏倒させた。 前方で響いた床の軋みに視線を動かした一人が、身体をくの字に曲げて二尺ほども宙に浮き上がった。神速の足運びで男とすれ違いざま、蒼馬の暗勁掌が鳩尾を撃ち抜いたのだ。崩れ落ちながらも味方を呼ぼうとする男の首筋に、容赦のない手刀の一撃が叩き込まれる。 残る一人が呼子笛を口に咥えようとした瞬間、笛が指を離れて胸の下に垂れ下がった。 「危ない危ない‥‥」 上半身だけを石落としから覗かせている彦六だった。懐に忍ばせていた扇子を投じたのだ。笛ではなく、必ず顔の前に来るであろう手を狙って。 声を上げようとする男の喉笛を、輪の貫手が突いた。前屈みになった男の首筋に、蒼馬の手刀が決まる。 「彦六、助かった」 「あんなに上手く行くとは自分でも思ってなかったけどね」 彦六は照れ臭そうに笑うと、ようやく石落としから身体を引き抜いた。 ● 二の門に、丸太を抱えた兵達が突撃を掛けている。既に門扉は大きくへこみ、今にも扉の向こうが見えそうになっていた。 「蔵前、既に制圧済みです! 開拓者の方々が内部の敵を掃討して下さっておりました」 「うむ。これが終われば、いよいよ本丸か‥‥油断するな、玲璃殿のお陰でこちらの損耗も殆どないが、何せ敵はあの元の軍だ」 「はっ!」 伝令が立ち上がろうとした時、いつになく練力を消耗し疲労の色が伺える玲璃が、それを止めた。 「お待ち下さい」 「玲璃? どうした」 眉をひそめる典膳に、玲璃は純白の聖杖ウンシュルトを持ち直し城へと歩き始める。 「城に入りましたら、私達で先行します。城門突破後は、気絶し負傷した敵の捕縛収容を」 「馬鹿を申せ。儂等が戦わずしてどうする」 「危険です。嘉木様は城を落とした後も、民を守ってアヤカシと戦わねばならぬ筈」 言葉に詰まった典膳には構わず、蔵を離れて本丸前へと小走りに近寄ってくる慧介と雪刃に、玲璃は杖を振って合図をする。 「存分に、私達をお使い下さい。人を使うも、上に立つお方の度量」 全身に傷を負った慧介と雪刃が、玲璃に軽く手を上げて合流した。 「玲璃さん、大丈夫ですか」 「お二方こそ、相当なお怪我をなさっているご様子」 「雪刃さん、攻撃あるのみなんて無茶な戦い方をするんでね。驚いてしまったよ」 比較的怪我の少ない慧介が笑う。雪刃はまだ戦えるようだが、軽口を叩く元気もないようだ。玲璃の手が複雑に動き、ウンシュルトにはめ込まれた白い宝珠から、朝の陽射しを掻き消す程の力強い光が放たれる。 「ひとまず、二度ほど閃癒で治療をしておきます。これからは、随時回復しますので、ご無理なさらずに」 「ありがとう」 雪刃は一息つき、重そうに天墜を抱え上げた。 篭手をはめた典膳の手が、その腕を掴んだ。 「待て、雪刃と言ったか。最早傷だらけではないか。十分だ、休め」 「ここまで関わったら、最後まで見届けたい」 雪刃はゆっくりとその手を払った。天墜が唸りを上げ、雪刃の肩に戻る。 「第一、儀光を見捨てた儀忠は許せない」 紺碧の瞳が、天守を睨んだ。先日城で見た時は大抵無表情だったその顔が、微かな怒気をはらんでいる。典膳は思わず気圧され、口を噤んだ。 天守に取り付けられた窓に、微かな輝きが見える。儀忠だろうか。 二の門の前で、歓声が上がった。 ● 既に蔵の前は嘉木勢が抑えており、剣戟の音すら聞こえてこない。 本丸前から聞こえてくる兵達の叫びに、大きな歓声が混じった。 「ここも、そろそろ危ういな」 「すんません。俺らがいてこの様だ」 「良い。もう無理をするな、命を落としては貰った金も使えぬぞ」 龍を模した兜の下で呟き、男は本丸の正面に取り付いた嘉木勢を見下ろす。 「そりゃあそうですがね、まあ今まで散々世話になったじゃあねえですか」 「そうですぜ。何があったか知らねえが、あんたは俺らの戦友だ。あんたが反乱起こすってんなら、それなりの理由があったんだろ」 居並ぶ男達に混じり、もみあげと髭に顔を一周させた男が、疲労の色濃く残る顔で笑う。 「殿。我ら、最後の時まで儀忠様と運命を共にする所存にございます」 儀忠は唇を真一文字に引き結んだ。 「梅野。‥‥私怨でお前達を巻き込んだこと、あの世で償うぞ」 「しかし、一つだけ聞いてもいいですかい。今回ずっと腰に下げてるその袋、そりゃ一体何なんで?」 男の一人に言われ、儀忠は腰に下げた麻袋をそっと撫でた。 「この反乱に、何か関係があるんでしょうが?」 「反乱の前、そこの梅野と二人で話してたのが関係あるんじゃねえですかい」 本丸の前で、一際大きな歓声が上がった。 儀忠は暫く窓から外を眺めていたが、やおらぽつりと呟いた。 「息子だ」 「息子? その袋がですかい」 男達が訝しげな目を袋に向ける。と、慌ただしい足音が階下から上がってきた。 「伝令! 一階が制圧されました! 一部、志体持ちと思われる敵兵を止められません!」 「話している暇はないか」 儀忠は壁に立てかけてあった槍を掴む。 「ちっ、まあ話の続きはあの世で聞かせて下さいよ」 「私も直ぐに行く」 男達が、それぞれの獲物を手に天守の間から階段に足を掛ける。 目の下に隈のできた顔で儀忠は長い溜息をつき、窓枠に手をついた。 「済まぬ‥‥儀光‥‥許してくれ」 腰の袋を幾度も撫で、儀忠は目を閉じる。 「許してくれないのではないですかな」 腰に走った灼熱感に目を剥いて振り向いた儀忠は、自分の腰から生えている忍刀を見た。 「この城に入って幾日目になるやら。ようやく隙を見せて下さった」 「梅野‥‥何を!」 顔を髭ともみあげが一周した男が、儀忠の腰に刺さった忍刀を抜く。 「お命を頂戴するのですよ。元よりそれが狙いだったのですから」 儀忠は咄嗟に槍を振り回し、梅野と呼ばれた男を追い払う。梅野は忍刀を槍の石突きに跳ね飛ばされ、舌打ちを漏らした。 「‥‥まだそれほどまでに動けようとは」 梅野は腰に手を伸ばした。咄嗟に身体を屈めた儀忠の頭があった空間を苦無が通過し、背後の窓に填められた格子を粉砕した。 更に放たれた苦無もまた格子を打ち砕く。 「梅野! どういうことだ!」 「まだおわかりになりませんか。この香山の地、いや嘉木家に、成り上がりは必要ないということです」 梅野は更に腰の苦無を抜き、苦痛に顔を歪めながら槍を構えた儀忠の間合いぎりぎりに立つ。 「城攻めの最中から隙を見せなかった事は褒めておきましょう」 その両手に気が凝集し、苦無を回転させ始める。迂闊に間を詰められない儀忠は、槍を立てて防御に専念する構えを取った。 「儀忠さん!?」 その時階段から現れたのは、笠に鬼面頬を被った青年、彦六だった。梅野の手が振り向きざま閃く。 回転する苦無が、寸分の狂いもなく彦六の喉笛目掛けて襲いかかる。咄嗟に身体を捻った彦六の上腕部と脇腹が深々と抉れ、血が噴き上がった。 放たれた苦無は一つではなかった。顔に近い急所目掛けて放たれた苦無で意識を引き、本命の苦無で腹を抉りにきたのだ。 「彦六さん!」 階段を転げ落ちかけた彦六の身体を、輪の手が咄嗟に支える。梅野の身体は瞬時に儀忠の前を駆け抜け、半ば以上壊れ掛けた格子窓を突き破って、外へと飛び出していった。 「ご無礼をお許し下さい、でも‥‥」 輪の言葉を遮り、天守の間に上がってきた蒼馬が麻袋を床に放り出すと、儀忠の前に立った。 その拳が、ゆっくりと目の高さに掲げられる。 「あんたが元儀忠‥‥儀光の父親か」 面頬の下で、蒼馬の双眸が火を噴いた。 「何故息子を裏切るような真似をした!?」 「どの口がほざく! 先に儀光を裏切ったのは、嘉木家ではないか」 腰から流れる血を抑えようともせず、苦痛に顔を歪めながらも儀忠は槍を構える。 「儀光は言っていた。まだ自分を我が子と思っているなら、生きてほしいと。勒戒村ならばあんたを受け入れてくれると」 「‥‥なにを言っている」 「まだ自分を見捨てていないのだと、愛しているのだと示してほしいと。その思いを踏みにじるか!」 「下らぬ虚言を。儀光の遺骨ならばここにある!」 儀忠がまさに蒼馬へ突きかかろうとした瞬間、服を裂いて傷口を縛っていた彦六が叫ぶ。 「遺骨!? 生きてるよ儀光クンは!」 「儀忠様、私達は儀光様の依頼により、貴方を救いに来たのです!」 叫び、輪は懐から出した書状を取り出した。 「これをご覧になって下さい! 儀光様からの書状です!」 ● 「確かに、儀光の字だ。‥‥生きているというのか、儀光が」 茫然自失の体で、儀忠は床に膝をつく。 「儀光‥‥」 「ここにいらっしゃいましたか」 ローブのあちこちを血に染めた玲璃が、荒い息をつきながら天守の間へと駆け上がってきた。 「玲璃さん!?」 「ご心配なく、私自身は無傷です。九法さまと雪刃さまが大分傷ついていらっしゃいますが‥‥それより、これ以上嘉木勢を留めておけません。お急ぎ下さい」 「お主は? この者達の仲間か」 「ご挨拶は後です。ここはお急ぎ下さい」 慌ただしく毛糸の帽子と袖無しのコートを取り出しながら、輪が尋ねた。 「玲璃さん。アヤカシの気配はありました?」 「いえ」 玲璃は、蒼馬が床に放り出していた麻袋の中身を取り出しながら首を振る。それは、豚肉の塊と骨だった。 「嘉木勢の中にも、城内にも」 輪が細い顎の先を摘み、眉をひそめた。 「アヤカシの事件にしては謀事が巧みすぎる、という後家鞘さんの言葉が証明されましたね」 「眉原が怪しい、というのが一番筋が通りそうだな」 蒼馬が豚肉と骨を儀忠の服の中に詰め込みながら呟いた。 「まだ断定するには早いですけれど、でもそう思って良さそうですわ」 灯明の油を辺りに撒き、輪が答える。 「お主達、何をする気だ? まさか‥‥」 「そのまさかですわ」 「止せ、この城は嘉木様の物ぞ!」 儀忠は血相を変えたが、輪は構わず焙烙玉を取り出す。 その手を止めようとする儀忠の肩を、玲璃の手が抑えた。 「では、どうなさるおつもりでしょう」 「嘉木様に下る。最早、これ以上戦う必要はない」 「戦いを止めるのには賛成ですが、嘉木様は今、頭に血が上っておられます。‥‥準備はよろしいですか、お三方」 蒼馬と輪は頷き、焙烙玉を手に窓へ近寄った。彦六は火の付いた灯明の芯を手に、階段の前へ立つ。 「裁きも受けられず首を刎ねられるのが落ちですよ」 「ならばこの首を差し出すまでだ。眉原の謀略に乗ったのは私の責任ではないか、無益な血も数多く流れた」 「あんたは確かに愚かだった、その責任は取れ。だがあんたが正しい裁きも受けず命を落としたら、儀光はどうなる」 蒼馬の言われ、儀忠は言葉に窮した。 「儀光様を見捨てず、まだ愛してるのだと、生きて、そうお示しいただけませんか?」 「‥‥わかった。だが御公儀の裁きは受ける。飽くまでそれまでの間だ」 「十分じゅうぶん。じゃ、行こうか」 彦六は面頬の奥で微笑み、灯明の芯を放った。火は瞬時に酒と油へ引火し、燃え広がり始める。玲璃がいち早く階段を駆け下り、ついで彦六と儀忠が続く。 輪と蒼馬が焙烙玉を放り投げ、破れた格子窓から外に飛び出した。 数秒の後、格子窓が完全に吹き飛び、火を噴いた。 ● 「退避して下さい。天守が燃えています」 玲璃が、わざわざ煤をつけたローブを見せるようにして、階段を駆け下りてくる。 先頭に立っていた嘉木軍の志体持ちが、目を剥いた。 「燃えているだと!?」 「天守はおろか、本丸が焼け落ちてしまうかも知れません。ひとまず蔵へ」 明くまでも冷静さを失わず、しかし珍しく早口で玲璃が言う。 「最低限、蔵と二の丸に延焼させぬようにお願いします。濠の水を汲んで下さい、本丸で火勢を止めます」 「おい! やっぱりさっきの、爆発だったらしいぞ!」 「火の手が上がったらしいぞ! 逃げろ!」 兵達が声を上げ、それが本丸中に伝播していく。 そうこうしている内に、玲璃達のいる階にも煙が充満し始める。 「ま、待て、玲璃殿。元儀忠はどうなった」 「爆死しました」 「覚悟の上だったんだと思う」 血を失いすぎたのか、青みさえ感じさせる白い肌になった雪刃が、慧介に支えられて煙の中から現れた。 「私達が天守の間に入った時には、酒と油を天守に撒いて、焙烙玉を二つ脇に抱えてた」 「爆死‥‥!?」 目を剥いた男を押し退けるようにして、慧介に支えられた雪刃が階下へと向かう。 火の勢いでも気になるのか、玲璃は階上を窺っていた。 「負傷者を蔵に集めて下さい。今は一人でも人手が欲しい時です、元衆は傭兵団、金を払えば働いてくれるでしょう。彼らもまとめて蔵へ。九法さまも、雪刃さまを連れてそちらへ」 煙に咳き込みながら、男が言う。 「元衆を? しかし、それでは殿のお命を‥‥」 「抜け道は、私が抑えておくから」 玲璃の閃癒に傷を癒され、幾らか血色の良くなった雪刃が言う。 「重傷者ならともかく、典膳を襲える様な元気があれば、城から出さない」 「確かに、それなら‥‥」 雪刃を支えた慧介が振り向き、男に声を掛けた。 「それと、手の空いている兵は三の丸に集めてくれませんか。残存兵が集まっているのが天守から見えました」 男は頷き、前を行く兵達に怒鳴った。 「負傷者を蔵に集めろ! 敵味方関わらずだ! 玲璃殿が治療をしてくれる! 手の空いている者は三の丸と濠へ向かえ、死ぬ気で火を止めに掛かるぞ! 殿にもそのようにお伝えせよ!」 本丸の中に残っていた兵達が一斉に声を上げ、整然と階下へ向かう。 慧介と玲璃、雪刃が、互いに目配せを交わし合った。 油断無く辺りの様子を窺いながら、慧介は小石を指で弾いた。途端、物陰から彦六と儀忠が走り出てくる。 「済まぬ」 「蔵の前までの道は、俺が人払いをします。早く」 儀忠は深々と頭を下げ、彦六と共に階下へと向かう。 煙が天井から漏れ始めた。服に火がついたのか、数人の男達が城の石落としから濠に飛び込む。 「おい、引っ張り上げろ、手が足りないんだ」 「渡り廊下と納屋に人をくれ、壊すぞ」 怒鳴り声が行き交う中、玲璃達もまた階下へと走り出した。 ● ようやく春めいてきた風が、屋敷の中に吹き込んでくる。 切り株型の小山の上に柵を巡らせた村、勒戒村。その中でも一際大きい、瓦葺きの屋根を持つ屋敷で、一行は村の長老を待っていた。 彦六が、ふと思い出したように切り出す。 「あのさ、儀忠さん。‥‥暗殺者なんて放っていないでしょ?」 「暗殺者? 嘉木様と待姫を狙わせたのは、私だが」 「じゃなくて、儀光クンをさ」 「馬鹿な」 借りた帽子とコートを返し、身軽な甚兵衛に着替えた儀忠は、言下に否定した。 「生きているなど思ってもいなかったというのに」 「だよね」 彦六は納得顔で頷く。 「ついでだ、一つ聞かせてもらいたい。何故反乱を?」 蒼馬に尋ねられ、儀忠は一呼吸置くと話し始めた。 「そもそもの発端は、眉原からの書状だった。殿が若年寄の息子に待姫を嫁入りさせたがっているという内容だった。そのために邪魔な儀光を消し、濡れ衣を着せて元家を取り潰したがっていると」 彦六は、笠をいじりながら口をへの字にして考え込む。 「まさかとは思ったが、念のため元衆の一部を香山に飛ばしてみると、なるほど儀光暗殺の噂が流れている。そうこうしているうちに、城で私を裏切ったあの梅野から報せが届いた。既に儀光は死んでいる、嘉木様は儀光の頭骨を杯に酒を飲み、それを濠にうち捨てたと」 「他の元衆は、その話を?」 「元衆の他の者は、城の警備が異様に厳重で、内部を調べる事はできなかった。だが城内の何かを隠そうとしているように見えると口を揃えた」 「警備を突破できたのは、その梅野って人だけ?」 儀忠は頷く。 「てことは。城で眉原衆が守ってたのは、儀光クンというよりは‥‥」 何かを察しているらしい彦六は、腕を組んで唸る。儀忠は腰に下げていた袋を開いた。 その中には、子供のものと思しき小振りな頭蓋骨が入っていた。 「儀光の頭骨だけでも拾い出したと言って、眉原からこれが届いた。更に嘉木様が私を攻め滅ぼす準備をしている、自分の言いだした事が今回の事態を招いた以上、せめてもの罪滅ぼしに、我が軍を城内へ導き入れると。軍を起こした私は儀光の仇と思い、嘉木様と待姫を狙わせたが‥‥後はお主等の知っている通りだろう」 「一つ、お聞きしてもいいでしょうか」 それまで黙って聞いていた玲璃が、魔法帽を被り直して呟いた。 「シノビ数名が確かに待姫さまを狙っていましたが‥‥女装していた儀光さまと、コートを羽織っていた待姫さまを取り違えていたとも受け取れます」 城を落ち延びる折、我が身を呈してシノビの投じた苦無から待を庇った玲璃の言葉に、一行ははたと考え込んだ。 「馬鹿な! 私が儀光を邪魔に思う理由がどこにある!」 「それはさ、玲璃さん。眉原の旦那が全部仕組んだ事なら‥‥」 彦六の言葉を遮るようにして、障子が開いた。一行が口を噤み、そちらを見る。 「儀忠」 禿頭の老人が、杖を両手で抱えるようにして立っていた。顔は皺だらけ、見事に禿げ上がった頭皮にも皺が寄り始めている。 儀忠は畳に手を付き、深々と頭を下げた。 「長」 「久しいな。話は聞いた」 老人はふらつく足で上座へ行き、緩慢な動作で座布団に胡座をかく。一同が、居住まいを改めた。 「‥‥お主が村を出る時、儂は言ったな? 勒戒村とは、勒、くつわを戒める村。大きな争い事に加わることは村に大きな禍をもたらすと」 「‥‥覚えています」 儀忠は額を畳に擦りつける。 不思議な老人だった。今この瞬間倒れてしまってもおかしくなさそうな体つきだが、目の光は確かで、呂律にも危なげなところが全くない。 「村の先人は、幾度もその過ちを繰り返した。結果、人の寄り付かぬこの地に村を移し、自給自足の生活を始めたのだ。志体持ちの血が混じった村では、開拓者の力を借りることもなかった」 顔の皺に隠れるようにして光る瞳が、開拓者一同を見渡した。 「お主の働きは耳にしておる。アヤカシと大いに戦い、香山の嘉木典膳殿に見出されたと‥‥」 「勿体のうございます」 「だがその結果はどうだ。同胞に裏切られ、無益な血を流し、逃げ帰ってきた」 「‥‥返すお言葉も‥‥」 老人の目が細められる。 「遠からぬ内に、追っ手もこの村へ来るのではないのか」 儀忠は答えない。ただ黙って頭を下げるばかりだ。 「来るのだな」 「はい。‥‥長居をするつもりはありませんが、私を追っているであろう男にだけは討たれるわけに行かぬのです。その男でなく御公儀が来れば、大人しく村を去りましょう。それまでは‥‥」 儀忠は絞り出すようにして言った。 老人は傍らに置いた杖を手に取り、儀忠の頭を小突く。 「人は過ちを犯すものだ」 「は?」 儀忠は顔を上げた。 「そして、過ちは償う事ができる筈だ。お主ならば、里に来るケモノやアヤカシを斬ることもできよう。好きなだけ里におれ」 「なれど、追っ手が‥‥」 軽い音が、部屋に響いた。 顔の皺を深めた老人が、今度は儀忠の頭を殴ったのだ。 「村人を守るが、村の役目。脅されて村人を放り捨てるなら、何の為の村か」 老人は言い、開拓者達を見渡した。 「この猪武者が、とんだご迷惑をお掛けした。どうかお許し下され。この通り」 老人は座布団を降り、畳に頭を擦りつけた。一同は顔を見合わせ、慌てて首を振る。 「この男が村を出る時、村の者は、故郷に錦を飾ってくれるのではないか、村を豊かにしてくれるのではないか、そんな期待を心のどこかに抱いておりました。是が非でもこの男を止めなかった、儂をはじめとする村のもの全員に責任はございます」 「長」 儀忠は声を詰まらせ、再び額を畳に擦りつけた。 山を越えてきた風が、部屋に吹き込んでくる。 彦六は一つ大きな息をつき、ちらりと外を見やった。 「一件落着とは‥‥いかないよねえ‥‥?」 |


