【不条理な祈り】後編
マスター名:まれのぞみ
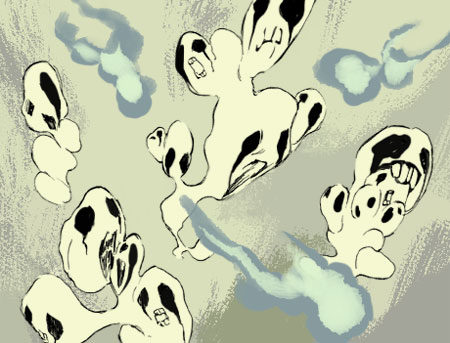
|
|
| ■オープニング本文 前回のリプレイを見る 村に流行した病は開拓者たちの尽力により、死者を出すことなく峠を越すことができた。それでも誰も治っていないという現実に代わりはなく、もし、それの意図するところは不気味な伝説の語るとおりであったのならば、状況はさらに悪化したのかもしれない。 しかし、それは救いであったのだろうか。 突然の死よりも、緩慢に迎える死の方が時に残酷である。 少なくとも、その少女は、そう信じていた。 それは、この屋敷は災いの中心にして根源。死神と病魔が抱き合って、呪いという舞踏会を開く、屋敷の中であった。 部屋の外からは、もはや声はひとつ聞こえることはなく、もはや、彼女のことを助けてくれる者などいなくなった。 皆、呪いという名前の病にかかり、動くこともできないのだ。 ただ廊下の向こう、屋敷のどこかの部屋で苦しみ、あるいは昏睡の中にいる。 (もう、私ひとりじゃないんだ) 苦しげに咳き込む少女は、だが不思議な喜びを感じていた。 もう長いこと感じた事のない安堵にも似た喜びである。 誰とも分かち合えぬと信じていた苦しみが、いまでは誰とでも分かち合えたのだという喜びに変わったのだと言っていい。 (ああ、これで――思い残すことはない……) 少女は顔を横に向けると、ベットの脇に咲いた赤い花を見た。 なんともいえぬ奇妙な花弁を持つ花であるが、それよるもまず異様を放っていたのは、その花弁の中央に開く目であったろう。まるでまどろむような眼差しは、見る者を、少女を夢へと手招く。 そう、夢――どれほどみずからが死んでいく姿を夢見、想像したのだろうか。それはもはや切望といっていいまでに育ち、糧となって花の花弁をほころばせた。 あとは花を咲かせるのみだ。 そう、それが、いま現実になろうとしている。 恐れがないといえばウソになる。 だが、恐怖の中にも安らぎがある。 いまでは終わりが確信できるのだ。 終わることのない永遠の苦痛という監獄から抜けることが出来るのならば、ひとは死神にすら救いを見いだす。終焉もまた、救いなのだ。 結局、どれほど宗教――このジルベリアでは滅びたはずのものである――哲学が、幾千、幾万もの言葉を費やし生という概念を称えようとも、いやだからこそ、それは死という概念への逃避でしかない。 (抵抗はムダだ。我々はおまえを同化する) あぁ、声がする。 無から生まれた自分が、無に帰るだけなのだ。 自然、震える手が天に伸び、まるでなにかをつかもうとする。 (私は、それでも……――) 少女のまぶたに涙が浮かぶ。 それでも――ワタシ――……心が解放され、ベットの脇にあった花がはじけて風になる。 風は屋敷を飛び出し、雪降る空へと舞い上がる。 風が吹き、雪が舞う。 いつしか町中に咲いていた赤い花が空へと舞い上がる。 散って、散って、積もって、積もって、花は花と寄り添って、雪と氷は手を繋ぎ、風はその見えぬ糸をからみとって、縫い上げる。 だが、それは夢は夢でも悪夢の類であったろう。 その異形はなにか。 氷のガラスで作られた湾曲した巨大な漏斗が上下に重なり、上から真紅の花が、まるで砂の滝となって落ちている。ああ、そうだ、これは砂の時計。 彼女のセカイは巨大な砂時計となって、この世に体現したのだ。 さっと雲間から、月光りが差し込んでくると、かつて屋敷のあった場所には巨大な砂時計……いや、砂花之時計が鎮座していた。 この赤い砂花が落ちきったとき、ここでアヤカシどもの虐殺の宴がはじまるのである。 |
| ■参加者一覧 18歳・女・巫 17歳・男・吟 13歳・女・陰 17歳・女・吟  神座亜紀(ib6736)
神座亜紀(ib6736)12歳・女・魔 25歳・女・砂 |
| ■リプレイ本文 「ただいま戻りました!」 村に近づくだけで、すでに何体ものアヤカシを仕留めてきただろうか。 だが、そのようなことはいまはいい。そんな態度でヘラルディア(ia0397)は、村に飛び込み、病院に駆け込むと看護士の格好に着替え、病人たちを見て回った。 すでに医師も動けない体になっている。 旅立つまでの短い間だが、やるだけのことはやるつもりだった。 その間、神座亜紀(ib6736)は鈴木 透子(ia5664)を手伝って書類の山にあたっていた。 暖炉の燃える炎と、はじける木の音。 もし、この世に終わりという日が来るとしたとしても、あるいは、こんな風に座り、開拓者とは可能性を信じ、そして求めて書を読み続けているのだろうか。 神座の心に、ふとそんな感傷が浮かんで、書類から目を離した。 巨大な時計が窓の外に垣間見える。 なんという、おとぎ話めいた景色なのだろうか。 あれは何のおはなしだったろうか。そして、それを語ってくれたのは母親であったのか、姉妹の誰かだったのか――遠き記憶もまた、すでに遠い昔のおはなしになっている。 (人の心をざわつかせる蠱惑的な光景ですね) ジェーン・ドゥ(ib7955)は、それを見つめながら片腕を無意識の内にさすっていた。 (この肌を刺すような悪意さえなければですが……) あまりにも芝居じみた雪景のそれは、だからこそこの奇異の根源であるという不思議な確信を見る者に与えていた。 あいかわらず部屋の中はただ静かで、暖炉の燃える音だけがしている。 鈴木があっと声をあげ、見つけたとつぶやいていた。 そして、書類をのぞきこみながら、黙り込んでしまった。 最後に入り口の鈴が鳴って来客を告げた。 雪の為、遅れていた仲間たちもやってきた。 「災厄の時を、止めましょう」 ● 玲璃(ia1114)は、暗い空を見上げた。 そして、手のひらを開くと、そこにはらはらと白い雪が降りてくる。 「覚悟、しなくてはいけませんね」 彼は、振り返って仲間に言った。 エラト(ib5623)が、そうねとつぶやく。 「呪いやらなにやらで呪術対策だけでも面倒ですのに、このようすですと天候もじきに悪化しそうですね」 「はい。天候が回復する時間があればいいのでしょうが残念ながら――」 玲璃は、流し目で村の中央に建つ時計台を見た。 まったくもって花之砂時計とはアヤカシもまた皮肉好きなものである。 あの天上に見える花がすべて落ちきったとき、この村は虐殺の場へと変わる。それを阻止するためには、砂に見立てられた花が落ちきるまでに、そこにたどりつかねばならないらしい。 すでに、この村にくる間にも、何匹ものアヤカシを倒してきた。 先に来ていた仲間たちも同様らしく、いい運動になったでしょと軽口を叩かれる程度に、彼女たちも苦労したのだろう。 なんにしろ村の外には、相当数のアヤカシがいると考えてまちがいないだろう。 ふりはじめた雪はやがて、あたりを白一色に染めた。 吹雪に隠れ、時計台もはや黒いぼんやりとした塔のようにしか見えない。 その時、異変が始まった。 「鐘の音?」 聞こえるはずもない音がする。 雪と氷の謡う、吹雪の合唱の歌声の中にではなく、確かに、その音は心の中に鳴り響くのだ。 開拓者たちは身構えた。 それが、それぞれの心をさすり、開拓者たちは抵抗した。 ――…… それは、なにかを語りたかったのかもしれない。 だが、その手が無理だと知ると、搦め手できた。 長い手は、やがて心をさすり、なにかを見つけた。 なれば、それを攻めるのが手。 小さな綻びは、やがて大きな傷となり、それを鷲づかみにした。 神座の眼差しが、いつしかぼんやりとしたものとなっていた。 ● 「あれ?」 自分はここで何をやっていたんだろうか。 神座は、ふと気がついた。 暖かな野原で、ひとり佇んでいると、声がした。 振り返って、声の主を見上げれば、陽光に影となった顔。 見知らぬはずなのに、なつかしい。 ああ、この雰囲気からば覚えている。 「お母さん!」 幼い頃になくなり記憶にはないはずなのに、なぜか神座には、それが母親だとわかった。 そして、その顔を思い出したと同時に、なにかを忘れた。 母は笑い、さあ帰りましょうと手をさしだした。 子は、喜んで手を取る。 そして、帰り道の間、じっと神座はしゃべりつづけた。 まるで何年もの間、しゃべることを貯めていたかのように、しゃべって、しゃべって、しゃべって、そして心の底から万感の思いがこぼれた。 「お母さん」 「なにかしら?」 「うんとね――」 それから、さらになにを語ったろうか。 姉妹のこと、好きな料理のこと、いつもの生活のもろもろ。そして、いままでしてきた旅―― (旅?) その時、それが神座の目に飛び込んできた。 「どうしたの?」 歩みを止めた娘に母が首をひねる。 しかし、少女は応えない。 足を止め、じっとそれを見つめていた。 なんだろう。 少女もまた首をひねった。 なにか大切な――そう、この母よりも大切ななにかを忘れている気がするのだ。 「赤い花がどうしたの?」 母が言う。 「赤い――花!?」 思い出した。 じぶんは開拓者として、アヤカシを倒しにきたのではなかったか。 そして、敵はその赤い花――。 神座はナイフに手をやった。 しかし、母の顔を見ると、決心がにぶる。 いや、だめだ。 (違う、これは呪いだ、母さんは死んだんだ!) 神座は母に向かって、最後のあいさつをした。 「じゃあ、さようなら――」 足に突きたてたナイフは肉をえぐり、その痛みは幻想を醒まさせるには十分であった。太ももから流れる鮮血は、いつしか雪の上にしたたり落ち、あたりには驚いたような顔をした仲間たちの顔が見えた。 「……戻ってきたんだ」 安堵と、そして、わずかばかりのさびしさが顔にある。 もし誰かが言っていた天国なるものがあるとしたのならば、母とは、またいつか会えるのかもしれない。だが、現在はその時ではない。 「母さん……」 つぶやきと供に流れた涙もまた雪の中へと消えていった。 ● 「まるで……廃墟ですね」 エラトが、半壊した村を見回した。 すでに時計は、目と鼻の先である。 「この前は、こうではなかっただけど……」 すでに、このあたりは、一度、この村に来ているヘラルディアたちの知る景色とも変わっていた。 「なんにしろこれからが本番なのでしょう」 と言って、エラトは、天鵞絨の逢引を奏でた。 玲璃も加護結界の具合を確認する。 準備は整った。 あとは覚悟を決めるだけだが、いまさら開拓者には不要なものであった。 そして、そこへと至る。 「瘴気の森……」 誰となくつぶやいた言葉は、見た目をあらわしてはいなくとも、本質をあらわしてはいたであろう。その時計台の下は、真っ赤な花が咲きみだれ、季節と場所との感覚を狂わせる。すくなくとも、その異様な景色は瘴気の森と呼ばれる、この世の穢土を思い出させるには十分であった。 ただですら、うちつづくアヤカシの攻撃にささくれだった心が一段と締め付けられたような気がした。 だが、結末は、意外ともろいものであった。 ジェーンが、それに手をつけたとたん、薄いガラスが割れたのだ。 「これで終わりなんて、ガラスハートなアヤカシさんですね」 そう、アヤカシ自体はそれで滅んだ。 だが、そのアヤカシは滅びようとも眷属は残っている。 「なんの音?」 遠くから響いてくるような音がした。 「雪崩の音?」 「こんなに近く?」 「水……じゃない!」 途端、開拓者たちの背後にあった時計が腹から割れ、まるで洪水のように赤い花びらがこぼれだしてきた。 あっというまに足まで埋まった花は、じきに膝、腰と潮位があがってくる。 「バラの洪水でおぼれ死ぬような趣味はないんですけどね」 「言っている場合じゃない!」 「見つけました! 神座さん!」 鈴木がなにごとが叫んだ。 流されながら、神座がストーンウォールを放った。 「邪魔はさせない!」 しかし、次の瞬間には彼女もまた赤い濁流に流され、それでもおぼれまいともがくしかなくなっていた。 残されたのは石の箱船となった魔法と、鈴木だけであった。 雪の中で花のせいで溺れそうになった――言葉にすればまったくもって意味は不明で説明を要する状況である。だが、その洪水の中に生き残った箱船が運ぶもの 鈴木の目の前――壊れた巨大なガラスの建物の中には、うずたかく残った花は、まるで砂丘の山のようになっていて、どのような案配か、その頂上にはベットがあった。 そこにはひとりの少女が取り残されている。 まるで、なにかの意思があるかのようである。 「だけど……」 石の船から降りて、鈴木は花の山に 砂のように崩れる花に足下をとられながら、鈴木は倒れ、転びながら、やがて四つん這いになって這い上がっていった。 やがて、頂上に立った時、彼女の姿は、まるで眠り姫のもとにたどりついた王子であった。眠れる姫君のの手をとって、鈴木は祈った。 (ごめんなさい――) ついてきてもらうはずであった病気の少女の両親は見つからなかった――いや、正しく言えば、このつぶれた時計の下のどこかに魂の抜け殻があるはずなのだ。 しかし、鈴木にはそれでも彼女の両親がそばにいるのだと思った。 (お嬢さんを取り返しに行きましょう) 鈴木は心の中で、その両親とともに祈った。 (親は子の為なら危険を顧ないと聞いています。だから――) ここにいない、彼女の両親をもしも連れ出すことができたとしても、それはやはり無謀であったろう。たぶん、その体は動かなかったであろうし、そもそもこのような場に連れてくることができたとしても、志体を持たざる体は持たなかったであろうし、それよりも前に、その心を壊すこととなったかもしれない。 失敗したからこそ救われたというものも時にはある。 下から仲間の声がした。 どうにか無事であったようだ。 ならば、最後のしあげだ。 少女が目覚める前に破壊するしかない時は 「しっかり手を握ってあげてて下さい。それから想って」 彼女の両親に言うつもりだった言葉を、自分が彼女につぶやいていた。 ● 「……饗宴の時は訪れません。これで終わりです」 ジェーンが高々とあげた剣を、そのまま振り落とし、時計台を土台から破壊した。 (……この想いを理解は出来ても許容できないのは、やはり実際的過ぎるからなのでしょう。然し、過去の事例と良い、作為の臭いがします負の想いを利用するモノ……厄介の極みですね) ジェーンの心に、そんな言葉がよぎった。 そして、山の上では鈴木が、家族の想いを吸うつもりで瘴気を集め、集めた瘴気を呪声にして、 「渡さないっ」 と叫んで、時計の欠片にぶつけていた。 むろん、そんな術はない。 ただ、彼女が思いが描いた技の連続である。 それが彼女ができるいまのすべてであった。 ● 「終わりましたね」 後方の確認から戻ってきたヘラルディアが告げた。 「はい」 遠くを確認する目をしながら玲璃が応じた。 エラトもうなずき、村の危機は回避された。 「さあて、後片付けが大変ね!」 口ではそう言いながら、ヘラルディアは本当にうれしそうな笑顔をするのであった。 |


