【浪志】死人憑き/霊験
マスター名:津田茜
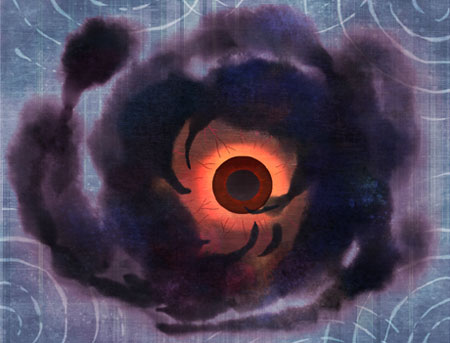
|
|
| ■オープニング本文 ●死人憑き 吐息をひとつ。 ゆっくりと張り巡らされた神経の束に意識を送り込む。 途端、流れ込む獲物の恐怖と絶望に――飢餓を潤すその甘美な味――狂喜にも似た愉悦が湧いた。ひと息に貪り喰らいたい衝動を堪え、それはさらに慎重に獲物を探る。 人間の身体は意外に繊細な構造をしていて、急いて無理に動かすと容易く壊れてしまうのだ。腕や首がいくらか捻じれていたところで器にさほどの支障はないのだけれど、周囲の人間たちにとっては酷く奇異なモノにうつるらしい。己の存在が彼らに知れれば、面倒なことになる。 幾度か失敗し――痛い思いもして――それは慎重になることを学んだのだった。 ゆっくりと。 時間を掛けて、神経を繋ぐ。少しずつ器の中へと外の気配が流れ込み、全てが仕上がる頃には僅かに残った器の意識は完全にそれのモノに喰い尽くされて死の境界すら覚らぬまま儚く最後の吐息をこぼした。ひっそりと途切れた拍動を最後の一拍まで味わい尽くすとそれはようやくゆるゆると瞼を開き、獲得したばかりの新たな感覚と共に世界を眺める。 驚愕と疑惑、恐怖、動揺‥‥そして、漠とした喜色‥‥ 様々な表情をその面に張り付けた家族と知人――次なる獲物たちが――黄泉路より息を吹き返した「彼」を取り巻き、見下ろしていた。 ●果報の噂 荒事好きの粗忽者ばかりが集まる小さな道場にも、噂話は舞い込んでくる。 頓着のない道場主が煩く言わぬせいもあるのだけれど、結局、人の口に戸は立てられないといったところか。眉を顰める者もいないではないが、市井に漂う眉唾ものの真贋をいちいち咎めて回るほど暇を持て余しているわけもなく‥‥大概は下火になるまで放っておかれるのが常だ。 「――そういや、件の拝み屋とやらの住まいはこの近くだな」 「やめてくれ。あんたまでくだらん噂話に踊らされる気か」 伸び放題の野草に占拠された疎水の堤でふと足を止めた真田の言葉に、連れの男は露骨に顔を顰める。 開発途上で放り出された開墾地に繁栄する街の喧騒から弾き出された人々が流れ着き身を寄せ合うように住み着いた少しくたびれた下町風情が色濃く漂う界隈は、素行のよろしくない胡乱な輩も多い。――もちろんまっとうに生きている者の方が多いのだけれども。 如何にも眉唾だと渋面を作る朋輩に、真田は少し不思議そうに首を傾げた。 「病を折伏してくれるというのは、ありがたい話だぞ?」 素直にありがたいと口にする真田に、男は眉間に刻んだ憂慮の証をいっそう険しいものにした。鷹揚で屈託がないと言えば聞こえも良いが、ともすれば、体よく騙されかねない危うさが付きまとう。少しは周囲の気苦労も考えろと、苦言のひとつも吐いてやりたいところだが。 「うわぁぁぁ――ッ!!!」 彼が口を開くその前に、野太い悲鳴が涼やかに水面を揺らす川風を裂いて響いた。 反射的に巡らせた視線の先で、歪な影が膨らむ。蠢きながら大きく広がった――地面より抜け出した影が、主人に造反を企てたかのような――漆黒の塊を見極める暇もなく、男たちは鞘を払った。 ●奇蹟の果て 持ち込まれた事件の顛末に《開拓者ギルド》の受付は、思案気に頬に手をあげる。 下町で奇妙なモノが流行の兆しを見せているという噂は聞いたような気もするけれど。――確か、死者さえ息を吹き返すという触れ込みの折伏師の呪符がどうとか。 「護符にアヤカシが封じられているとは聞いておりませんでしたが‥‥」 アヤカシだと知らされていれば誰も買わない。 そういえば、どこぞの長屋で死人憑きが出たとかなんとか。――筆の柄でほりほりと額を掻きつつ首を傾げる受付係に、真田はだんと天板に掌を叩きつける。 身を竦ませるような乾いた音が高い天井に大きく響いた。 「ともかく、急いで人を集めてくれ!」 ありがたい霊験だとばかり思っていたものが、禍の種だったとは。 舞い込んだ《死人憑き》の噂が本当ならば、既にアヤカシとなって街に浸潤しつつあるのかもしれない。――俄かに慌ただしさを増した空気の中で、彼は苦いものを噛みしめた。 |
| ■参加者一覧 17歳・女・巫 16歳・女・陰 25歳・女・泰 13歳・女・陰 12歳・女・弓 14歳・女・陰 17歳・男・陰 |
| ■リプレイ本文 一頃の茹だるような暑気が嘘のように、大気は穏やかに澄んでいた。 時折、冷気さえ感じる秋風に懐手して行き交う通行人を追い越し、柊沢 霞澄(ia0067)はいつもより早足で歩く。――霞澄の少し前を歩く巴 渓(ia1334)の気風の良い肩がやや前屈気味なのは寒いのではなく、怒っているからだ。 「死人も甦る御札って、怪しすぎるのですよ〜」 アイリス(ia9076)が零した嘆息は、皆の心の声を代弁していた。 天地の理を揺るがす奇蹟が二束三文で手に入る。幾度、反芻しても胡乱としか喩えようがない。訝しんで然るべき‥‥で、あるはずなのに。迂闊に手を出してしまうのは如何なる心象か。 「まぁ、当事者にとっては縋りたくもなるわよね」 漠然とではあるが、気持ちは理解る。 アヤカシやケモノだけでなく、時には利害が対立する人間を相手に命のやり取りをすることもある彼らだ。不帰路を覗く怖気を知らぬはずがない。同情を滲ませたリーゼロッテ・ヴェルト(ib5386)に、渓は自嘲を込めて辛辣に口許を歪ませた。 「ふん。人間も業が深い‥‥」 命への執着は、権力者でも下町の貧民でもさして変わらぬものであるらしい。 愚かである。暗愚ではあるが、なるほどたいした狭量だと一概に当事者を嗤うことはできなくて。いっそ悪意に等しいアヤカシの所業に怒りが募った。――己は絶対に大丈夫だ、と。そう断言出来る者の方が、きっと少ない。 「神楽の都も最近物騒なのですよ」 ふうわりと青い髪を撫でて過ぎる涼風に唇を尖らせたアイリスの言葉のとおり、平穏というには程遠い世情の気色に緋那岐(ib5664)は少し引き篭もりが過ぎたかと冷や汗をかく。――否、決して遊んでいたワケではないのだけれど。――しかも、やたらと上背のある同行者に遥か高みより見下され、余計な不安まで脳裏を翳めた。 「‥‥俺の身長、ちゃんと伸びるのか心配になってきたっ」 実は悩んでいたらしい。 思わずといった風情でポツリと洩らした緋那岐の深層に、アイリスと鈴木 透子(ia5664)は顔を見合わせる。幸いと言っては語弊もあるが、カンタータ(ia0489)とリーゼロッテも今のところそこまでの不安は感じずに済んでいた。そして、緋那岐の将来(?)に一抹の不安を投じた男はというと‥‥少し困惑した風にぽりぽりと指の先で頬を掻く。 「あ、いや。オレだって生まれたときから筋骨逞しかったワケではないぞ。‥‥ま‥ぁ‥チビだって理由で苛められた記憶もないんだが‥‥」 ちっとも慰めになっていない。 だが、どこか彼の人柄が覗えるように思えて、霞澄は淡い唇の端にほんの小さな笑みを浮かべた。きっと泣き虫な仲間を苛めっ子から庇ってやっていたのだろう。――着物の上からでも良く鍛えられていると判る真田の広い背中を見上げ、透子はそんなことをちらりと思った。 ● 影に潜んだアヤカシは凶風となって、神楽中を吹き抜ける。 死への恐怖か、あるいは、生への執着か。――《黄泉返り》の奇蹟は、思った以上に多くの人々の心を揺らしたらしい。独り歩きする噂に肩を落とした緋那岐の吐息に、アイリスも頭を抱えた。 「‥‥やっぱり元を断つのが一番だろうけど、う〜ん‥‥」 「神楽の都は結構広いですから、お札を探すのも大変なのですよ〜」 奇蹟の起こった裏長屋に、既に噂の痕跡はなく。 遠巻きに覗き込む野次馬の垣根の向こうで事件を検分していた開拓者は、既に朽ち果てた死体に憑いていたアヤカシを探しているのだと訪れた霞澄に告げた。 最下層の裏長屋にて奇蹟の呪符を配りはじめた祈伏師自身がアヤカシに取り憑かれていたらしい、と。‥‥神楽に持ち込まれたのが偶然か、アヤカシの意図であるのかまでは、まだ判らなかったが。 生きて活動しているように見えても、その身体が腐りはじめれば、僥倖に舞い上がった周囲も流石に異変に気づく。騒ぎになる前に狩りを始められなかったことが――アヤカシにとっては不運なことに――ひとつの事件の始まりだった。 「つまり、アヤカシに憑かれても肉体の腐食は止まらないってことね」 解けた疑問のひとつに、リーゼロッテは思案気に顎を引く。 死者と生者の区別さえつかない下級のアヤカシなら、手掛かりを残さずに行動するなど無理な話だ。きっと方々に手掛かりを散りばめているだろう。拾い集めるのは、難しくはない。 そう、例えば―― 「‥‥あの‥こちらに伺えば‥‥奇蹟を得て命を長らえた方にお会いできると‥‥ええ、実は父様が病気で‥‥」 誰もが避けて通れない別離への不安。 それを口にするのが若く美しい娘なら、誰もが何とかしてやりたいと思うもの。――悩む緋那岐とは対照的に、年齢より幼く見える外見を最大限有効利用するリーゼロッテだった。 ● 呪符の奇蹟で死者が蘇ったという噂は多くの者が知っている。 だが、実際に蘇った者を知っているかと問われれば、是と応える者はやはり少ない。 人から人へ―― 伝えられる噂話はいくつにも分岐して。散りばめられた断片より真に実のある話を見つけ出すのは、思いがけず手のかかる作業だった。あるいは、運といっても良いくらいに。 病人に貼り付ける前に実体化して人を襲った例を思えば、さほど上等な呪符でもないのだろう。――人を喰らわなければ生きられないのだとすれば、いつまでも呪符に潜んでいるわけにもいかない。 「‥‥実際に呪符を受け取った人は、多くないのかもしれません‥‥ね‥‥」 より強く、凝った瘴気の澱みに発生するアヤカシは――ごく少数の例外を除いて――自らの手で仲間を増やす能力を持たないとされていた。 おっとりと小首をかしげた霞澄の言葉に、カンタータはちらりと足元で主人の言葉を待つ忍犬に視線を落とす。追いかける対象を具体的に設定しないことには、せっかくの《絶対嗅覚》にも出番がない。 「ばら撒かれたアヤカシの数が少ないのは朗報ですー、けど‥‥」 僅かに語尾を濁して言葉を区切り、カンタータはつと厚司織の袖で口許を隠して小さく呟く。特に聞かれて困る内容でもないが、カンタータにも開拓者の矜持というものがあり‥‥惰性に受け取られては、面白くない。 「追いかけるボクたちにはちょっと面倒な話ですねー」 過ぎたる力を手に入れたところで、立ち竦む者もいるだろう。幾重にも人の業を逆手に取ったアヤカシだと、渓は不快気に表情を歪ませた。 「地域のお医者さんに尋ねてみませんか?」 人通りの多い繁華な街の賑わいに視線を配りながら、透子は思案しつつ言葉を選ぶ。 怪しげな呪符に手を出そうというのだ。大人しく寝ていれば治るといった単純な病気だとは考えにくい。むしろ、医者にも匙を投げられるような、大病や怪我に長らく患わされているはずだ。 「なので突然、体が良くなり、なのに様子が変とか。逆に、姿を見せないとか。そういう人を探してみるのが良いと思います」 胡乱な商売仇に良い心象は抱かぬだろうが、だからこそ記憶には残りやすいもの。――施療者だけでなく、集まる患者たちも、その手の噂には敏感だろう。 なるほど、一理あると頷いて。開拓者たちは辛抱強く、聞き込みの手を広げたのだった。 ● 高い塀の向こうは、ひっそりと静寂に包まれていた。 近くに住む者の話では、家督を譲ったご隠居が身の回りの世話をする下働きの中間夫婦と一緒に住んでいるのだとか。 「本家の方から、こちらのご隠居さまはこの春先に卒中で倒れたと聞いたですよ」 それ以来、半身が不自由なのだとか。――夜半のことで手当てが遅れたせいだと家人たちが酷く気に病み、湯治や鍼など効能があると聞けば、多少、遠方であったり、値が張ってもすぐに飛び付いていたらしい。 アイリスの報告を引き継いで、カンタータも近くの生薬屋で仕入れてきた話を披露した。 「――で、医者に処方してもらった膏薬を10日毎に中間さんが取りに行くことになっていたらしいのですけど〜 半月ばかりお店に来ていないそうです〜」 生薬屋としては気にならないワケではなかったが、いつも少し多めに処方するので、飲み残しが溜まっているのだろうと考えていたという。 顕著な異変を見つけたのは、いつも野菜を納めに来る振り売りの天秤担ぎで――こちらは、緋那岐が話を聞いた――日頃は愛想の良い下女が、ここ数日、能面でも被ったかのように無表情になったばかりか、買った野菜が手付かずで庭先に放置されているのを見つけた。 高い板塀で囲まれて家の中が簡単には覗えないのも、潜伏するには好都合である。 踏み込む前の確認に、塀の向こうを《瘴索結界》で探っていた霞澄は、ゆるゆると拡げた意識の網に微かに触れた瘴気の気配を感じて表情を曇らせた。 ゆらり、ゆらりと当てもなく家の中を徘徊する瘴気の塊がひとつ。――《鏡弦》の共鳴が拾い上げた波形と違わぬ結果に、アイリスも小さな肩を落とす。 「‥‥アヤカシの‥気配がします‥‥」 見つけた、と。 素直に喜べないのは、結末を知っているから。善意によって持ち込まれた悪意の息吹に、透子も小さく吐息した。 「――踏み込むぞ」 「判った」 勝手口の引き戸に手を掛けた渓の声にも、静かな怒りに満ちていた。 真田も無言で、佩いた刀剣の鯉口を切る。カンタータと緋那岐はそれぞれ効き手に符を構え、リーゼロッテも「アゾット」を握る手に力を込めた。 「おそらく、座敷だ」 《心眼》が捕えた反応は、家の最奥。 無言の裡に今一度、お互いに視線を合わせ、そして―― 雷の力を宿した式が白く輝く閃光となって、襖を弾き飛ばした。 間髪入れず放たれた《ホーリーアロー》は、天井を揺るがさんばかりの轟音に振り返った女の胸に的を違うことなく吸い込まれ‥‥そして、散華した。 期待した効果は得られなかったが、目眩しとしては十分で。 《瞬脚》を用いて畳みを蹴った渓は、一呼吸で下女‥‥否、下女の姿を喰らったアヤカシに肉薄する。――躊躇ないこと――それだけを念じて、丹田に溜めた練力を解き放つ。 《破軍》、そして、《絶破昇竜脚》の青い閃光がのたうつ龍となって、座敷を奔った。 「喰らえッ!!」 救命が叶わぬのなら、せめて、人の姿である内に―― それが、渓なりの思いやりであることは理解っている。それでも、哀れであることに変わりはない。居た堪れずに、透子はかつて人であったものより眼を背けた。 雷鳴にも似た轟音に、 人為らざるモノの断末魔が重なった―― ● 秋の色を色濃く宿した蒼穹は、どこまでも高く透明で。 吹き飛ばされた障子の向こうに四角く切り取られた一巾の絵を思わせる光景の、地上の不安など微塵も感じさせぬ平和そのものの色相がいっそ小憎らしい。 刀を納める拍子につと空を仰いだ真田は暫し眼を細めて白く吹き流される筋雲を眺め、困った風にその精悍な表情に薄い笑みを浮かべる。――振り返った男の顔は笑っているのに、何故だか泣いているように見えた。 「‥‥流れ着いた先が神楽でなければ、こいつもこんなに早く正体を暴かれることもなかったのだろうか?」 「いやいやいや」 どこか感慨を宿した真田の言葉に、緋那岐は慌ててぶんぶんと首を横に振る。 密やかに集落ひとつ、気がつけば丸ごとアヤカシに取り込まれていたなんて図式もあり得るだけに、洒落にならない。 人の多い神楽であったからこそ噂になり、また、アヤカシも領域内の獲物を喰らい切れなかったのだ。――結果として存在を暴かれ、退治されることになったのだから。 「‥‥神楽で良かったとも言えないけど、な‥‥」 欲を言えば、誰かが犠牲になる前に――事件として《開拓者ギルド》に持ち込まれてからでは遅いのだ――予兆である内に気づくことができれば良いのに。 神楽にいてさえ確実に濃くなりつつあると感じるアヤカシの影。 今のままでは、いずれ《ギルド》の手に余る日が来るかもしれない。――漠然とではあるが。容易く消しさることのできぬ重い不安と焦燥は、心の底でいつまでも燻ぶり続けた。 |


