未来への一枝
マスター名:龍河流
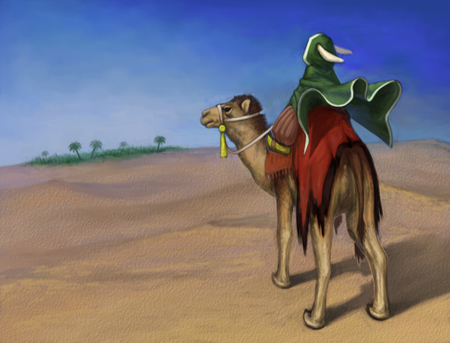
|
|
| ■オープニング本文 アル=カマルの魔の森は、大アヤカシ退治の後、順調にその版図を削られていた。 元が広大な土地の事とて、完璧に姿を消すにはまだ時間が掛かりそうだ。それでもアヤカシの姿を見るのは稀となり、そのアヤカシも植物型か蟲型と大抵が弱いものばかりになった。 瘴気は未だ濃いものの、ジンならば瘴気感染の心配をする必要もない。 現在はほとんどが只の焼野原だが、所々では緑が芽吹いて来ている。 魔の森の跡地に芽吹いた草木が、瘴気による多少の変異は見られても、人に害為す存在ではないとの調査が公表されてすぐ、魔の森近くのオアシスでは重要な実験が行われようとしていた。 「これから、試験植樹を行う。神の巫女からの賜りものを、喧嘩で損なったりしないように、落ち着いてやってくれ」 「こいつらに、まともな植樹が出来るのか?」 「なんだとぉっ」 「喧嘩するなっつってんのが、聞こえなかったのか、この阿呆共!!」 魔の森の跡地に、アル=カマルと他の儀からも集めた植物を植えて、その生育を観察する。瘴気に汚染されることなく育つ植物があれば、土地を肥やすための最初の段階として、その植生を広げていく計画だ。 そこから、この先何年かかるか分からないが、魔の森を人が住む土地に変えていこうというのに、定住民中心の王宮軍と遊牧民の独立派とは角突き合わせることを飽きず繰り返している。 それでも言葉の応酬だけで終わるので、最初の頃よりはよほど穏便になって来ているとは、オアシス住民と両派の穏健派の言葉である。 協力しないと、事が成らないのはどちらも承知しているので、本格的な衝突には至らない。個々人でなら、割と親しく付き合えるようにもなっていた。たまに、オアシスの女性を巡って盛大な争いを繰り広げている奴らもいるにはいるが。 なにはともあれ、これから行うのは未来に向けた大切な事業である。 そして。 「で、この広さに俺達だけで頑張れと?」 「そりゃ無理だ。応援はいつ来るんだよ」 「文句言う時だけ仲がいいのか、お前らは‥‥とりあえず開拓者に来てもらっただろ。後は、十日後に応援が来る予定だから、それまで休みなしな」 人手は、慢性的に足りていない。 |
| ■参加者一覧 22歳・男・泰 18歳・女・吟  リィムナ・ピサレット(ib5201)
リィムナ・ピサレット(ib5201)10歳・女・魔 19歳・男・砂  レムリア・ミリア(ib6884)
レムリア・ミリア(ib6884)24歳・女・巫 25歳・男・砂 |
| ■リプレイ本文 今日も、アル=カマルの魔の森の跡地に、元気な掛け声が響いた。 「さあっ、いっちゃうよ〜♪」 声の主はリィムナ・ピサレット(ib5201)。どこからどう見ても無邪気な女の子。開拓者で、相棒は上級からくりのヴェローチェだ。一人と一体で、にこにこと愛らしく笑っている。 彼女の前には、本日は王宮軍と独立派遊牧民双方の男性ばかりが二十人ほど。作業の植樹そっちのけで殴り合いをやらかし、進行予定をしっちゃかめっちゃかにした連中である。 『生きた心地がしないって顔付き‥‥かな?』 「それは穏やかではないね。後悔は先に立たずとは言うが、反省はしている様子かな?」 『してなかったら、殴って教える』 人妖のテラキルを目の代わりに、離れた場所から様子を窺っているのはジョハル(ib9784)だった。目が不自由ながらも助力に駆けつけ、豊富な植物、薬草の知識を教授してくれる彼は、すでに皆から一目置かれる存在だ。 相棒のテラキルは元気が過ぎて、たまに一緒に作業している人達にぶつかったりしているが、こちらも可愛がられていた。ただし、今の時間だけは事情が違う。 ジョハルに行ってもいいよと言われたテラキルが、リィムナの方に飛び出したのを見て、苦笑したのはクロウ・カルガギラ(ib6817)と羅喉丸(ia0347)の二人だ。 「今日は怪我人が出ないといいけどな」 「明日の作業に差し障るから、程々にとは頼んでおいた」 彼らの視線の先には、『逃げようとしたら踏む』と言いそうな位置で、ティア・ユスティース(ib0353)の相棒フォルトと、レムリア・ミリア(ib6884)の相棒ブラック・ベルベットの甲龍二頭がどっしりと腰を据えていた。時に何もしてはいないが、威圧感はある。 主人たるレムリアとティアはと言えば。 「怪我人なんて、とんでもありません。もう、どうして殿方は喧嘩が止められないんでしょう」 「こうなるって言ったのに、殴り合ったんだから自業自得。ほんと、どうしても順位を決めるのが好きな生き物で困るわ」 リィムナの前に引き出された連中の怪我は心配しているが、助けようとは考えていない。この調子だと、ブラック・ベルベットやフォルトが彼らを突き転がしても怒らないだろう。もちろん、相棒が無闇と人を傷付けたりしないという強固な信頼があるからでもある。 後は、これがわずか数日で恒例化した『その日仕事をさぼるか、邪魔した奴へのお仕置き』だからだった。名目は特別訓練なんてなっているが、実際はどう取り繕ってもお仕置き。 初日は、開拓者や別勢力への意地を無闇に振り回して、止めに入ったリィムナに喧嘩を売る暴挙に出た輩がひどい目に遭わされた。そこから、どういう訳だか、毎日何かしらあるとお仕置きだと、リィムナにビシバシとやられる姿を皆に晒されることになっている。 「こんなことするより、ほんとは資料でもまとめた方がいいんだからね。でも、だからって意気地がないとこ見せたら、ただじゃ済まさないんだから〜♪」 もうすでにヴェローチェとテラキルに、素早い動きでとがった葉をまとめた刷毛をざりざりされている男達が、散り散りに走り出した。とりあえず、リィムナの攻撃とも呼べないちょっかいから、一定時間逃げおおせればいいことになっている。 なっているが。 「おっそーい!」 今までのところ、誰一人として三分と持った試しがない。 時間は巻き戻って初日のこと。 魔の森の跡地は、人里に近い場所ほどだだっ広い焼け野原の様相を呈していた。奥の方にはまだ木々も残っているが、風の具合を見ながらの焼き払い作業は順調に進んでいるようだ。 「何度かここには足を運んだが、最初はこんな光景が見られるとは考えもしなかったな」 「俺は、焼け野原ってどうも落ち着かなくて。見てるともったいない気になるんだよ」 焼畑か、春先の野焼きのようだと感慨にふける羅喉丸の横で、クロウが渋い顔付きでいる。緑が貴重なアル=カマルでは、焼け野原なんてものが発生することがほとんどありえない。よって、ここが魔の森だと理解していても、面積が広くなってくると慣れるのに少々時間が掛かるものらしい。 これはレムリアも同様で、しばらく呆然と景色を眺めていた。つまりは、それほどに魔の森が版図を縮めているということになる。 その光景が見られないジョハルは、アル=カマル出身ながらも驚愕にとらわれることなく、テラキルから周りの様子を説明してもらいながら、左右に顔を動かして、こう口にした。 「焼けてしまえば、魔の森も普通の森と同じ匂いじゃないか。瘴気があっても、植物を養っていた土地だ。大地の力を信じたいね」 「そうね。同じ匂いだわ。水源もあるし、そのうちに畑や牧草地に化けるのよ。そう思えば、将来有望よね」 半ば自分に言い聞かせるように、レムリアが足元の土を靴の爪先で小さく掘り返した。 そう、考え方を変えれば、薄いながらも土の層と、曲がりなりにも植物が生える栄養がある土壌である。砂地に何か植えるよりは、よほど先行きが明るいというものだ。 牧草地と聞いて、遊牧民出身のクロウは表情を緩ませたが、不意に何か思い付いたようで、一言断って走り出した。遊牧民達のところに、何か用が出来た様子だが、何事か分からない。 「今、クロウさんがすごい勢いで走っていかれましたけど、何か手が足りないことでも?」 「どうしたのかな。アヤカシくらいなら、あたしがすぐ片付けてあげるのに」 両勢力穏健派に案内されて、一番近い水源を観察しに行っていたティアとリィムナが不思議そうに近付いてきたが、そもそも残された方も何が何やらだ。 周囲の気配から危険はなさそうだと踏んで、当初の予定通りに植樹する区画などを確かめて回り、宿営場所に戻ると、クロウ達が何やら慌ただしく作業していた。 「あぁ、羊」 皆が納得したのは、遊牧民達が乳を搾るために連れている家畜の群れを入れる囲いを、クロウ達が今までよりしっかりしたものに作り直してことだ。今までは苗木などのある区画が囲われていたので、家畜は半ば放し飼いでいた。そのままにしていたら、作業を始めたところから食い荒らされていただろう。 家畜用の囲いは、元からの住人達の家畜分も強化することにして、そちらにも人を割く。残りで、植える苗木の数や種類をきちんと確かめ、種は地面に直接植えるのと、箱や鉢に植えるものとを仕分けた。 「お、これがあの時のか。無事に届いてなによりだ」 羅喉丸が目に留めたのは、以前に王宮からの依頼で関わった隊商が運んだ苗木などだ。無事に届いて、きちんと世話をされていたのだろう。青々と葉を茂らせて、地面に植えられるのを待っているようだ。 そうした苗木を前に、全員を集めて徹底したのが、植える間隔と水やりについて。 「これからの作業は、植えた植物の何割かは枯れる可能性があるものよ。それを見て、将来の緑化を進めるための情報を集めるの。いい加減な作業で枯れると、それだけ緑化が遅れて、自分の部族が苦労すると肝に銘じて働いて」 レムリアに厳しく作業の注意点を並べられた一同は、最後の一言で特に発奮した。それはいいが、相変わらず無闇と張り合う空気がある。 ここで、ティアが誰の提案とは言わずに、こう切り出した。 「まず一定人数で班を作って、作業量が大体等分になるように、区画や仕事内容を割り振ります。それを最初に、きちんと終わらせた班には、夕食の時にお酒が振る舞われることになりました」 実はクロウが『対抗心を作業に振り向けさせて、作業が順調な班には褒賞』と案を出し、作業の中枢の穏健派が物品を出すのを了解して、この提案になった。ティアが持ち出したのは、全体の『精霊の聖歌の使い手が言うと、聞く側の気が引き締まると思う』との判断による。 植え付けの作業は、王宮軍は農村出身者が中心になり、遊牧民側には羅喉丸と両派穏健派の農業経験者が付いて行うことになった。植え付ける場所はだいたい決めてあったが、区画の計測をやり直しつつ、瘴気濃度も記録しているのはリィムナだ。 瘴気の濃度に差が明確な区画には、それぞれ同じものを植えて後日の生育状況を比べるように仕切り直したりまでしている。その計画を見て、アル=カマルの気候風土と灌漑方法に合わせて、微修正を加えるのはレムリアである。 「この灌漑方法って、ここでも使えるの?」 「ええ。あそこの水源の近くに、水路の跡があるのよ。それを利用するなら、この方法が手間もお金も掛からないって」 レムリアが天儀で学んだ農耕方法の記録も、こちらの技術者達が懸命に写しを作り、リィムナは両方の知識を仕入れて自分のものにしていく。 もちろん計画の手直しばかりではなく、リィムナは植樹、レムリアは休憩所で作業に当たる人々の健康と安全管理にも勤しんでいた。リィムナが実際の作業現場で各自の様子を見て回り、異常があればレムリアに通報するようにもなっている。 木の植え方は、リィムナが教えて回ったりしているが、それ以前、土を耕すやり方は羅喉丸の指導領分だった。王宮軍は大体なんとかなるが、遊牧民は農機具と縁が遠い。腰が入らないことこの上もなく、腰痛持ちが大量生産されそうな状態で気が抜けなかった。 「腕の力で振り回すと、筋を傷めるぞ。疲れやすいから、作業も遅くなる。もっと体全体の動きで、駱駝に乗る時も手綱だけで操るんじゃないのと一緒だ」 鍬の使い方一つでこれだから、農業用語も結構通じない。こちらもあちこち回って、危険な手付きの者がいれば道具の使い方を指導し、合間にこれから必要になる言葉を教えたりと、なかなかに忙しい。 「防砂林? ああ、オアシスにある砂除けだよな」 とりあえず、この言葉はすんなり通じたのが、かなり嬉しかった。いずれ、確実に必要になるものだからだ。なにしろ焼野原、風と飛んでくる砂を遮るものを作る算段をしないと、植えた傍から木々が砂に埋もれていきかねない。 今の段階で、その不自由を一番受けているのはティアだったろう。無心になる精霊の聖歌の三時間、周辺に天幕を張ってもらい、フォルトや数人のジンが付いていてくれるとはいえ、我に返ると砂まみれも珍しくない。服や髪はどうでもいいが、喉を傷めないようにするのが大変だ。 その辺りの準備は当人も、レムリアもしていたので、大事にはならずに済んでいた。一日二回、水源地と判明している範囲の水路を浄化して回り、その後は瘴気濃度の計測も行われる。 「水源は、今まで手つかずだったんですの?」 「いつも最優先だけど、直ぐに周辺から再汚染されるんでイタチごっこだね。それでも、この辺りは今年に入って大分浄化が進んだよ」 この調子で、何十キロか先の魔の森の果てまで、いずれは根絶やしにしてみせると当たり前に語る人々を見て、ティアは小さな助力でしかなくても来てよかったと心底思ったのだ。 実際は、小さいどころではないのだけれど。 やがて、リィムナのお仕置きがない日が三日程続いた、平穏無事に作業が進んでいるある日。 将来、新たに植えるための植物の種を、木箱に植え付けていく作業を進めていたジョハルは、聞こえてきた声に一瞬だけ手を止めた。目が不自由とは思えないほど、丁寧かつ確実に種を植えているジョハルだから、この変化に気付いたものはいないだろう。 声の主のクロウも、作業の進み具合を尋ねて寄越したほかは、ジョハルに注目している様子はない。 「いずれ、この砂漠が草原になったら‥‥」 実際にそうなるには、砂漠から吹き寄せる風に植物が負けずに育つことが前提だ。すると今度はこれまでと違う風が吹き、雲が湧くようになり、雨も増えるだろう。これは羅喉丸も指摘したし、レムリアやリィムナもその可能性は高いと口にしたことだ。 日干し煉瓦の家は雨で壊れるし、家畜が濡れれば病気の素だ。アル=カマルの生活そのものが、大きく変わらざる得ない。急激な変化ではないだろうが、どう変化するかは誰も見通していなかった。 そうした話題が出て、だがそれでも生きていくために豊かな土地が必要だと誰もが思った中で、クロウは予想される変化の話を詳しく聞きに来て、いずれは変わると断言した彼に、 『砂漠が緑に変わるのは良いことだ。でも、それで砂漠で生きていくための技術や知恵が廃れていくのだとしたら‥‥砂漠の民と言うのもいなくなってしまうのかな』 砂迅騎と呼ばれる存在も、いずれ必要なくなるだろうかと、そう漏らしたのはジョハルも砂迅騎だからだろう。ジョハルにしたら、まだ自分をそうだと言ってくれるのはありがたいような、少し違和感を感じるような。 「ジョハルさーん、ティアさんが戻って来たから、皆でお昼にしよう」 手は休めずにつらつらと考えを巡らせていたら、リィムナが元気に走り寄って来た。声の調子から、近くまで来て、こちらに背中を向けたようだ。テラキルが彼の手を取って、リィムナの肩に乗せ、人の間を先導してもらいやすくする。 「足元を失礼。相変わらず、作業が速いな」 「決まった場所に種を落とすだけだよ。最初を間違えなければ、間隔は道具で測れるしね」 種を植えた箱は、羅喉丸がまとめて抱えて、それぞれの植物の名前が書かれた囲いの中に運んでいく。 「こらっ、ちゃんと並んでちょうだい。食べるのが遅くなるだけよ」 昼食の時間は全員一斉ではないが、誰かがちゃんと並んでいないのか、レムリアに怒られている。 「遅くなってすみません。お手伝いしますね」 戻ってきたティアが配膳に加わって、場が賑やかになった。彼女の術中の護衛は女性ばかりだから、ほとんど男所帯の中では華やかな一行なのだ。部族が違ったりして、あまり話す機会がない輩は、この機に少しの会話を楽しみたいと色めき立つのかもしれない。 おかげでレムリアもティアも余計に忙しいが、それで二人が文句を言うことはなかった。皆に穏やかに話し掛けて、体の調子を確かめたりしている。 人数を数えることは、ジョハルには困難だが、かなりの人数が枯れる確率の高い植物を植える作業に熱心に取り組んでいる。その成果を見るのは、自分ではない可能性も高いのだが、誰も嫌だとは言わないでいる。 「いつか、ここも緑の丘に変わるのかな」 「そのために、頑張ってるんでしょ?」 「おうよ。なんたってセベクネフェル様の希望だ。きっと実現してみせるさ。将来は俺も砂漠の民じゃなくて、草原の民になるかな」 その前に、何があるだろうかと悪いことも想像したジョハルだが、あっけらかんとしたリィムナの問いかけと、昨日と打って変った自信に満ちたクロウの宣言に、無闇と思い煩うことはしないと決めた。 いつか砂漠のすべてが草原になる日が来るとしても、それまではアル=カマルは砂漠と草原の国であるのだから。 それが争いのない国であれば、なにより素晴らしいことだろう。 |


