荒野は麗人の帰りを待つ
マスター名:七瀬もこ
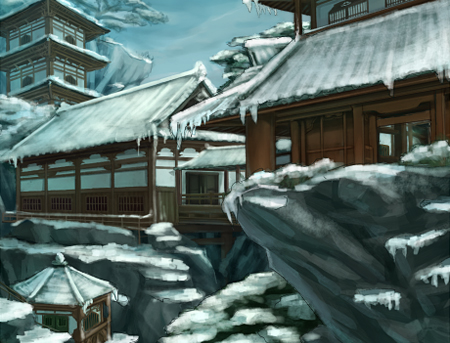
|
|
| ■オープニング本文 安積寺――その一角にひっそりと夜の息吹を待つ歓楽街がある。 随分と前になるが、歓楽街で遊んだ翌朝、一人の女性に出会った事がある。 美しい茶色の髪に橙色の瞳が印象的な人だった。 綺麗だな、と思っただけで、理由は充分だった。 今から思えば、それが過ちだったのかもしれない。 けれども彼女は、最も大切な宝だけは残してくれた。 それだけは感謝している。 ☆ 伊織――起きて、伊織。 薄絹を纏う女性に急かされて彼は起き上がった。着物のはだけた女性の艶かしい肢体が目に飛び込んでくる。 おはよう、と微笑んだ彼に女性は頬を少し赤くする。 「朝よ。帰るの? それとも……」 もう一夜、お相手してくださる? 彼はうーん、と首を捻ってしばらく考えこんだ。 この女性は数日前、安積寺をふらふらしていた時に出会った人だ。一応、大人の関係を結んでしまったのだから恋人という括りになるのだろうか。 何人目だったか……いや、数えるのも虚しい。 女性の栗色の乱れた髪を撫でて、彼は首を横に振った。 「いや……今日は帰るよ」 「あら、冷たい人」 「あはは。よく言われるけど、私はそんなに冷たいかな?」 「あら、やだ。拗ねてるの?」 「拗ねた方が可愛いと思ってくれる?」 「まったく、この人は――」 唇を重ねようと顔を近づけた女性に、彼は人差し指で紅の残るそれを制した。 「だめ。今日は、帰るよ」 「他に誰かいるの?」 「今は君しか見えないよ」 「上手いこと言って……」 事実なんだけどなぁ、と彼は肩を竦めた。 まあ、安積寺は何度も来ているし、それなりに顔馴染みも多い。 深い仲になった女性も多いが、別れを選んだ女性も多い。 「ねぇ……」 しなだれかかった女性の白い腕を丁寧に布団へ戻して、彼は長くなってきた前髪をかきあげる。 少し不満そうに女性は更に胸を腕に押し付けてきた。 「あたしじゃ、だめ?」 「だめではないけど」 きっと君は、燈子のお母さんにはなれないから。 それを言わないまでも、彼は悲しそうに微笑んだ。 良い人だと思う。綺麗だし、リードしてくれるし、会話も弾む。 好みかと言われると好みの範疇だが、だからといって再婚しようとは思わない。 思えない――という方が正しいか。 「帰るよ。ごめんね。娘がずっと待ってるから」 「あたしと娘じゃ、娘を取るのね」 「あはは。よく言われる」 愚問だよと言わんばかりに笑って、彼は緩んだ帯を締めた。 会計をしようと一階に降りた時だった。 明らかに店にそぐわない大柄の男たちが入ってきたのである。 「あんたが黎森の伊織か?」 「そうですけど、どちら様で?」 のんびり答えた彼に男たちは下卑た笑みを浮かべた。何となく言いたいことは分かる。 女みたいな顔と体で、女をくわえこむなんて。 線が細いのは生まれつきだし、特に苦労もしたことがないんだけどと思いつつ、彼は相手の言葉を待った。 「あんた、俺の女に手を出した責任はとれんだろうな?」 「どの女ですか。覚えがありすぎて……もう少し絞ってくれると、私も対応できるんだけど」 「ふざけた寝言ぬかしてんじゃねぇぞ、おい。ああ? あの女だよ」 顎で示された方を見ると、先程まで同衾していた人が不敵に笑っていた。 「おい。こいつで間違いねぇんだな?」 これは、彼女への言葉。 頷いた彼女を見て、彼はようやくちょっとだけ危機感が出てきた。 だが、もう逃げられない。 「ちょっと体を貸してもらおうか。なに、悪いようにはしねぇよ。何でもおめぇ、随分と金持ちらしいじゃねぇか」 「え……」 「俺の女に手ぇ出したこと、後悔させてやるぜ」 「ええ……?」 彼は決して怯えた声で言ったのではない。 いつの間に娘はそんなに稼いだのだろうと疑問に思っただけだった。 ☆ 何なのよさ、これーーーーーーーーー!! 亡き祖父宛に届いた手紙を見た燈子は怒髪天を衝く形相になり、黎森島の尼寺へ飛び込んだ。 受付をしていた尼はびっくりして思わず筆を落とし、歩いていた別の尼は驚きのあまり湯のみをひっくり返して尻餅をついた。 「おばちゃん! おばちゃん!」 「どうしたね、燈子」 「お……お、お、おとう、さんがっ!」 「伊織がどうかしたかね?」 「お父さんが、お父さんした!」 意味不明である。 ぷるぷるしている燈子の差し出す手紙を見て、彼女達もようやく合点がいった。 というか、ようやくこの時が来たかと思った。 「あれだけ遊んでいればねぇ……わたしゃ、いつ刺されるかと」 「まったくだ。良い薬になって欲しいけど」 「違う! 違うの、おばちゃん! そうじゃなくて!」 ダン、と机を叩いた燈子は尼に顔を突き出した。 「お父さんの身代金がたった10万文ってなにさ!」 「10万でも高くないかい、燈子」 「安い! ふざけてんじゃないわさっ!」 貧乏人の燈子でも、父親の価値はそんなものではないのだろう。 あれだけ苦労させられているのに、それでも彼女にとっては父親なのだ。 「おばちゃん、私、安積寺に行く」 「これ、燈子」 「行って、お父さんを連れ戻して、誘拐犯をボコボコにして説教してくる!」 「お待ち、燈子!」 尼の声も聞かずに燈子は三本爪のフォークを担いで飛び出した。 おろおろする尼を別の尼が宥め、それからようやく彼女達は安積寺のギルドへ事の詳細を伝え、応援を要請したのであった。 翌日、安積寺の入口で羊を伴った少女の、職員に引き止められている姿が目撃されることになる。 |
| ■参加者一覧 13歳・男・騎  獅子ヶ谷 仁(ib9818)
獅子ヶ谷 仁(ib9818)20歳・男・武 24歳・女・サ 15歳・女・吟  黒憐(ic0798)
黒憐(ic0798)12歳・女・騎 18歳・女・騎 |
| ■リプレイ本文 ゴロゴロ、と大八車が地面を押す音が街道に響く。 十万文……と言えば、かなりの重さである。道中、行き交う人々が不思議そうな目でその一行を見つめた。 風呂敷、してきて良かったなぁ、とエレイン・F・クランツ(ib3909)は肩を竦める。 燈子は、尼から連絡を受けたギルドの職員が、安積寺の入口付近で保護していた。 残していこうという話もあったが、何が何でもついていこうとする少女を彼らが引き受けた形だ。 「……ねぇ」 「ん、なに?」 大八車を引くリュドミラ・ルース(ic1002)以外、黒憐(ic0798)とエレイン、そして燈子は荷台に乗っかる形である。 「その、『角』……本物?」 「え? ほ、本物だよ」 たじろいだのは、いきなりそんなことを聞かれたからだ。 「獣人は……昨今珍しいわけではないのです……かくいう憐も……」 呟いて自分の耳を触った黒憐に、前方のリュドミラは振り向かずに「そうだよー。普通にいるよー」と付け加えた。 そうなんだ、と黒憐の黒い猫耳をじっと見つめた燈子は、続いてエレインの綺麗に渦巻いた角を指さした。 「触って良い?」 「えっ」 何を言うかと思えば。 一瞬きょとんとしたエレインは、ついで困ったように眉を寄せてはにかんだ。 「どうぞ」 折角堪えたのに、燈子が角を触って「梅々と違うっ」と声を上げた時は、思わず噴き出してしまった。 花街の入口まで来ただろうか。 ねぇ、押してるー? いやに重いんだけど。 相変わらず振り返らないリュドミラの声に答えたのは黒憐だった。 「……ちゃんと押してます……大丈夫……」 「ほんとにー?」 親友の声も半分諦めているから、気づいてはいるのだろう。 黒憐は小判に埋もれるようにして休んでいる梅々の毛を撫でながら燈子に言った。 「……燈子さん……お父さんの事……聞かせてもらえますか……?」 「んー……一言で表すと、大きい子どもだわさ」 ふふ、とエレインが小さく肩を揺らして笑った。確かに、聞いただけでもそれしか浮かばない存在だ。 「人を疑わないし、すぐに色々あげちゃうし、危機感がないし、興味のあることに突っ走るし……よくあんな男と結婚したがる女の人がいるなって思うのね」 弱冠十二歳に再婚の心配までされる男もなかなかおるまい。 「しかし、何でお金無い人なんて誘拐するのかな……?」 「お金で買えないものが……あるのです……」 黒憐の言うことはもっともだが、そんなに価値のある人間とは思えないリュドミラである。 「でも、燈子ちゃんはお父さんに帰ってきて欲しいんだ?」 そう聞いたエレインに、何とも言えない顔になった燈子はフォークをぎゅっと握りしめた。 「保護者は……必要だわさ」 「……つまり……燈子さんはお父さんの事が……大好きなんですね」 「嫌い……ではない、けどっ」 詰まりながら言った燈子に、一人で大八車を押すリュドミラが、「偉いっ!」と感動の声を上げた。 ● いやしかし、本当に父親に似なくて良かったな。 一足先に花街へ入った獅子ヶ谷 仁(ib9818) はあちこちで伊織と、彼を攫った集団について聞いて回っていた。 すると出るわ出るわ――人攫いではなく、伊織の花街での遊びっぷりが。 しかも遊ぶだけ遊んで、その代金は全て女持ちだ。 「ヒモだな……完全に……」 流石の仁も言葉が無かったが、遊んだ女達とは後腐れなく縁を切るか、今も親しい友人として付き合い続けているという清算の手際良さは及第点か。 「伊織はんと遊べるなんて、うちらの間では喜ばしいことやわぁ。あの方、しっかりしてはるし、マメなんですよ」 遊女の一人がそんな事を言うのだから、花街はよく分からない。 助ける気が右肩下がりの仁だったが、何軒か当たった先で妙な事を聞いた。 「最近、伊織さんが懇意にしていた遊女なんですけどね、結構な借金握らされてねぇ……その話を聞いた伊織さんが、大分慰めていたって話さね」 「借金、って言うと?」 「賭場だよ。よくある話さね。それに、あの女はちっと悪い男と付き合ってるって噂だったしねぇ」 お金が無いの。助けて。 うん、貴女の助けになりたいな。うちにお金があると良いけど……。 伊織さん、お家は? そうだね――、 そこまで容易に想像できた。伊織の事はよく知らないが、おそらく馬鹿正直に答えて、女が先走ったのだろう。 女の情報を信じた男が、借金の一発回収を名目に計画を立てたに違いない。 「……まともな奴はいねぇのかよ」 何とも頭を痛い話だ。 ● まったく……困った旦那もいたもんだね。 胸元の大きく開いた掛衿を正した火麗(ic0614) はぼやいた。 「とにかく、助けないことには目覚めが悪いしね。勿論、誘拐犯にはちょっと痛い目を見てもらうことにはなるだろうけどね」 頼むよ、と彼女は合流した仲間たちに溜息混じりに言う。 「……やりすぎなければ大丈夫!」 グッと親指を立てたウィオラ(ic0616)の笑顔がなんだか怖い。人質にはやり過ぎないように……とは、分かっているだろうから言わない。 「じゃあ行こうかね」 金を運んできたエレインと黒憐を見てから、火麗は燈子へ視線を移した。 今にも飛び出しそうな表情の少女は、状況が分かっているのか不安そうに視線を泳がす羊の毛をぎゅっと握っていた。 男たちにとって、それは結構予想外の構成だった。 本殿に伊織と女を残して外に出てきた男たちは互いに目を見合わせる。 艶っぽい女に、少女二人に、獣人――女二人は関係者として、もう一人は金の運搬役に雇われた者だろう。 そう、男たちは結論付けた。あまりにも非現実的なので、木陰に避難した梅々は見えていなかったようだ。 「金は持ってきたんだろうな」 一際大柄な男が言った。大八車から一部の金を風呂敷に包み、エレインが無言で自分たちの前に置く。 「あたしの旦那が世話になったね。金は持ってきたから、離してくれないかい?」 「ああ? あんた、あいつの嫁かい。ったく、妻子持ちで良いご身分だなぁ」 まったくだが、妻として認識されている火麗が同意するわけにもいかない。 代わりに、夫の不貞に諦めた妻の仮面を被った火麗は呆れたように言った。 「でも、十万なんて……ろくでなしの宿六にそんな価値あると思っての」 「はっ。知るかよ。金がありゃ、何でも良いな」 「うち、そんなお金ないしっ!」 すかさず燈子が全力で否定する。 その隣では、猫耳を帽子で隠す黒憐がしくしくと泣いていた。 「パパを返して……かえしてよう……」 「――そうだ、お父さん! お父さんを返してっ!」 「……チッ、うるせー餓鬼どもだな」 苛立ったように言った男が、後ろで控えていた仲間たちに手で合図をする。エレインの持っている風呂敷や大八車を奪え、ということか。 じりじりと距離を詰める男たちが充分に本殿から離れた時だった。 開拓者達の猛攻が始まった。 仁は本殿の屋根に、リュドミラはその近く、本殿の中を観察できる位置に身を隠していた。 「多分、あの細いのがそうか……よく見えないけど」 呟いたリュドミラが捉えたのは、間違いなく伊織だ。燈子が見れば分かると言う通り、他の男と比べても何となく違う気配がする。 もうちょっと近くで見れれば、と彼女が目をこらしている間に、男たちが動いた。 頃合いだ。 「そろそろだな、行くぜ!」 仁は瓦を踏み台にして高く跳躍する。そのまま本殿の入口に着地して、間髪入れずに扉を一気に開いた。 「な、なによあんた……!」 縛られている伊織にしなだれかかっていた女――何をしようとしていたのかは、この際脇に置いておく――が襟を合わせながら慌てて立ち上がった。 だが、その頃には仁が彼女の懐に入っている。 「殴りゃしないさ。ただ大人しくしてもらうぜ」 「ちょっと――きゃぁっ」 悲鳴を上げた女が床に組み伏される。手早く腕を背後で交差するように抑えて、仁はぽかんとしている伊織を見た。 なるほど、まあ……顔は悪くない。男から見ても美形だ。 だが、甲斐性はお察しというやつだ。 色々言ってやろうかと思ったが、とりあえず仁は溢れそうになる言葉を抑えながら言った。 「おい、あんた。とっとと逃げろ。娘が迎えに来てるぞ」 一方の外では、異変に気づいた男たちが明らかに狼狽していた。 「おい、仲間がいるなんて聞いて無いぞ!」 「どうなってんだ、糞がっ!」 「こうなりゃ交渉失敗だな、男を殺せ!」 「――やかましいわっ!!」 喚く男たちを大喝したのは火麗だった。怯んだ男たちの視線が交渉役の三人に注がれる。その間に、仁が本殿に入るのが見えた。 「畜生! やっちまえ!」 刃物を握った男たちが燈子達へ突進したが、 「危ないですよー!」 少女へ刃を振り被った男の脇を見事なタイミングでウィオラのハープが強襲した。とはいえ、アヤカシ相手ではないので力は全然入れていないのだが。 「痛い目見たくなければ、近寄らない事です!」 角で脇腹を殴られた男が綺麗に地面に転がった。相当ダメージが大きいのか、ぴくぴくと動いて失神している。 「あら……そんなに強く殴ってないですよ?」 「てめぇ――っ!」 きょとんとしたウィオラに激高した男が拳を突き出す。 代わりにそれを受けたのは黒憐だった。鉄傘で拳を受け止めた少女は、先程の泣き顔から一転、無表情で大きな男を見上げる。 「……安心してください……峰打ちです……」 「ぐ、ぁ……!」 (黒憐の中での)コツン、と男の胴を鉄傘で突いて、黒憐は倒れた男を足で転がした。 ここまで来ると、男たちも否応なくこの交渉人達が只者ではないと実感するというものだ。 「――なら、人質を増やすまでだぜっ!」 焦った男たちは手近な燈子の腕を掴もうと手を伸ばした。 だが――、 「させないよ」 盾を構えたエレインが、がっちり燈子を守っている。わなわなと震える男を剣の鞘で殴って、彼は手早く荒縄で男たちを縛り上げた。 リュドミラが本殿付近の男を吹っ飛ばすのを確認して、エレインは燈子と隠れている梅々に言った。 「手伝ってくるよ。見張りよろしくっ」 仁が本殿を抑えているので、リュドミラは本殿入口に留まっていた男に一気に肉薄した。 「この……! ここにも居たかっ!」 「遅い!」 吠えたリュドミラが力一杯剣を振る。 「スタンアタァァァッァック!!!!」 ――と、叫んだは良いものの、体が鈍い。活性化し忘れたか。 「まあ、これで丁度良いよねっ!!」 勢いに任せて、リュドミラが男を吹っ飛ばす。文字通り宙を飛んだ男の大きな体が大木に激突してボロ雑巾のように転がった。 「……わぁ、すごい力だねぇ」 拘束を解かれて仁と一緒に出てきた伊織とリュドミラの視線が合った。 かっこ、いい……? 無意識に働いた乙女心の鼓動に、リュドミラの顔が急に赤くなる。 「ス、スタンアタァァァァァァックゥゥ!!!!」 「おわっ、危ねぇぞ!!」 リュドミラの放ったスタンアタックは、勿論ただの剣の強打だったが、仁が慌てて防いだおかげで伊織は怪我を免れた。 当たっていれば即死級の照れ隠しだった。 ● 確かに、伊織という男は非常に顔が整っていた。 「確かにかっこいいですが……憐の相手には足りません……男気誠実真面目さ勇気腕っ節……何より肉球が足りません」 真顔で言い放った黒憐の隣で、リュドミラは何とも言えない表情のまま固まっている。 その伊織と再会した燈子は余程心配していたのか、父親にひっしと抱きついたまま、しばらく離れようとしなかった。 少女の姿に、火麗が思わず伊織に説教したくらいだ。 「いくら顔が良くても娘にいらん心配かけるのはダメ親父の象徴だよ! ったく、燈子ちゃんには同情するわ」 「うん、ごめんね」 「……ほんと、燈子ちゃんの苦労が窺い知れるってもんだわ」 「というか……明らかにお金持ってないこの親父さんの、一体どこ見て誘拐しようと思ったんだ?」 呟いた仁の言葉は、荒縄で縛り上げられた誘拐犯達へ向けられている。 やっぱ顔なのか、と嘆く仁の脇で、誘拐に加担した女がさめざめと見当違いの事を言いながら泣いている。 「あたし……伊織の事、本当に好きなのよ」 「うん、私も貴女が好きだったよ」 「違うの。あたしは何も知らないの」 「うん。知らなかったんだね。ごめんね」 「なんでお父さんが謝るのさっ!」 燈子に怒られた伊織が苦笑する。 伊織の言葉は全て、もう過去形だ。 やんわり、それでいて明確に拒絶してなお微笑みを絶やさない伊織の方が、実は少し残酷なのかもしれない。 (まぁ……でも、) 話を聞いていたウィオラは息を吐く。 この男にそんな冷酷さを計算する脳みそがあるとは思えない。 どう見ても人畜無害で、どう考えても色々抜けている。 「それじゃ。今度はもっと怪我がないように頼みますよ」 一名の重傷者を荷台に置いて、ギルドの職員達はお小言と共に誘拐犯を連れて行った。 残された開拓者達に真っ先に頭を下げたのは、やはり燈子だった。 「ありがとうございましたっ。お父さんがご迷惑をかけました」 「燈子がお世話になりました」 「違うでしょ!」 またしても怒られた父親が娘に無理矢理頭を下げさせられる。 逆じゃないのかなぁ……と思いつつも、エレインは伊織の傍に寄る。 「伊織おじさん、あのね」 「やぁ、梅々は人間になれるんだ。凄いね」 娘と同じ反応を見せた伊織に、エレインは口元を綻ばせるだけに留めておいた。 エレインと同じ目線になった――よく見れば、伊織は結構背が高い――美形に、彼は耳打ちした。 「もし、燈子ちゃんのおかーさんになる人を探してるんだったら、それは間違ってるよ」 燈子ちゃんのおかーさんは、一人しかいないんだ。誰も代わったりできないよ。 だから、おじさん自身が燈子ちゃんと一緒にいてあげて欲しいな。 そう続けた羊の少年に、伊織は何も言わずに金色の柔らかな髪を撫でた。 「梅々は燈子の事を心配してくれるんだね。ありがとう」 「あと……僕はエレインで、梅々じゃないよ」 「あは、ごめんね」 困ったように微笑んだ伊織は背筋を伸ばした。 「燈子。帰ろうか」 「えっ」 素っ頓狂な声を上げたのは燈子である。 「か、帰るの……うちに?」 「うちに。……だめ?」 「駄目……じゃ、ないっ!」 パッと顔が輝いた燈子である。 「――じゃあ、今回の借りは親父さんが牧場で働いて返すってことで」 「えっ」 突然の仁の言葉に、今度は伊織が素っ頓狂な声を出した。 「当然だろ。娘にここまで心配させたんだ。俺達が見張るから、きっちり働いてもらうぜ」 「うー……それは困るなぁ」 布より重いものは持ちたくないんだけど、という伊織のささやかな反抗は、まるっとするっと無視されたのである。 翌日、早朝着の船に乗って伊織と燈子は黎森島に帰っていった。 後で聞いた話では、三日ほど親子時間を満喫した後、やはりふらりとどこかへ旅立っていったとのことである。 了 |


