エネミー
マスター名:KINUTA
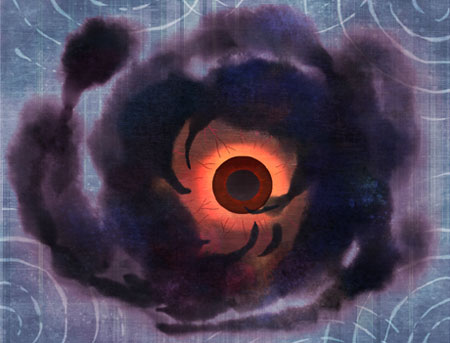
|
|
| ■オープニング本文 この世の暗がり、混沌のどこかにうごめいている影も形もないアヤカシ。 その名は悪夢さん。能力は名前そのまま、悪夢を見せること。 ● どうも、アヤカシ隙間女です。悪夢さんの新作実況中継。なう。 この間とちょっと似た舞台装置ですね。高い頑丈な壁が聳えています。 規模が大きくて端が見えません…国全体を囲んでるんですかね。 遠方から煙が上がってるように見えますが、さてあれはどういうことか。 とにかくその壁の上、取り込まれた人たちが二手に分かれちゃっています。 「…クソ野郎…」 のっけから女騎士エリカが罵倒を始めました。 瞳孔に一点の光もないですね。激おことかいうレベルを超えて暗黒面に落ちてるんじゃないかってほどお怒りです。 「…向こうに逃げきる前に間に合ってよかったわ…今ここで死んで」 こっち側にいる軽そうな男は…えーと、ロータスでしたか。エリカの多分婚約者。 イヤな笑いを浮かべてます。かなりヤケクソ入ってるみたいです。 「すごい手のひら返しですね…ねえ、これまで僕とあなたは仲良くやってきたじゃないですか」 「止めて吐き気がする」 「…いったい何がそんなに気に入らないんでしょうか? よかったらお聞かせ願えませんかね。騙されてた間抜けな自分にムカついて八つ当たりしてるだけでないのでしたら、是非」 言った途端白刃がロータスめがけて振るわれました。 彼、それを腕で受けました。 ああ、プロテクターつけてたんですか。剣めっちゃ食い込んでますけどそのおかげで切り落とされずにすんだと。 あり得ないですねー。現実だったら死んでるはずですこの人。 「…つい昨日までの恋人に対してずいぶんな仕打ちじゃないですか?」 「黙れ! 町を焼いて罪もない人を大勢殺して! 恥知らず! 害獣!」 ロータスがエリカの喉に手をかけました。 「それはお前等だって一緒のことだ! この悪魔!」 剣を取り落とすほどの呼吸困難に陥りながらも、さすが野獣メンタルの持ち主、反撃に出ました。 ロータスの目を殴りつけ相手が手を離した隙に離れ、再度武器を取り戻します――この人の場合、現実でも十分このくらいのことしそうですね。 ロータス側の人間とエリカ側の人間が武器を手に取り…血の雨が降りますねどう考えても。 ここだけ見ていても事情がよく掴めませんから、悪夢さんのくれた解説書、読んでみましょうか。 ええと… 「人類は二つの勢力に分かれている。慢性的な紛争状態。アヤカシは現実に準じて存在するが、人類側がこのような有様なのでさしたる抵抗も受けず、勢力をやすやす拡大、現在世界の三分の二以上が魔の森に飲まれつつある」 …悪夢さん、これって例のあの時のアレにそっくりなような…。 同じ状況下におかれたら人間は、同じ行動を何度でも取るだろうということを、確認しておきたい? 今後のためのデータ収集? なるほど。 ともあれロータス側が工作員、エリカ側がそれを追いつめた特殊部隊というかそんな感じですかね。 「アガサ…うち言うたことがあったよなあ? うちの村は敵軍の襲撃を受けておとんもおかんも死んだんやて…それ知っといてこの3年間、うちらと付き合ってたんか…仲間面して…クズや、あんたほんまにクズや!」 「…うるさいっすよアリス! クズ? 上等っすよ! そうやっていつまでも喚いてりゃいいっすよ! 馬鹿の証明として! 大体ねえ、あたしはいっぺんもお宅等を仲間と思ったことなんかないっすよ! ウザい勘違いしないでほしいっすね!」 「…このっ…畜生がっ! 死にさらせ!」 あ、ヤンキー女学生組もいた。 いつになくどろどろしそうです。すでにこの時点でお腹いっぱいですね私。 「待て! お前たちちょっと待て!」 誰か来た。 あれは機械ギルドのボスコイとかなんとか…。 「アヤカシの侵攻を受けている今、人類同士でこんなことをしている場合っ」 …なんかいい正論言いかけたのに流れ弾受けて即死ですか。 「ボーちゃん! しっかりせえボーちゃん、ボー…くっ…おんどれよくもやりおったな!」 女学者のファティマがキレました。 多分仲介に来たはずなんですがねえ。 負の連鎖ってこういうのを言うんでしょうか。 ああ、あの人この人死んじゃった。 うーん、理不尽。 |
| ■参加者一覧 / 鈴木 透子(ia5664) / 成田 光紀(ib1846) / リンスガルト・ギーベリ(ib5184) / リィムナ・ピサレット(ib5201) / アルバルク(ib6635) / イデア・シュウ(ib9551) / 鎌苅 冬馬(ic0729) |
| ■リプレイ本文 ついさっきまで生きてものを言っていたアリスが額を撃ち抜かれ横たわっている。 その前でアガサが喚いている。 「あああっ、くそっ、畜生!」 立ち上がろうとしているが無理だ。腹から背中までレイピアが突き出ている。痛いという単語が出ないのは、感覚が麻痺してしまっているからだろう。 (あれはもう持たない) リィムナ・ピサレット(ib5201)の観察に呼応するかのように、アガサが倒れた。 「……」 リィムナは乾いた笑いを浮かべ、リンスガルト・ギーベリ(ib5184)に視線を移した。 「そっかあ、これまでのことは全部ウソだったんだ、一緒に登下校したのも町へ遊びに行ったのもお泊まり会したのもお誕生日のパーティしたのも…リンスちゃん…友達…大勢死んじゃったんだけどさ…それ、どう思う…? これじゃあ人殺しだよリンスちゃん…」 リンスガルトの目は冷たかった。軽蔑が声に滲んでいる。 「汝はまこと痴れ者よの。そのようなこと、言われずとも承知しておるわ――妾は何とも思わんの。すべては汝らが招いたことではないか。当然の報いじゃ」 「…え? ごめん待ってリンスちゃん、言ってる意味が分からないんだけど? 報いって何? 皆平和に暮らしてただけなんだけど? いきなりテロ攻撃してきたのリンスちゃんたちなんだけど?」 リィムナの手の震えは止まらない。 リンスガルトの『秋水清光』が、ガツッと足元に叩きつけられた。 「…汝らは妾たちの国を蹂躙しておきながら、いざ自分たちに刃が向いてくると、臆面もなく被害者面をするのかや…罪なき民の生皮を剥ぎ轢き潰すような真似をしておいて…町一つが焼けたくらいがなんだというのだ! そんなもの、当然の報いではないか!」 一瞬目を点にしたリィムナが狂ったように笑い出した。おかしくてしょうがなかったのだ。事実が白日の下にさらされているのに、まだ何かの間違いではないかという希望にすがろうとしていた自分の、馬鹿さ加減が。 「あは、は…分かったよ。憎いリンスガルト・ギーベリ! あんたはあたしの敵だ! いや、人類の敵だ! 駆逐しなくちゃね!」 リィムナは口に『ヒーリングミスト』を当てた。 「ようやく飲み込めたようじゃな…さあ、覚悟するがよいわ! ゆくぞリィムナ!」 リンスガルトが刃を持ち上げる。 彼女らは、息もつかないほどの早さで立ち回りあう。つかず離れず対になってダンスをするように。 そして、示し合わせた如く場から離脱して行く。壁の側面の段になっている部分を足掛かりに、降りて行く。 ● アルバルク(ib6635)は目を細めイデア・シュウ(ib9551)と対峙している。 「まさかアルバルク様が鼠の一味であったとは…」 イデアはいったん言葉を切った。 師とも仰いだ相手が敵であったについて、怒りより高揚を覚える。少なくともリィムナのように、絶望を感じることはない。 理由は彼女本人が一番よく分かっていた。 (自分はこの人と戦いたいと思っていた。ずっと) 『ペンタグラムシールド』で体の前面を防御しつつ、『グラム』を脇にぴったりつけ、構える。 「殺る気アリアリだな」 「当然です。現行犯ですから言い訳は出来ませんよ――またなんでこういうことをなさったんですか?」 「まあ、仕事だからかな…特に私怨があるわけじゃねえ。根無し草だからな、俺は――で、どうしても戦わなきゃいかんのかね、これは」 問いかけにイデアが答えることはなかった。 娘のようにさえ思っていた相手から発される闘気と殺気を受け止めアルバルクは、髭を撫でる。 「ぐぁっ!」 悲鳴。 隙を作らぬよう目だけで確認を取れば、ロータスの右太ももあたりから吹き出した血が彼女の足元に溜まりを作って行く。 血まみれの剣を持つエリカがどんな表情をしているのか、窺い知ることは出来ない。背中を向けていたので。 ただ叫びだけが聞こえた。ロータスのと重なって。 「エ、リカッ!!」 「あ、うぁああ!?」 ロータスがエリカに全力で飛びかかり抱きこみ、諸共壁から落ちて消える。 ほんの一瞬の出来事だった。 「エリカさん!? エリッ…」 鈴木 透子(ia5664)が壁の縁に身を乗り出し、下を見下ろした。すぐ目を閉じ顔を背けたところからするに、両方生きてはいないのだろう。 まあ50メートルはある場所から落下すれば当然だ。自分だってそうなるだろう。イデアから同じことをされれば。 (殺るか殺られるか…なんだが、どうにも現実味がねえな。どこで間違えちまったんだかな、全く) 珍しく感傷的になるが、土台考えたって分かるはずもない。世界はこんなものだと割り切るしかあるまい。とっくに抜け殻となった理想を掲げ、惰性で殺し合う。魔の森に飲まれ世界はどんどん狭まって行くが、地上に立つ場所が有る限り、この状態がいつまでも続くんだろう。 「…俺とやり合うことに迷いはねえか?」 「ずっと実力を知りたいと思っていた相手が目の前にいる。ならすることは一つでしょう?」 「……ま、いいぜ。全力で、掛かってきな。この先も強くなりてえならな」 アルバルクは咥え煙草を吐き捨て、重心を落とす。 (向こうのやり方は判ってる。盾で突っ込んで切る、だからな。小細工考えるくらいは成長してるかねえ?) ● 成田 光紀(ib1846)は眉を顰め、切り合い撃ち合う修羅場を眺めている。 その前には、彼の作り出した式に手足を取られたファティマがいる。 「さて、今しがた死におった者の言うように、本来アヤカシの侵攻がある以上、人間同士で争うのは道理に合わん」 「なにしとんねん…放さんかい!」 耳の毛を逆立て、尻尾を膨らませ、噛み付いてきそうな形相。 光紀は彼女の手からジャンビーヤを取り上げ、はるか地上へ投げ捨てる。 「ファティマ君は先ず頭を冷す事だ。いやしくも学者であるのだ、手ではなく頭で戦うべきだろう。これ幸いとやる気を出している者もいるようだがな」 実に冷静な態度だが、だからといって光紀が心から平静かというとそうでもない。いきなり攻め込んできた相手方への憎しみはある。ただ彼の場合、怒りは燃え上がる形を取らない。逆に冷える。エリカたちと違って。 敵のものか味方のものか分からない(どっちにしても似たようなものだが)銃弾が飛んできた。 咄嗟に壁を作り防ぐ。そこに透子が駆け込んでくる。 「あっ、よかった。生きてらしたんですねファティマさん」 彼女の様子に光紀は一人ごちた。 「ふむ、少しはまともな頭もいるようだ」 『ド・マリニー』を手に計測を行うと、瘴気の濃度は中程度。 魔の森が繁茂する御時世、このくらいの数値がノーマルというものだろうか。 とにかくゆっくり考察するに、ここは全然向いていない。 「うおおおおおお!」 死闘の苦痛からか恐怖からか、男がいきなり切り込んできた。例によってどちらの陣営なのかはっきりしない。 「チッ」 光紀は炎の狼を呼び出し、相手を襲わせる。 こんなところで間抜けに殺られるなど、全く御免こうむる事態だ。早く退くにしくはない。 即決を下した彼の側で透子は、ファティマを宥めかけていた。半分は自分の気を落ちつかせるために。 ここに来るまでに目にした惨状を思い出せば吐き気がするほどだ。 しかしそれでも透子は、敵対行動をとれないでいる――アヤカシではなく人間を相手に生の殺し合いをするというのが、恐ろしくて。 「ファティマさん、一緒に弔いをしませんか。」 「……」 それだけでは説得されてくれそうもないと見て、続ける。 「仇討ちなら後でも出来ますけど、弔いは今しか出来ません。もしファティマさんがここで殺されたら、ボスコイさんはこのままなんですよ!」 光紀が脇から口を挟む。 「その通りだな。そしてファティマ君、戦った場合君は確実に負けるね。何故なら戦闘員ではないから。このままここにいたら、俺たちだって危ういものだ。話を聞く気がない連中は放っておくに限るよ。撤退しよう」 彼がそう言い退けた側に、刃を掴んだ手首が落ちてきた。 鎌苅 冬馬(ic0729)が『終華』の血糊を振り払い、苦悶に転げ回る相手をそのままに駆けてくる。押し潰した怒りを瞳にたたえて。 「俺が護衛しましょう」 戦闘開始直後から彼は周囲の状況把握に努めていた。であるから、ほとんどのものが気づかなかったボスコイの声も耳に入っていた――そのせいで、微かながら周囲と意識のずれが生じた。 敵をここまで追い詰めてみたものの、そういえば、いかにして短時間の間にあそこまで町を壊滅状態に至らしめたのか、その手段が不明だ。 今目にしている武器のようなものでは、とてもあれだけ広範囲の被害を出せるとは思えない。 ふっと脳裏にアヤカシという単語が閃く。 (これは…アヤカシの仕業なんだろうか…?) 『そうだ』と頭の片隅で肯定の声が湧き起こる。 (――元凶は何処に居る?) 迎え来る刃を擦り抜けあるいは払いながらそのことを考え続け一つの結論に至る。 (…争っている場合ではない) 素早くしゃがんだ彼は、ボスコイの体をかつぎ上げる。 「…まぁ、簡単に死ぬつもりは無い」 透子は小鳥の式を作り、飛ばした。 「いったんここから降りないといけません。」 上空から今一度確かめてみれば、自分たちのいるすぐ近くに門らしきものがあった。階段がついている。 真下には建物郡がある。 あちこち崩落し人影もない、見るからに廃墟と化している街区だ。 「行きましょう、ファティマさん!」 拘束を解かれたファティマは数秒唸っていたが、ピシッと間近に銃弾が着弾したのを契機に動いた。走りだした。戦場と逆方向、つまり光紀たちが向かう方向に。 ● 地面が白い灰のようなもので覆われている。 崩れた街区には猫の子一匹も見当たらず、草一本も生えていない。空虚だけが支配している。 これから雪崩をうち瘴気が入り込んでくるのだろう。ここはもう人間が住める土地ではない。 「くっ、ちょこまかと動きおって!」 リンスガルトはリィムナを追う、リィムナはそれを避け逃げ続ける。 逃げるだけでもかなりの労力を要し、演奏に集中出来ず、なかなか効果的な一撃を与えられない。 (…外じゃ、音が拡散する…屋内の方がいい!) 真っ先に目についた建物へ飛び込む。 そこは広いホールだった。 扉も窓も開け放してあるため灰が床に入り込んできている。 正面には巨大な石像――大男が背の上へ球体を担いでいるというもの。表面は劣化しヒビだらけ、頭部が首の部分から崩れ落ちていた。 その上に飛び乗った彼女は、追ってきたリンスガルトに言う。 「ここだよ、リンスガルト!」 喉に刃が肉薄した次の瞬間、リィムナは自身の存在をリンスガルトの目前から、意識から――世界から消す。 自分が一体何をしようとしていたかリンスガルトには分からなくなる。 訝しげな顔をし、動きを止めたその前に、再びリィムナが出現した。 「負けないよっ!」 フルートの旋律に呼応し、頭に焼け火箸を突っ込まれるに似た激痛がリンスガルトに襲いかかる。 「ぐああああああ!」 あやうく意識が飛びそうになるのを堪えたリンスガルトは、第二の攻撃を食らわぬよう必死で起き上がった。 (あと一撃喰らえば終わりか…面白い!) 渾身の力を振るい俊足移動し、手元を狙う。 硬い音を立て、『ヒーリングミスト』が床に転がった。 「フルートが!」 リンスガルトは剣をかなぐり捨て相手に飛びかかり、床に組み敷いた。首に手を当て、絞め上げる。 「くく…首をへし折ってくれる…」 「が…は…」 呼吸を止められ視界がどんどん暗くなっていく。 その最中にリィムナは、奇妙としかいいようのない感情に囚われた。 何故かそうしなければならない、いつもそうしてるような気がして――目を瞑り、唇をすぼめた。口付けを待つように。 「何じゃその顔は…」 リンスガルトもまた奇妙な感情に陥った。こうされたらこうするものだというように、気がつけば熱い口付けをしていた。 「リィムナ…ん…」 「ん…ふっ…あ…んっ」 ● イデアは盾を構え高速移動する。 彼女が見ているのはアルバルクの足元だ。右、左どちらに動くか。 ここは壁の上、足場は限られた範囲しかない。 (こいつ…崖っぷちに追い詰めてくる気だな) 相手の意図を見切ったアルバルクは、彼女を中心に円を描くような形で回避行動を取る。 盾は防御において最適だが、攻撃者自身の視界をも塞ぐという欠点がある。向こうの手を確認するためには、どうしても合間合間に頭を出さなければいけない。 彼は、そこを狙う。 「相変わらず真っすぐ過ぎるぜ、戦法が!」 『アル・カマル』で切り裂かれ、端正な顔が傷だらけだ。だが微塵も怯むことなくイデアは、『グラム』で突き返す。 急所に入らない攻撃に限り彼女は、防御を捨てている。肉を切らせて骨を断つ戦法だ。そうでないと、この海千山千の相手に対し、勝機を掴むなど不可能。 アルバルクの頭部に刃が当たり、滑る。染み出した血は額を彩る。 鋼と鋼がぶつかり、生じる火花。 二人はいったん距離を取った。休むためではなく、最大限の一撃を食わせる隙を窺うために。 切り落とされた髪が吹き過ぎる乾いた風に吹き飛ばされる。 回りにはすでに死体しかない。 ぬるぬるした赤が壁の上を染めている。 「…俺たちで最後のようだな」 「…そうみたいですね」 「なあ、この任務が終わったらどうする気だ?」 「別にどうもしません。より強くなれるよう精進を重ねるだけです。自分の力は…まだ何処にも届いていない…」 「…らしい答えだ」 言うなりアルバルクは前傾姿勢を取り、突っ込んだ。 盾の下から『ズフル』を、突き上げる形で差し込む。狙うは脇の下。 狼の唸り声が、空を割く刃身の声と重なる。 イデアは身を縮め、盾を下げた。 直後ぐずっと脇腹に異物がめり込む。 痛いのではなく熱かった。 アルバルクは目を見開いた。次に彼女が取った行動が予想外だったので。 あろうことか、盾を捨てたのだ。投げ付ける形で。 咄嗟に背後に飛びのいたところ、目の前に黒煙が広がる。狼煙銃だ。 「くそっ!」 文字通り持てる力の全てを振り絞った一撃が、煙を割り襲ってくる。 もはや小細工は通用しない。 そうと悟った彼の体は、自然に動いた。相手の首もとを狙って。 噴水のように勢いよく、赤い飛沫が上がる。 ● 透子はぽつりと呟いた。埋めるもままならぬまま地面に横たえられたボスコイの姿に。 「ボスコイさんって良い人だったんですね。」 ファティマは憔悴した様子で、せやな、と小さく答えるだけ。 光紀は改めて周囲を確認した。 地平の果てまで続いている長い壁。 先ほど向こう側を見たときには、何もない広野が延々と広がっていた。 こちら側にはこの死んだ町並み。 その両方を見下ろしているのは、曇っているのか晴れているのか曖昧な空。 これ以外の空を自分は見た記憶がない――はずだが、なぜか頭に澄んだ青の色が浮かぶ。 式を肩に乗せた透子が、沈鬱に言う。 「…この土地も放棄されてしまったんですね…あたしたち、どこまで後退すればいいんでしょうか。」 「…分からへんな。中央では瘴気の研究がなされとるけど、どれだけ浄化しようとしても、魔の森はすぐ回復して繁茂しよる…焼け石に水や…このままやといずれ地上は全て…」 冬馬が不意に顔を上げた。見通せないほどの遠くから伝わってくる空気の揺れと音を感じ取って。 光紀も『ド・マリニー』が示す異様な数値に気が付いた。 「な、何でしょうか。」 透子は式を飛ばす。 彼女は見た。壁の向こうの空が不気味に赤く染まってくるのを。 腹の底からの突き上げてくる恐怖が、ざわりと産毛を逆立てる。 ファティマが弾かれたように走りだす。 「地下に退避せえ! 退避!」 皆は彼女を見習い、近場の建物に飛び込む。誰に教えられた訳でもないのに地下へ通じる階段を駆け降りて行く。透子の作った明かりを頼りに。 ● 裸で抱き合う少女たちは、睦言を交わし合う。 「愛しているぞ…」 「リンスちゃん…大好き…♪」 互いの肌の温もりを思い出すと同時に、周囲に対する違和感が呼び起こされた。 「なぜこんな殺し合いを…ここはどこじゃ…現実なのか…?」 「なんで殺し合ったりしたんだろ。そもそも、ここどこ?」 改めて考えてみれば、どれもこれも見覚えがないものばかり。あの城壁もこの場所も。 彼女らは無意識のうちに、傍らにそびえる石像を見上げた。 頭のない男は重みに耐えかねながら、真ん丸い荷物を担いでいる。改めて思えばなんともへんてこりんな造形。 「どういう意味の姿じゃろな…ちと理解しかねるのう」 「んー…スイカを運ぶ人の記念碑とか?」 「いや、それは違うと思うぞよリィムナ…まあおかしな意図の像も世の中にないことはないが、そういう色物であれば、これだけ大掛かりにはせんような――」 言いかけてリンスガルトが、はっと目を見開く。 空気に伝わるちりちりした振動をリィムナも感じた。 2人はこぞって外に出る。 黒い光が空一杯に落ちかかってきていた。 ● 片腕を無くしたアルバルクは、事切れ横たわるイデアの隣に腰を下ろす。 一応止血はしたものの、この状態では帰還も難しい…もっとも帰還など、最初から期待されていないのかも知れない。 というか絶対にそうだろう。間を置かずしてこのような無差別攻撃を始めた時点で。 「やれやれ、最後に一服したかったんだが、その暇もねえのかよ」 落ちてきた光が弾けた。 自分の体が泡立ち粉々になった壁と一緒に吹き飛ぶ。それが最後に彼の感じたものの、全てだった。 ● ずん、と足裏に伝わる鈍い轟き。 天井からぱらぱら土くれが落ちてくる。 「奴ら、この一帯焼き払う気かいな!」 「あの、あの、どうすれば!」 「このまま地下道通って、ひとまず脱出せな! 駅があったはずや!」 下って下って下った先に広い空間があった。 待っていたかのようにぱっと周囲が明るくなる。 ドーム型の天井。 見たこともない乗り物。 しかしそれより透子は、そこにある小さな店舗に気をとられた 従業員など一人もおらず商品は散乱したまま。 積み上げられていた――多分瓦版の一種だろうものを手に取れば、絵と思えないほど鮮明な絵が多数載せられている。 『――は――を――することも視野に入れねばならないと――計画を――急ピッチで――』 所々読めない記事の下に地図がある。 一面青く塗り潰された上に、まるっきり見たことのない形が散らばっている。 (…れ…これ、は、これ、は、何…? あたしはこんな儀なんて、一度も見たことがない…ここは一体どこ!?) 混乱を始める彼女に負けず劣らず光紀もまた、膨れ上がってくる疑問を制御出来なくなってきていた。 「…ファティマ君、俺たちはどうして戦っているのだったかな。つまりその、先ほど敵対していたあちら側と。同じ人類だろう」 「そんなん同じ人類としても、目指すところが正反対やからやろ。あたしらは―――の意志に反しようとしてる、向こうは―――の意志に沿おうとしてる。噛み合うわけないねん。あたしらは向こうさんみたいに―――の都合に合わせるのは御免や。それが自然な流れだとか言われても、いっこもそんな気にはなれへんし。大体――」 「…待て。何やら今、一部聞き取れなかったんだが」 冬馬は彼女らの話を耳に、高い天井や壁を見つめていた。どちらものっぺりしているだけで凹凸がなく、照明器具なども一切見当たらない。 (…どうやって明るくしているんだ…?) 不審に思った所、いきなり近くの壁面に映像が浮かび上がった。 見慣れぬ服装の男が表情を殺し、口を動かしている。 『臨時ニュースを申し上げます、たった今入った情報によりますと――にて――が使われた模様です。多数の死傷者が――』 直後、構内にアナウンスが響き渡る。 『悪夢さんストップ。これ以上見せるのちょっとストップ。まずいと思います…あの時のアレそのまんまになり過ぎてる部分がちょいちょいと…ええ…』 次の瞬間、そこにある一切合財が消えた。 ● ダブルベッドの中。 がばっと起き上がったリィムナは同程度の勢いで起き上がってきたリンスガルトと顔を見合わせた。 お互い頬をぺちぺち叩き合い、ようやく安堵の息を吐く。 「…なんじゃリィムナ」 「…リンスちゃんこそ…いやね、なんだかすごく悪い夢を見た感じなの」 「そうか。奇遇じゃな。妾もじゃ…二度寝入りする気にはなれんな」 「あ、それあたしも…そだ、子守唄吹こうか。そしたら頭がすっきりするかも」 「…うむ。そうじゃな。頼もうかの」 アルバルクは頭をかき、野営の寝袋からもそもそはい出てきた。 焚き火の前――今回の依頼同行者である仲間の一人が座っている場所に行く。 「なんだ、交替か。早くないか?」 「いや、どうもいい夢が見れそうもなくてな。時間はちょっと早いが代わるよ」 「そうか、悪いな」 イデアは頭から井戸の水を被り、ぶるぶると払った。硬く澄んだ空には星が出ている。 夢の中であっても負けてしまったのが腹立たしい。 まだ弱さが克服出来ていない証拠だ。そう思うと、いやがおうにも苛立ちが募る。 (自分は…) 強くあらなければ、強くならなければ。二度と奪われないために。 冬馬は朝ぼらけの光を障子の向こうに感じつつ、寝返りを打つ。 (妙な夢だった…) 寝たはずなのにひどく肩がこっている。まるで本当に動き回っていたみたいだ。 頭は重いし気分も悪い。目を閉じればありありと、重苦しい空の色や腹の底を揺すぶる振動が蘇ってくる。 「…もう起きておくか」 昼頃、茶屋。 光紀と透子が額を突き合わせ話をしている。 「どうやら透子君が見たのも俺が見たのと同じものということで、間違い無さそうだな」 「はい。これだけ細部が一致しているとなると…最後の声、隙間女のひとに似てたような気がするんですが…。」 「ああ、そこは俺もそう思った。後でファティマ君にも聞いてみた方が良さそうだ。どこまで覚えているか知らないが」 ぷかりと光紀が煙の輪を浮かべる前で、透子は身をひと揺すりした。 「…どうしたね」 「いえ、考えていたらなんだか空恐ろしくなってきて…あの地図って、一体どこの、いつのものなんでしょう…」 「…さてな」 |


