【黒沙】しゃれこうべ
マスター名:和
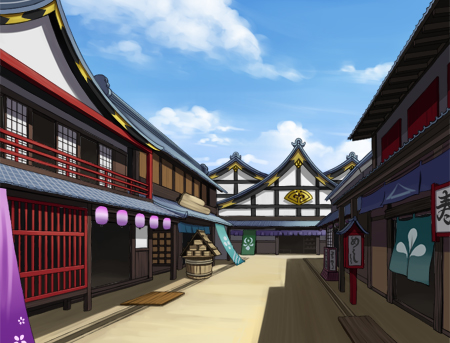
|
|
| ■オープニング本文 ギルド係員の栄は、まず最初に嬉しい報せから読む事にした。 曰く、洗脳の治療を行なっている燦と詩の二人は、病状が極めて良好な為、犬神の出里の一つに移される事になったらしい。 閉鎖された空間は隔離にはもってこいだが、社会生活を学ばなければならない二人にとってはあまり良い環境とは言えないのだ。 単に、友達を作れるようにしてあげたいという思惑もあったのだが。 この報せにほっこりと微笑んだ後、本命を読む。 読み終えるなり机に突っ伏した彼の姿から、それがあまりよろしくないお話である事は誰の目にも明らかだろう。 現在彼が抱えている問題は、ともすれば犬神の里全てを巻き込む大戦に発展しかねない。 犬神側の窓口である薮紫よりの書状によると、ギルドと犬神で敵対している黒沙という街には、先に倒した無骸老と同格の存在が少なくとも後七人居るらしい。 内の二人は薮紫の方で片付けると豪語しているが、五百もの兵を平然と動かす連中だ。 如何に犬神の里とはいえ、里一つで果たして相手しきれるかどうか。 そもそも、ここで下手に犬神が総力戦などしてしまった日には、他所の里もここぞとちょっかいを出してくるに決まっている。 ギルドとしても、ギルドに対し非常に協力的な犬神の里が力を失うのは出来れば避けたい事態だ。 「薮をつついて竜が出た気分ですよ‥‥薮紫さんも、独断で総力戦規模の戦闘を決定出来るはずありませんし。ぜーったいあの里長にどやされて、引かざるをえなくなりますよねぇ」 許せぬ悪を倒すべく動き出しておいて、いざ敵が強いとなると尻込みする無様さに自覚はあれど、戦の規模が大きくなりすぎた時の損害を考えれば、容易く全てを決するわけにもいかないのだ。 あくまでこの戦の主体は犬神の里である。 ギルド全体で動くなんて話になったら、それこそ取らなきゃならない許可の山で、二月は身動き取れなくなるだろう。 その頃にはとうに戦なぞ終わっていよう。 結局の所、栄は与えられている権限の中で戦うしかないのだ。 栄は目の前に置かれた報告書類に目を落とす。 「やるしか‥‥無いですかね。備えはあるでしょうが、ウチの連中なら腕づくで突破出来ると信じます」 書類には黒沙八王の一人、カルバリの所在が記してあった。 ギルド、そして陰殻のシノビが本気になって調査すれば、見つけ出せぬものなぞこの天儀には存在しない。 問題になるのは、発見するまでの時間である。 敵が犬神の規模の大きさに気付き、全力を向けるべく動き出す前に、仕留められるだけ仕留めておけば、後々の展開が楽になるだろう。 「薮紫さん所で二人、こちらで後一人、計四人潰せたとして、まだ半分残っているんですよね。こりゃ相当厳しい話し合いになりそうです」 栄は、既にこの戦争の落とし所を模索し始めていた。 長身の男が部屋の中に居る。 鍛え抜かれたしなやかな肉体を無理に服の中に詰め込んでいるせいか、着物の腕の部分がもこりと盛り上がっている。 彼は、椅子に腰掛けた目の前の女性の髪を、愛おしげにすいてやる。 「あー、うー」 女性は特に逆らうでもなく、心地良さそうにしている。 「‥‥今日、国光から手紙が来た。相変わらず元気そうだったぞ」 「うあー、あぃー」 「そうか、兄からの便りはお前も嬉しいか」 『冬耶、元気でやってるか。一つ良い報せがあってな。遂に俺が頭領として独り立ちする事になったんだ。 正直、不安も無いではないが、大工一筋十五年、根性の見せ所って奴だ、やってやるさ。 そっちはどうだ? 商売の方は上手くいっているか? お市がわがまま言うようだったらどやしてくれて構わんぞ。 冬耶は腕っぷしは確かなんだが、どうにも優しすぎるからな。ここ一番って時はきっちり旦那の器量って奴を見せ付けてやるんだぞ。 仕事も忙しいだろうが、たまにはお市を連れて遊びに来い。俺の子供、とうとう六人目が出来ちまってな、毎晩うるさくてかなわん。 お前等子供がまだなら、うちに来て少し子供ってものを知っておけ。えらい大変だぞこいつは。 お市にもよろしく伝えておいてくれ。ではまたな』 男は手紙を机に置くと、一人呟く。 「‥‥お前からの手紙が来る度、俺は俺の罪を自覚出来る。国光よ、お前が妹を託した男の不甲斐無さはどうだ。お市は既に、俺もお前もわからぬ有様になってしまったぞ‥‥」 女性はただ、椅子に腰掛けたまままっすぐ前を見つめている。 写る景色を、意味あるものとして捉えられぬ瞳で。 男は部屋を出る前に、手にしていた兜を被る。 それは骸骨を模した鉄製の兜で、顔全体をすっぽりと覆い尽くしている。 部屋を出てすぐの所に、一人の男が控えていた。 「若水様が軍を出されました。我々もすぐに動けるよう準備を整えてありますが」 「ふん、若水の尻馬に乗ってやる程こちらは暇ではない。それより騎士を全てこの屋敷に集めておけ」 控えていた男はそれだけでぴんと来たらしい。 「‥‥この屋敷も狙われると?」 「無骸老の隠れ家と比して、ここがより隠密性が高いとは思えんのでな。用心の為だ。それより、灌漑工事の入札はどうなっている?」 「八割方我々で手に出来るかと」 「残りの二割は?」 「相手が氏族崩れの商人でして。これを黙らせるにはそれなりの覚悟が必要かと」 「馬鹿が。それと知られず消せ。家族諸共皆殺しにしてやれば、外の官憲は盗賊を疑う」 男は肩をすくめてみせる。 「今月これで皆殺し三件目ですよ。流石にバレるんじゃないですかね」 骸骨を被った男、カルバリこと冬耶は兜の奥で含み笑う。 「その時はその時だ」 |
| ■参加者一覧 19歳・男・泰 33歳・女・泰 17歳・女・シ 19歳・女・騎 15歳・女・泰 23歳・女・騎 18歳・男・騎 25歳・女・弓 |
| ■リプレイ本文 『八王が一人カルバリ党! 我等は突撃隊、主等は既に包囲されている! 投降せぬ者は、義の旗下天誅仕る!』 そんな大声と共に堂々と正面より討ち入った正面突入組。 入り口側に控えていたらしい二人の騎士がまずこれと相対する。 騎士一、嵩山 薫(ia1747)の蹴りを鎧の肩で弾きつつ、長巻を振り下ろすフェルル=グライフ(ia4572)に盾を突き出しそのまま押し飛ばし、グリムバルド(ib0608)の突き出した十文字槍を引っつかみ逆にグリムバルドを槍ごと引きずり倒す。 騎士二、目にも留まらぬ秋桜(ia2482)の踏み込みをすら見切り、拳打に合わせて拳を突き出し首元を掴み取り、続くレイシア・ティラミス(ib0127)に向け放り投げ、戦の雄叫びを上げる。 更に奥から騎士と巫女が顔を出してくる。 そして最後の一人、壁面の向こうに膨らんだ殺気に薫が飛びのこうとした刹那、壁をぶち破りながら、全身に薄気味悪い色を帯びた男が血走った目で騎士の奥義を振るってくる。 敵方の要となりうる人間を野生の勘で嗅ぎわけ、不意打ちで最強の技をぶちこんだ男は、とても騎士とは思えぬ形相で口元からオーラの煙を吐き溢す。 オーラの直撃をもらってしまった薫は、だがこのままでは済ませぬと三連撃を叩き込み、両者は苦痛を堪えながら睨み合う。 カルバリの秘書兼護衛のシノビは、全力で陽動に引っかかる仲間達を苦々しい目で見ていた。 頭であるカルバリが、黒沙らしいだろうと笑っているので文句も言えないのだが。 「‥‥生粋の黒沙組の考える事はいまだに理解出来ません‥‥」 ちらと後ろを見るシノビ。 「そちらの方も、そう思いませんか」 ぱらぱらと舞い落ちるのは屋根瓦やら木材の破片。 その豪腕で屋根をぶち破って侵入した朱鳳院 龍影(ib3148)は、豊満だのという単語を軽く突き抜けるような胸囲を誇示しつつ答える。 「そも理解する気もない」 ひらりと中に着地した鬼灯 恵那(ia6686)は、くすくすと忍び笑いを漏らす。 「こんばんはっ! 首取りに来たよ王様♪」 シノビが目を見張り、カルバリもまた僅かにだが身を硬くする。 「‥‥居るじゃないですか、敵にも黒沙が」 「いや、コイツは多分一般狂人だろ。独特の生臭さがない」 「一般狂人て、種族か何かですかそれ」 酒々井 統真(ia0893)は腰に両手を当てながらとんとんと床を足で叩く。 「お前、運が良いよ」 「何?」 「俺に負けても無骸老以下だとは言われないからな。良かったじゃねえか、地獄で肩身の狭い思いする事もないぜ」 騎士達が纏う強固な鎧はさながら城壁のようで、放たれる剣撃は攻城槌のように激しかった。 その上巫女の援護まであるというのだから、その厳しさがわかろう。 秋桜の抱いた危機感は、彼女を普段なら決して踏み込まぬ危険領域へと誘う。 敵騎士は皆好き勝手動いているように見えて、その実後方の巫女を守れるように位置している。 これを、敵騎士を打倒する事なくすり抜けようというのだ。 咄嗟に踏み込みを止めたのは、敵騎士の大剣が鼻づらをかすめたせいだ。 返しの一撃が来る前に、左拳の牽制打を騎士へ。 体を入れて殴るため、見た目より遙かに伸びる拳を、委細構わず額で止める敵騎士。 寸前、握った拳を開いて手の甲と指で顔をはたき、視界と動きを一瞬だが封じる。 その場で低くしゃがみこみ、横っ飛びに距離を取る。 これで、敵騎士の視野からは完全に外れたはず。 右拳を脇腹に叩き込みつつ、背後をすり抜け左側面へ。 敵騎士が脇腹の痛みに側面を向いた時にはその背後に位置しているのだから、秋桜の姿を敵騎士は捉えられぬままのはず。 敵騎士の後頭部目掛け、秋桜の回し蹴りが飛ぶ。 そんな見えぬ蹴りにすら、殺気のみで反応してこそ一流。 しゃがみ避けながら振り返り様に一閃が走るが、ここで初めて騎士は動揺する。 秋桜が放ったのは回し蹴りを放つという殺気のみ。 当の本人は更に奥、殺気にて騎士へと牽制するなり、敵巫女へと踏み込んでいたのだ。 薫は眼前の騎士につきっきりとなっていた。 動きは薫が上だが、鎧の厚さとタフさは比べようもない。 薫は右胴、左足脛、右肩から後背にかけて、大きな斬り傷を負っており、何より、最初の奇襲の一撃のせいで全身が痺れるような衝撃がまだ残っている。 それでも下手に時間はかけられぬと、最も気を練りやすい自然体にて敵騎士を見据える。 静かに、力強く、体中を流れる気脈を活性化させる。 「破軍参式・極神――この先はまだ考えていないの」 頑強な鎧は健在でありながら、敵騎士は紫色になった顔で、闘志のみをむき出しにぎらぎらとした目を光らせる。 「この一撃に耐えきったなら、貴方に名前を付けさせてあげるわ」 敵騎士は動けない。直前に、薫が呼吸を止めての超近接乱打戦を挑み、彼は酸欠状態に陥っていたのだ。 当然薫も少なからぬ消耗を強いられていたが、僅かに、地力の差で薫が勝っていた。 薫が鋭さのみを追求した左拳を打ち込むと、見た目の軽さからは想像出来ぬ重苦しい音と共に、大量の吐血が騎士の周囲に撒き散らされる。 「ま、無理だとは思ったけど。騎士苛めは我が泰拳士生命の糧。受防爆発しろってね」 体内が炸裂したような吐血を吐き出し終え騎士は倒れたが、薫はすぐに次の敵へと動く。 全てを出し尽くすつもりで戦わなければ、被害者を出す前に決着をつける事は難しいだろうから。 グリムバルドは体を沈め、振り下ろされる大剣を頭上に掲げた槍で受け止める。 絶対に引いてやるものかと腹をくくっていなければ、それだけで弾き飛ばされる程の剛剣である。 グリムバルドの足元、土間の床がべこりとへこんだのは、衝撃に床が耐えかねたせいであろう。 同時に、もう一人の騎士が側面より斬りかかってくる。 この一撃はグリムバルドの足を止める為のもの。奇声を上げるわ、デタラメな勢いで押し切りにかかるわする狂人の分際で、実に見事な連携を見せてくる。 全身を捻り、上から押さえつけてくる大剣を弾きつつ、後ろ回し蹴りを放つ。 全身を伸ばせば、辛うじてこの男の片手剣の間合いより長い。 ぎりぎりで軌道を変え、足を狙って来たのには肝を冷やしたが、何とか先にこちらの蹴りが当たってくれた。 すぐ側で大きな足音。 ぞくりと背筋が冷えそちらに目をやると、大剣を用いる男は既に至近に踏み込みこれを振りかぶっていた。 『戻しはええよおっさん!』 体を伸ばしているせいで、これに対応はしきれぬ。 そこでグリムバルドは、槍を手元に引き寄せ、後ろ足を大きく引きにかかる。 防御を考えぬ動きは、次に起こる事がわかっていたからだ。 大剣と真っ向からぶつかって派手に壁の中に叩き込まれていたレイシアが、助走も無しに大きく飛び上がり大剣男に迫っていたのだ。 飛び蹴りを仰け反りかわす事しか出来ぬ大剣男に、着地するなり挑発するように告げる。 「同じ騎士の技なら当然避けれるんでしょ?」 更に真下から垂直に足を振り上げ顎を蹴り上げる。 完全に攻撃態勢を崩された大剣男は、続くグリムバルドの疾風のような突きをかわす事は出来なかった。 更にグリムバルドと交差するように動いたレイシアは、片手剣男の突きを鎧の肩で弾きつつ腰溜めにフランベルジュを突きこむ。 片手剣男は、レイシアの突きを同じく鎧の表面で逸らし、再び攻撃を仕掛けてくる。 息をつく暇もないとはこの事だ。 肩で息をする余裕すら無いレイシアとグリムバルドは、歯を食いしばってフランベルジュを、十文字槍を振るい続ける。 フェルルの視界の端に霞がかかって見えるようになったのは、何時からだろうか。 敵騎士がどんな表情をしてるのかもわからぬ程疲弊したフェルルは、既に思考能力すら失われ惰性で長巻を突き出す。 脳裏を占めるのは、苦しい、の一言のみ。 歴戦と言っても過言ではないフェルルが、体力が底をつく程に打ち込み続けても、敵騎士は尚健在のまま。 もう打ち込んでるんだか撫でてるんだかわからぬ勢いで長巻を振るうと、狙いを大きく外れて敵騎士の腕に当たる。 間が悪かった。 ちょうど敵騎士が踏み込もうとしていた所に当たってしまい、逆に勢いに負けて長巻ごと後ろにたたらを踏む。 伸び来る敵の剣はフェルルの胸に当たり、その重心を更に崩す。 ぺたんと、しりもちをついてしまった。 疲労困憊なんて言葉では表せぬ程に疲弊していたフェルル。 もう、足に力なんて入ってくれない。 扱いなれた長巻すら、持ち上げる事も出来そうにない。 絶望的な思いを抱えながら、フェルルは必死に思い出す。 守りたい者の顔を。 『動いて、動いて、動いて、お願い動いてっ』 ぶるぶると全身を震わせながら体を起こしかけ、気付いた。 敵騎士の足元もまた同様に小刻みに揺れていることを。鋭い剣先を誇る敵騎士の突きを受けて尚怪我らしい怪我を負っていない事を。 『‥‥そっか。なら、後は‥‥気持ちの勝負っ!』 敵騎士も苦しいのだ。それでも剣を振るう意志の強さが敵にもあると思うが、この点だけは決して譲れないと足を引きずりながらフェルルは立ち上がる。 恵那は一挙動で懐より丸薬を取り出し口に放り込む。 手先の感覚が失われ、足も他人のそれであるようだ。 だが、動く。 「まだまだ、こんな半端なとこじゃやめられないよねぇ」 カルバリを相手にする時とは違う、剣先を後ろに向けた構えのまま走る。 信じられぬ踏み込みの速さで恵那の眼前へと至る敵シノビに、半身を晒したままの体勢で連撃を浴びる。 二つ響いた音は、硬い何かで刃を弾く音。 切っ先の速度では追いつかぬと見た恵那は、剣先ではなく柄の裏、柄頭と呼ばれる極めて狭い部位を用いてシノビの剣を防いだのだ。 そして待ちに待った横薙ぎの一閃。 シノビはここで初めて、余裕の欠片も無いありったけを用いた回避を行なう。 「いくぞ!」 カルバリと拳を交えながら好機を待ち続けていた統真の声が響く。 右の足に練気が集い一歩の踏み込みと共に開放すると、部屋中が桜に染まる。 統真を中心に吹き荒れる薄紅の嵐はシノビを、そして八王カルバリをすら巻き込み壁際まで跳ね飛ばす。 恐るべき統真の一撃、荒れ狂う衝撃はまるで噴炎のごとく、一瞬で部屋中を駆け巡ったのだ。 恵那は盾にしていた執務机を押しのける。 「部屋中何処に逃げてもダメとか、合図の意味ないんじゃないかな?」 統真は悪びれもせず笑って言った。 「悪ぃ、勢い余った」 と、衝撃の嵐も覚めやらぬ中、龍影が動く。 壁際に叩き付けられた衝撃で、呼吸の止まったシノビの首元を掴むとそのまま壁に再度叩き付ける。 絞め殺すのではない、万力のごとき力で捻きるつもりなのだ。 「ようやく、捕まえたのじゃ」 片腕一本での所業ながら、指は喉元に食い込み、呼吸を奪いシノビの動き全てを封じる。 しかし、彼もまたカルバリ貴下にあって護衛を任される程の男。 口元に含んでいた針を龍影の目めがけて打ち出すと、これを避けざるをえない。 僅かに緩んだ隙をついて窮地を脱する。 龍影の全身には無数の斬り傷がある。全てこのシノビとの対戦でつけられたものだ。 「‥‥ならば、再び捕まえるまでじゃ」 それが如何に至難であるかを龍影も理解しているが、心は決して折れてはいなかった。 レイシアのフランベルジュと騎士の大剣が絡み合うが、翻す手首と肘の入れ方のみでレイシアはフランベルジュを弾き飛ばされてしまう。 それは考えて動いた訳ではない。 レイシアは剣に欠片の未練も見せぬまま、騎士の顔面へと掴みかかる。 疲労に萎えかける足で大地を蹴り、顔を手で抑えたまま膝を胸板の上へ乗せ、騎士へとのしかかる。 騎士は大剣を手放すのが一瞬遅れたせいで無防備となり、後頭部を大地に叩き付けられてしまった。 ほぼ同時に、グリムバルドの片手で目一杯伸ばした十文字槍がもう一人の騎士を貫く。 敵もまた槍を振り上げ、必殺の一撃を放たんとしていたギリギリの所であった。 槍を突き出した姿勢のまま前のめりに突っ伏すグリムバルド。 「あ、あっぶね‥‥こっちはもう指一本だって動かせねえぞ」 飛び掛った勢いそのままにひっくり返っているレイシアは、怪我と疲労からか意識が若干怪しい状態で、何事かを呟いている。 薫は少し前にケリをつけぶっ倒れたままのフェルルに問う。 「どう? 動けそう?」 目に光は戻っているが、少しほうけた顔のままフェルルはこちらに顔を向けた。 「‥‥今、私の名前呼びました?」 これは後詰めが来るまでどうしようもないなと、秋桜は肩をすくめるのだった。 付かず離れずを繰り返し龍影を翻弄し続けるシノビは、青白く変わっていく彼女の顔を見て、仕留め時の到来を知る。 出血が多すぎるのだ。 シノビは数多の牽制を加えた上で、それまで一度も利用しなかった龍影の死角、大きすぎる胸のせいで出来る直下の空間へと潜り込む。 低い姿勢より鳩尾を貫くべく突きかかる刃が、龍影に届く事はなかった。 「何故じゃろうな、私を狙うシノビは決まって最後にそこに来る。おぬしもまた、その誘惑に勝てなんだか」 見えぬ場所に二本の剣を突き刺しながら、龍影はようやく捉えた敵にそう呟いた。 カルバリの執念は凄まじかった。 大きく足を開いて剣撃を弾いた恵那も、膝が崩れぬようにするので精一杯。 代わりに打ち込まれる統真の拳、これに合わせて、カルバリは神速の戻しからの交差法を。 手では止められない。ならばと統真は脇の下にカルバリの刀を挟み腕全体で無理矢理押さえ込む。 残る腕でトドメを刺したいが、それすら適わぬ程の剛力でカルバリは統真を脇の下から真っ二つにかかる。 じわりと進む刃。 麻痺しているせいでまるで感覚の無い腕を、きっと大丈夫だろと恵那は無造作に振るう。 首元に一筋。 斬りおとす所か薄肉半枚分程の傷しかつけられなかったが、それで充分だった。 「最高だったよ王様。八王を斬った人は違うねぇ。うふふ、あはは♪」 噴水の様に噴出す血潮が、カルバリの残った気力を根こそぎ奪い、遂に、八王カルバリは倒れるのだった。 「‥‥ところでさー。小間使いの人もみんな逃げたよね。なんかまだ人がいる感じがするんだけど」 怪我も疲労もまるで感じさせぬ暢気な口調で恵那がそう漏らす。 龍影がその気配に気付き振り向くと、何時の間に現れたのか、一人の女性がそこに居た。 「あー、あー、あー」 彼女は倒れるカルバリの側に行き、腕を取って持ち上げる。 その手が髪に触れた所で、女の力が持たないのか腕は床に落ちる。 誰がどう声をかけても、後詰めの回収部隊が来た時も、女は、何度も何度もそうし続けていた。 |


