吉凶、三つ
マスター名:風華弓弦
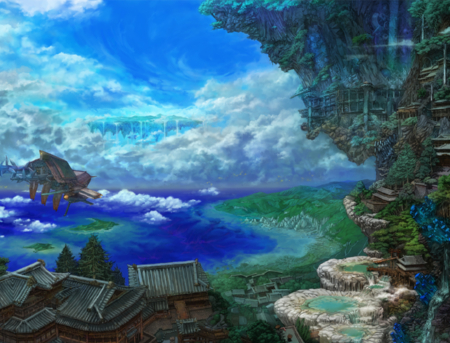
|
|
| ■オープニング本文 ●前触れなき来訪 神楽の都の一角にある、『開拓者長屋』。 「開拓者が多く住む」という以外は何の変哲もない長屋を身なりの良い一人のサムライが訪れたのは、肌寒さの残る三月半ばの午後の事。 「随分と……随分なところに住んでいるのだな」 「てめぇっ。ナンでこんなところにいるんだ、元重ッ!?」 怪訝そうに長屋の風景を見回す客人に、狼狽したゼロが叫んだ。 神楽の都から北へ徒歩で三〜四日の位置にある、武天国の数多ヶ原。領地は小さいが古くから彼の地を治める氏族が「天見」であり、現当主の名を基時(もととき)という。 開拓者長屋に住むゼロを訊ねたのは、天見家の三男、天見元重(あまみ・もとしげ)だった。 「わざわざ、てめぇが神楽まで出てくるってのは……よっぽどの話か?」 普段、開拓者の繋ぎをしているのは三枝伊之助(さえぐさ・いのすけ)というサムライの少年だ。ゼロを親の仇として仇討ちしようとしていたが「お流れ」となり、それ以後は開拓者との縁がある者として天見家当主より世話役を仰せつかっている。 「三枝には、いささか荷の重い話だからな。直に俺の口から開拓者へ伝えた方がよかろうと、足を運んだ次第だ」 「そんな、面倒くさい話なのか」 言葉を切って出された茶を口へ運ぶ元重に、訝しげなゼロが眉根を寄せた。 血の繋がりで言えば、元重はゼロのすぐ下の異母弟となる。だが出奔したゼロは元の名を捨て、家も過去も全てを捨てて、開拓者となった。また天見家も彼の存在を「氏族始まって以来の恥」とし、「いなかったもの」としている。故にゼロは天見家と必要以上に関わらぬよう振る舞い、天見家もまた対外的にはゼロを一介の開拓者として扱っていた。 「ここで話すのも、はばかれる。開拓者ギルドならば、込み入った話も出来るだろうから……場所を移していいか」 「いいけどよ。ナンかぞろぞろ付いてきても、知らねぇぜ?」 「問題ない。それが俺が顔を知っている者なら、好都合だ」 腰を落ち着けたばかりの元重だったが、茶を干すとゼロに案内されて開拓者長屋を後にした。 ●吉報、二つ 「実は、吉報凶報の二つがあってな。まず今年の初め、弟の元信が無事に元服を迎えた」 開拓者ギルドに都合してもらった一室で、元重はゼロを始めとする顔を揃えた者達に告げた。 天見家四男の元信(もとのぶ)も十五歳となり、正式に氏族の後継者として名を連ねる事となったという。 「元服の儀自体は年初に済ませたが、当主より世話になった開拓者らにも祝いの席に顔を出して欲しいという希望があってな。だが北面が騒がしかったため、今まで時機を見ていたのだ」 「基時の体調を考えれば今頃の方が暖かいし、負担は軽いか……」 ぽつと呟くゼロに、真剣な表情で元重も首肯する。 「当家の当主は身体が弱く、出来る限りの負担は避けたいのもあった。それから、吉報がもう一つ」 言葉を切った元重にゼロが向けた視線は、焦らすなと言わんばかりに催促をしていた。 待ちかねる視線に何故か元重は気が進まぬ風に眉根を寄せ、こほんと咳払いをしてから先を続ける。 「基時に、世継ぎが出来た」 「……は?」 今度は、きょとんとしてゼロが呆気に取られた。 「兄上……じゃあねぇ。天見家当主はまだ、妻を娶って(めとって)なかったんじゃ?」 「実は「お手つき」の侍女がいて、な。予定より早く男児が産まれたが難産だったため、母親である侍女は子を産んですぐに死んだのだ。今は先代の後妻である千代殿が、亡くなった母親の代わりに世話をしている」 「そう、か。それは天見の殿も、辛い事であったろう」 視線を落とし、肩を落としてゼロは項垂れた。 当主の身の回りの世話をする侍女が「手付き」となるのは、武家において特に珍しい事ではない。生まれた子が男児なら、子の母は側室や後妻となる。 世継ぎが出来たのは喜ぶべきだが、妻となる相手を失った基時は辛かろうと、ゼロは目を伏せた。 「それが凶報か」 「そんなところだ。ともあれ世継ぎの将来を祈り、出来れば開拓者から名を一文字もらいたいというのが、天見基時の意向だ」 嫡子の名は父の基時より「基」の一文字を取り、「基○」となる。この「○」部分の名づけを開拓者に委ねる……という事だった。 そこまで話した元重は、不意に何かを思い出した顔で舌打ちをした。 「いかん、妹の津々に頼まれた買い物を忘れていた。嫡子の健康を祈って、守り袋をと言われていたのだが」 頼まれてくれるかと元重が視線を向け、「仕方ねぇな」と不承不承の体でゼロが立ち上がる。 「今じゃなきゃ、駄目なのか。というか、俺が勝手に買っていいのか?」 「構わぬ。津々の話では、今日に買うと験が良いそうだ。開拓者が知る神楽の社なら、霊験もあらたかであろう」 「ナンか……無駄に大任を背負った気分だぜ。ちぃと待ってろよ」 部屋を出るゼロの背を見送った開拓者達も、話は終わりかと三々五々に席を立ち。 そのうちの顔を知る者達を、神妙な表情で元重が呼び止めた。 ●凶報、一つ 「まず最初に。今からするのは、当家でも限られたものしか知らぬ『裏の話』。貴殿らの胸の内に留め、誰にも口外せぬよう願いたい。それが出来ぬのであれば、席を外してもらおう」 話す事に気が乗らないのか、どこか不遜な口調で元重は居並ぶ開拓者へ断りを入れた。 そして開拓者それぞれの動向を見守った末、浮かぬ表情で先を続ける。 「実は、先ほどの世継ぎの話だが。本当は基時の子ではなく、千代が産んだ子なのだ。それを隠すため、表立っては先の話……基時に世継ぎができたと触れている」 重い口調の元重が語った『裏の話』は、こうだった――。 千代の懐妊が判ったのは、今年に入ってすぐの頃。 正気でない千代は、相手を詰問されても「これは『我が殿』の子」と繰り返すのみだった。千代が言う『我が殿』とは、先代当主……基時や元重達の父、天見基将(あまみ・もとまさ)の事なのだが、既に故人となって久しく、主張と大幅に食い違う。 医師の見立てより、昨年にあった謀反騒ぎの頃に元重の側近だった鷹取左門(たかとり・さもん)との関わりが疑われるも、牢にいる左門本人はこれを否定する。 残る可能性は限られたが当主の基時は「それ以上の追求は子の為にならぬ」とし、関わった者達全てに「この子は基時の嫡子とす。以後、一切口外無用」を命じた。 ただし、もし何らかの「不測の事態」が起きた場合に備え。過去に関わりがあり、将来に助けを求めるやもしれぬ開拓者へは内密に伝えておくべきとして、元重を寄越した次第だった。 「当主の言うとおり、大事なのは「子の父が誰か」という論議ではない。だからこの話を、ゼロ……あの開拓者へ天見家から伝える気もない。あいつの耳に入れるか否かは、そちらで相談してくれ。そして親の件とは別に、天見の世継ぎの将来を祝ってくれると有難い」 そう告げて、静かに一同へ頭を下げた。 |
| ■参加者一覧 23歳・男・陰 20歳・男・泰 35歳・男・サ  七神蒼牙(ia1430)
七神蒼牙(ia1430)28歳・男・サ 22歳・男・シ 21歳・女・巫  シア(ib1085)
シア(ib1085)17歳・女・ジ 15歳・女・巫 |
| ■リプレイ本文 ●祝う一文字 「子の名付け……でやすよね。なんだか恐れ多いのですけど、折角の機会ですので参りやした」 天見基時に目通りをした以心 伝助(ia9077)は、傷跡がある頬を掻く。 「静雪・奏と言います。この度はおめでとうございます」 初対面の名乗りをした静雪・奏(ia1042)は祝いを述べ、神妙に言葉を続けた。 「名は『基幸』を。世継ぎの赤子に、幸多き様に」 「あっしからは『基船』っす。正しき航路を仲間と共に進み、嵐の壁をも越えられる……そんな強さを持った御子に、なりますように」 いつになく緊張気味の伝助も、悩んだ末の名を挙げた。 「俺から贈る名は、『基清』だな。理由は好きに解釈してくれ」 煙管片手に鬼灯 仄(ia1257)は、いささか荒っぽく。口に出せぬが、裏にアヤカシ、あるいは『無名衆』――大妖『無貌餓衣』の名代絡んでいると踏んでいた。 (当主が不測の事態を危ぶむように、何かあれば災いの渦中に据えられるだろうからな) それ故、災いや邪を退けられるよう「清」の一文字を……そんな心持ちを仄は伏せておく。 「う〜……けろりーなは『基宗』を提案ですの」 次々と名が出る間もケロリーナ(ib2037)は悩んでいたが、おずおずと案を出した。 「天儀の辞書では『もと』は物事の礎で、『むね』は主で中心でしたの。家の中心となって盛り立ててくれるコトを願って、考えてみましたの」 そして大役を終えたかの如く、ほっと胸を撫で下ろす。 「えへへ〜♪ あまたがはら、幸せいっぱいになるといいな〜」 「そうですね。平和を愛し、何事も公平に判断する子に育つよう、私は『基平』という名を考えたのです」 楽しそうなケロリーナにリーディア(ia9818)も頷き、考えてきた名を明かした。 「被ったが、俺も『基幸』か『基平』がいいんじゃないかと」 由来は言わず七神蒼牙(ia1430)が付け加え、残るシア(ib1085)と有栖川 那由多(ia0923)は辞退する。 「ゼロさんは?」 「俺も考えてねぇぜ」 問うリーディアに、最下座のゼロがむすりと答えた。 「赤ちゃん……ゼロおじさまとリーディアおねえさまは〜?」 目を輝かせたケロリーナが訊ねれば、「それは」とリーディアは頬を赤らめ。 「ゼロさん。ご自分の御子が出来た時には、ちゃんと考えて下さいやしよ」 「伝、てめぇっ」 半分からかう伝助に、全力でゼロが狼狽する。 「変わらず仲睦まじい事で、安堵したよ」 やり取りを見守る基時の小声に、黙って元重は頭を下げた。 「怪我したって聞いてたが、もう大丈夫そう……か?」 「応よ。怪我する暇はねぇからな」 宴までの合間、具合を聞く蒼牙にゼロがけろりと笑い、その腕を那由多が引いた。 「宴終わったら、ちっとツラ貸せ! ……後で待ってる、から」 即座に踵を返す那由多を不思議顔でゼロは見送り、傍らのリーディアが耳打ちする。 「声無滝の庵に行きたいのです。大事な話があって」 (千代様の子。もしもの可能性を考えても……子の事を思うと、不思議なほどその子の幸せを願ってしまいます。だからきっと、私は大丈夫) 騒ぐ胸を確かめる彼女の頭を、「了解した」と大きな手が撫でた。 「短い間の事でも『隠し事』なんて、あいつの前で出来る訳ねぇだろっ」 苛立ちを隠せず廊下を歩く那由多は、その先に伝助と三枝伊之助を見つけた。 「何かあったのか?」 「鷹取の話をしていやした」 訊ねる那由多に伝助が答え、伊之助へ目をやる。 「以前、問われた返事の反応とか。直に会えれば……先日の辻斬りの件や、執拗に『彼』を狙う理由が聞きたいっすけど」 「それが。相変わらず、口をつぐんだままで」 バツが悪そうな伊之助に、伝助も苦笑した。 「ま、答えは余り期待しちゃいやせんから」 「伊之助、千代さんへ祝いの天儀酒を渡してもらえる、か? 元信の母親だし、元服の祝いに」 「うん。あっ、承知致しました。俺は奥へ行けないので直接は無理ですが」 那由多の頼みを、かしこまって伊之助が預かる。 「大丈夫っすか、那由多さん」 「俺……あいつには嘘が言えねぇ。きっと苦い顔しちまうし、絶対に隠し果せないから」 「あっしも気持ちは同じっすよ。そろそろ行きやしょう」 沈んだ那由多を伝助が気遣い、二人は大広間へ向かった。 ●祝宴 「此度は元信様の元服と嫡子の誕生を祝う席、無礼講にて候。開拓者殿には物足りぬかもしれぬが大いに飲み、楽しまれよ」 並んだ酒と料理を前に家老が寿ぎ、祝いの宴が始まった。 大広間の最上座に基時と元信が座し、脇の布団に寝かせた赤子を津々がみている。一段下がって並ぶ家臣は老齢と年若い者が多く、その下座に開拓者が座った。 「騒乱の影響、か」 国を守る要となる中堅が抜け落ちた家臣の顔ぶれに、苦く呟いた仄が酒杯を傾ける。 そんな仄より下座に、指輪に刻んだのと同じ紋『丸に剣三つ桃』の直垂を着たゼロがリーディアと並んでいた。あえて正装で臨む事で、筋を通したとも言える。 「ゼロおじさまの子供の頃の事、聞けないですの〜?」 「ゼロさんは天見家の人ではないので、ちょっと無理ですね」 残念そうなケロリーナをリーディアが宥め、ぐっと平静を装うゼロがフケないか気にかけていた。 「ま、美味しく、大いに呑ませて貰おう。元信殿は初めましてだったかな? 元服おめでとう。これからも精進して兄君たちを助けられる人物になってくれ……って、こんな真面目な話、柄じゃねぇなぁ」 杯を掲げた蒼牙が元信へ声をかけ、からからと笑う。 「にしても、今日は随分と大人しく飲んでるんだな」 城町の住人を避難させる際、花魁道中よろしく遊女らを連れて来たのを蒼牙は思い出しながら仄を冷やかした。 「たまにはこういうのも、いいだろう。芸妓も遊女も無しで、少々華に欠けるとは思うがな」 からりと笑った仄は腰を上げ、澄酒「清和」を元信の前へ置く。 「さて、元服祝いの品には北面での戦場の酒を献上する。良き刺激になれば、な」 内心、ガキには早すぎる酒だとは思いつつ、大人しい少年の気付けにと。 「あっしからの祝いも酒ですが、お納め下さいやし」 祝いの言葉と共に、伝助もまた澄酒「清和」を並べた。 「けろりーなは長脇差「一文字」が、祝いのお品ですの〜」 ワンピースドレス「ブラック・プリンセス」の裾を摘み、軽くお膝を曲げて優雅に挨拶をしたケロリーナが、名工の手による逸品を捧げ持つ。 「元信おにいさま、大人になるですのね。大人いいな〜」 「酒も刀も、自分には過ぎた祝いの品な気もしますが……お気持ち、有難く頂戴致します」 緊張した面持ちの元信が一礼し、席へ戻ろうとしたケロリーナを基時が「ちょうど良い」と呼び止めた。 「先に開拓者より妙案を得て、嫡子の名は『基宗』と相成った。名付けの親はこのケロリーナ殿だ」 「おぉ、この少女が」 「良き名に御座います」 一瞬ざわついた空気は祝いの言葉に変わり、渦中のケロリーナは照れたようにもじもじとする。 「祝いの守りだ、受け取ってもらいたい」 ゼロに頼んだ物だろう。健康を願う赤い蛙の根付け守り二個のうち一つを元重がケロリーナへ手渡し、残る一つを基宗の枕元へ置いた。 「おめでとうございます。お二人に、精霊のご加護があるようにと祈りを込めました」 我が事のように嬉しそうなリーディアが、元信にモフテラスのお守り、基宗へはもふらのぬいぐるみをそれぞれ渡す。 「元服、おめでとな。これで元信ももう大人だ。兄さんや家の皆を支えてやれるよう、頑張れよ……お前の兄さん達は、“皆”、本当に立派な人だから。背を見ていれば、お前も立派になれるさ」 元信と向き合った那由多は、古神書と羽ペンを少年の前に置く。 「これには祝福の言葉が一杯詰ってる。辛い時はさ、これ読んで、今日の皆の嬉しそうな顔、思い出せよ」 「はい。肝に銘じ、一日も早くお屋形様の支えとなるよう精進致します」 元信の返事に頷き、それから那由多は基時へ向き直った。 「その、基宗を……抱かせてもらって、いいですか?」 「勿論だ。津々」 言われた津々はそっと眠る赤子を抱き上げ、まだ座らぬ首に注意しつつ預ける。くしゃくしゃの赤ら顔に握った小さな手、その温かさと重さを那由多はじっと確かめた。 「良い名を貰ったんだから、幸せに育てよ」 そんな祝い一色の雰囲気の陰で、そっとシアは元重に近寄る。 「どうか……基宗に『顔無』の影が近づかないよう、注意して。以前に鷹取が語った目的、当主の寿命を削り、貴方を排除しようとした……その企みの仕上げが嫡子の誕生だとすれば、内からこの地を蝕む気かもしれないから」 懸念を伝え、ふわりと衣を翻して宴の中央へ進み出た。 残した元重の性格を失念し、伏した面の眼光が鋭さを増した事に気付かぬまま。 「この目出度き席に、祝いの舞をお納め致したく」 シアの口上に奏も横笛を手に取り、奏でる笛の調べに合わせ、ジプシーの舞いを披露する。 華やかで穏やかな時は、ゆるゆると過ぎていった。 ●星影に寄りて 「今夜は新月か」 宴の後。茶を手に夜空を眺める奏だが、肌寒い夜気に障子を閉じる。 「今頃は皆、ゼロと話をしている頃かな」 「元重おじさまから聞いたお話は……けろりーなも、びっくりしましたの」 その際、驚きのあまりに落としたかえるのぬいぐるみをケロリーナがぎゅっと抱いた。温かい甘酒を置く奏は天見一族と面識がなく、『裏の話』を知らない。 「ケロリーナちゃんは、一緒に行かなくて良かったのかい?」 「きっと、子供を厄介ごとに巻き込みたくないって……ゼロおじさまなら、言いそうですの。ゼロおじさまって、そゆ優しさあるからぁ」 こくと頷いたケロリーナは、甘酒の湯飲みを取った。 「ゼロさんを信じて、話したい人が多いようだけど……そこまで信じた上で託されている事までが重荷にならなければいいわね」 シアは嘆息し、懸念を茶と共に飲み下す。 「けろりーなも、あまたがはらのために力になりたいですのっ!」 ぐっと拳を握ったケロリーナは今日の事を絵にしようと絵筆を取り、熱心な様子を奏が見守っていた。 「待てよ、ゼロ!」 夜に消えた親友の背へ、那由多が叫ぶ。 話の進める程にゼロは表情を失い、全てを聞くと無言で庵を飛び出した。 「ゼロさん、滝の方へ向かったみたいっす」 「ありがとうございます」 耳を澄ませた伝助の助言にカンテラへ火を移したリーディアが礼を告げ、その間に『人魂』の式を那由多が打つ。 日の暮れた山道へ駆ける二人を追うべく、蒼牙も腰を浮かせたが。 「止めとけ。大勢でゾロゾロ行っても、しょうがねぇだろ」 離れて様子を見ていた仄が、それを制した。少し寒そうな様子に伝助は庵にあった徳利の酒をぐい飲みへ注ぎ、二人へ回す。 「お二人に任せて大丈夫と思いやす」 「それはそうだが」 承服しかねる感の蒼牙だが、渋々と胡坐を組んだ。 「赤子に罪は無い……出生の裏にどんな陰謀が隠されてても、俺はゼロを助ける。それはコレと関係ない他の事だろうと生涯変わらねぇし、変える気もねぇけどな」 「赤子か……それが、よからぬ事の引き鉄にならなきゃいいが」 呟いて、仄は酒を口へ運ぶ。 「そうっすね。この話が本当であれば、いずれまた嵐は起きる。先日の一件で、もし真実を早めに知れたなら……と思い知らされやしたし」 故に、話すならば今と伝助も判じていた。人目につかぬよう、同行する者が多ければ真っ先に辞する気だった伝助は、屋敷に残った三人に感謝する。 「ま、もっと早く話せとか愚痴らなかっただけ、上等だろ」 「俺も、あいつに隠し事なんてしたくねぇからな」 からりと笑った仄は口惜しげな蒼牙へ酌をし、友人達を待ちながら伝助も過ぎぬ程度に酒を含んだ。 「見つけた。あいつ、滝壷の傍に……」 式の目も借りて所在を探し当てた二人は暗い山道を急ぎ、やがて佇む姿を見つける。 「ゼロさん!」 名を呼ぶも滝の轟音にかき消され、駆け寄ったリーディアが立ち尽くす背を抱きしめた。振り返ったゼロは二人の姿にくしゃりと顔を歪ませ、すまねぇ――そう唇が動く。 「お前……泣いてた、のか」 滝から離れながら、顔を拭う仕草に那由多が気付いた。 「落涙は滝が流し、嗚咽は滝音が消す。人前で慟哭すれば家臣や民はうろたえ、付け入る隙となる故、天見の男はここで嘆く。未だ抜けない、俺も馬鹿だが」 「ごめんな」 那由多は沈痛な面持ちで、静かに詫びる。 「俺、散々お前に「話せ」「頼れ」「抱え込むな」って言った癖に……こんな事しちまって……悪い」 「気にするな。でも……俺は、裏切っちまったのかな」 「私も『子の父が誰か』は重要ではなく、『子の未来』が大事だと思いますよ」 打ちひしがれた一言にリーディアは頭を振り、強く握った拳を両手で包むとゼロを見つめて念を押した。 「答えの出ない問題ですから、悩むのは構いません。けれどどうか一人で悩まず……私や、皆さんに打ち明けてほしいのです。そうして気持ちをさらけ出して……改めて、あの子の幸せを願えたらって思うのです」 祈るように目を伏せて、言葉を切り。 「私はね? ゼロさんではないと思っているのですよ」 「え?」 男二人が揃って驚いた顔をすれば、明かしたリーディアはくすと微笑む。 「半分以上、勘ですけど。でも……女の勘を信じてみるのも、よくないです?」 「ありがと、な」 短く礼を言うゼロは大きく息を吐き、おもむろに口を開いた。 「俺の母は、茶屋の看板娘だったんだぜ」 「……ゼロ?」 滅多にせぬ話に、今度は那由多が首を傾げる。 「領内を見回った父が一服した折に見初め、以後たびたび茶屋で休むようになった。だが母は身体が弱く、家も裕福ではなく。時おり床へ臥す事を聞いた父は病身を案じ、家来の反対を押し切って正妻に娶ったそうだ」 「それで、千代様が後妻になったのですね」 「だが千代様は武家の娘、市井の娘が正妻なのは侮辱に思えたのだろう。更に子は皆、志体がなく……俺は風当たりが強い覚えしかない」 「それでも。千代様もお父様が大好きだったんだと思いますよ」 リーディアの言葉に項垂れるゼロの頭を、那由多はわしわしと撫でた。 「なぁ、ゼロ。この出生……いや、なんでもねぇ。しばらく気をつけて、過ごせよ」 言いかけて止めた彼の手へ、不意にゼロは守り袋を押し付ける。 「これ……馬鹿っ、気をつけるのはお前の方だって!」 「うっせ。勾玉は壊れたし、何かあったら勝手に手を取るんだろ。ありがとよ、追っかけてくれて」 「だって約束、しただろ」 憮然と答えた那由多は守り袋を握った手で相手の胸を小突き、こくこくとリーディアも頷く様子にゼロが苦笑った。 「戻らねぇと、他の連中も心配してるな。それに後は天見家当主が領分だ」 彼岸の星夜を仰ぐ友に那由多が倣い、リーディアは夫へ寄り添う。 ゼロの父や母、命を落とした家臣や領民……それらの御魂が天より此の地を見守り、良き方へ照らしてくれるよう祈りながら。 |


