おいしいもので感謝
マスター名:茨木汀
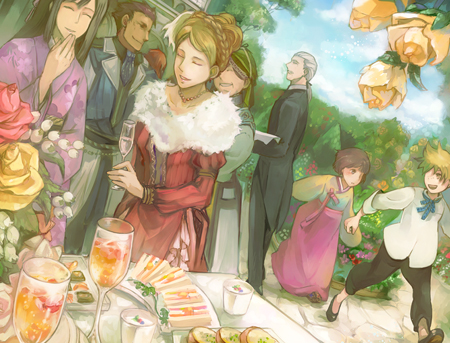
|
|
| ■オープニング本文 ――佐羽へ このごろ寒くなってまいりましたね。こちらは収穫や冬支度に忙しい日々が続いております。 お前はしっかりした子だから、風邪などは引いていないことでしょう。あまり人見知りをしないから、町の暮らしに慣れたのかも、そんなには心配していないけれど。 でも、お世話になっている方にはくれぐれも感謝を伝え忘れないように。折に触れて心からの感謝を伝えられるよう、日々気をつけることです。 それでもまだお前には、資金も揃わず四苦八苦することでしょう。わずかばかりですが、畑でとれたさつまいもを送りました。それで何か得意なものを作って、お世話になっている方にお礼の品を作るとよいのでは、と思っております。 家のことは心配しなくて結構です。今年は流和ちゃんのお師匠様や、流和ちゃんのために来てくださった開拓者の皆様がよくよく田畑を手伝ってくださいました。お前は料理に励みなさい。 では。 ――母より 追伸 お前の成功と元気を願っておりますが、挫けたのなら帰っておいでなさい。よい嫁ぎ先を探してあげます。 かさり、音を立てて手紙を畳む。 「もう、お母さんったら‥‥」 滲んだ涙を拭い、最後の一文に苦笑する。半ば強引に飛び出してきた家だし、家族との時間はあまり持たなかった佐羽だ。じんわりと胸が熱くなる。 別に不仲だったわけではない。ただ姉が四人もいて、あまり過ぎている女手であった佐羽は親友の家を切り盛りしていた。だから、あまり家族と親密に過ごした覚えがないのだ。 それでも特別に寂しいとか悲しいとか、思ったことはなかった。村では普通のことだったし、村ひとつが大きな家族みたいなものだ。その中で佐羽は、自分の父母や兄弟より、親友やその家族と親しくしていたに過ぎない。それだけなのに、今になって届いたこの文がこの上なく嬉しかった。 大事に文を懐に仕舞い、一緒に届いた木箱を見やる。とても嬉しい。それは確かだ。間違いない。けれど。 おそるおそる、ひとつめの箱を開けた。 「うわ‥‥ぎっしり」 これをあたしひとりで料理するの‥‥? ちょっとだけ佐羽の頬が引きつった。 お母さん、やりすぎ。 この季節の薔薇は、色の深いものが多い。今でも透き通るような桃色の薔薇も咲くことは咲くけれど、それよりもベルベットのように深い牡丹色や、褪せたようにくすむオールドローズの色がことのほか美しかった。この庭の主は、もう本当に最後の薔薇だから、あまり咲いていなくて、と言っていたけれど。 そんな今年最後の薔薇の飾られた、白い壁の応接間。天気がよく暖かいので窓を開け放ち、庭の景色を楽しみながら出されたミルクティーに口をつける。 覚えのある、芳醇な香りと濃厚な味わい。 「アッサムティーですね。おいしいです」 佐羽の言葉に、ミルクティーと同じ色の髪をした綴はふわりと笑う。 「ええ。寒くなってくるとミルクティーがことのほかおいしいですから」 そうして他愛無い雑談を交え、佐羽は母からの手紙の件を相談した。 「まあ、素敵なお母様ですね」 「はい、あたしもすごく嬉しかったんです。でも、やりすぎ感も否めないっていうか‥‥。たぶん畝ひとつ分、丸ごと送ってよこした感じで。これくらいの木箱五つって豪快すぎるっていうか‥‥。よっぽど豊作だったみたいです」 「まあ‥‥! すごい量ですね」 「それでもういっそどうせなら、みんなで何か作ったらどうかなって。 いつか、村でお菓子教室みたいなことしたんです。そんな感じでやりたいなーって」 「素敵だと思いますよ。場所は確保できましたか?」 「それが‥‥。たぬきーずの空き家は台所設備もないし‥‥、もしよかったら、綴さんのお家を貸してもらえないかなって‥‥」 だめですか? 上目遣いで見上げると、綴はふんわり微笑んだ。 「構いませんよ。わたしも混ぜてもらっていいかしら」 「もちろんです! よかったー。じゃあ、お邪魔をしますけどよろしくお願いします」 「こちらこそ。ちょっと手狭ですけれど、二、三十名くらいならなんとかなると思います。キッチンが無理なら、リビングや応接室もありますから。火や水を使わない作業はそちらでも構わないでしょう」 「はい。えっと、それで材料なんですけど‥‥」 「基本的なものを揃えるくらいでいいのではないかしら。わたしの伝手で、安くしてくれると思いますから」 「助かりますー。あ、調理器具はどんな感じですか?」 「たくさんありますよ。洗いながら使うのが面倒なときもありますから、泡だて器なんかも複数揃えていますし‥‥。多少は共用しながらになると思いますけれど。 あ、刃物だけは心配しないでください。いくらでもありますから」 なんで刃物‥‥? 引きつりつつも、佐羽は笑顔を返した。 そんなこんなで、当日。 「すごーい、柔らかい!」 ほっくほくに蒸かしたさつまいも。はくり、と咥えると唇だけで実を崩せる柔らかさ。広がる素朴な甘み。舌で押えると、ふんわり潰れる。 「繊維もほとんどないのね。舌触りがとてもいいし、裏ごししなくても使えそうだわ……」 佐羽と同じく、品質確認として一口食べた綴も驚いた。ついつい一本まるごと平らげた佐羽は、ぱぱっと使ったものを片付けて、人を迎える準備を整える。綴もそれに習った。 「なんか、いつも通り他の人に頼りっきりな感じがしないでもないけど……、楽しんでくれるといいな」 わくわくと待ち構える。今日はどんな人が来てくれるだろう。おいしいお芋を使って、どんな料理ができるのだろうか。 今から楽しみだ。 |
| ■参加者一覧 / 柚乃(ia0638) / 礼野 真夢紀(ia1144) / 皇 りょう(ia1673) / 和奏(ia8807) / フラウ・ノート(ib0009) / 明王院 未楡(ib0349) / ティア・ユスティース(ib0353) / マルカ・アルフォレスタ(ib4596) / カチェ・ロール(ib6605) / 平良 良平(ib8272) |
| ■リプレイ本文 ●ようこそ、またよろしく ドアノッカーを叩くと、ぱたぱたと出てきたのは佐羽だった。 「ようこそ! 来てくれてありがとうございます」 「いらっしゃいませ」 ふわり、綴も笑顔で出迎える。 「薔薇の花びらの砂糖漬けの時は、ありがとうね♪ 今回もお願いするわ」 軽く頭を下げてから挨拶するフラウ・ノート(ib0009)。砂糖漬けが恋人に好評だった、そう笑う。 「まあ……。それはよかったわ」 「美味しいお芋料理が食べられるって聞きました」 カチェ・ロール(ib6605)が素朴な動機を伝える。照れたように佐羽が笑った。 「えへへ、お母さんがねー」 簡単に事情を説明する。明王院 未楡(ib0349)が微笑んだ。 「あらあら……いいお母様ですね」 折角のお心遣いですし、和気藹々と素敵な一時と出来るようお手伝いさせて頂きましょうか。そんなことを考える未楡は、見たところお淑やかなお姉さんだがれっきとした母親だった。ほのぼのする輪の中で、けれど少しばかり表情の冴えない少女もいる。 「よいお母様ですわね」 マルカ・アルフォレスタ(ib4596)の声には、佐羽が知る限りではめずらしい感情が滲んでいた。寂しげな響きは聞き覚えがある。けれど、どこか羨ましげな、そんな感情を滲ませているのは少し、めずらしい。 言葉に詰まった佐羽のかわりに、綴は玄関脇の生垣から深い紫色の薔薇を手折る。それを金色の髪にさし、黒いレースのリボンでとめた。 なぐさめなのか励ましなのか、はたまた同情なのかはまるでわからない。それでもマルカはそっとリボンの結び目に触れて、一拍の沈黙ののちに礼をのべる。にこりと綴が微笑んだ。言葉もなく理由も動機もわからないけれど、それはささやかな心遣いだった。 「さあ、どうぞ中へいらしてください。ここは暖かい土地だけれど、冬になるのだもの」 家の中は清潔で、窓にはレースのカーテンが引かれている。そのカーテンに漉された日の光が、規則正しく等間隔で続いていた。ジルベリア風ではあるが、天儀の気候にあわせた木造。靴を脱ぐ習慣はなく、玄関のマットで軽く靴の土を落として中に入る。白く塗られた壁と、少し褪せたような板張りの床。短い廊下を抜けて通されたのは、まずリビングだった。作業のためにクロスのかかっていないテーブルと、壁際に避けられた椅子。火の入れられた暖炉は、日中ということもあり真っ赤な熾き火が置いてあるだけだ。それから、隣り合うキッチン。長方形の分厚い作業台に調理器具が並ぶ。 「いつまでも家事全滅の精霊などに負けていられませんわ!」 ぐぐっと決意の握りこぶしを握り締め、意気込むマルカ。柚乃(ia0638)はその蒼い髪をゆるく三つ編みに編みこんで、蒼いリボンをきゅっと結んだ。それからフリルに縁取られたエプロンを着て、準備万端。この家によく溶け込む、ジルベリア風の装いだ。 「お芋のお菓子ですか。 数を作れるように簡単なもので行きましょ」 礼野 真夢紀(ia1144)はいつも通り、てきぱきと自分の使う材料をそろえはじめる。 「秋の味覚満載ですね」 箱置きされたさつまいもを見て、ティア・ユスティース(ib0353)は微笑んだ。 「料理教室……ふむ」 皇 りょう(ia1673)は、一年近く前のことを思い出す。 「以前「けーき」を教えて頂いたあれか。あれに参加するまでは、私が料理を一品完成させる事が出来るとは夢にも思わなんだな。……くっ」 自分で言ってて切なくなったらしい。その台詞に、あはは、と佐羽は苦笑した。 「真夢紀ちゃんのお手柄だったよねー」 りょうの苦手分野と真夢紀のてきぱき片付ける性格が、上手く組み合わさった結果といえよう。……あどけない見た目と常にいろんな食べ物を持っている印象からつい失念するが、意外と真夢紀は論理的だ、というのが佐羽の感想である。 「今回もジルベリアの甘味のようだが、さつまいもは天儀でも馴染み深いな。冬の寒空の下で食す焼き立ては技を凝らした逸品にも勝る」 じゅるり。 (――っと、いかんいかん。今回はその技が目的なのだから) 食欲に傾きかけた自分を、はたとわれに返って戒める。 「しかし甘味ばかり作れるようになっても、妻としてどうなのか……」 りょうの呟きに、はっ! と佐羽は息をのんだ。しかし、当のりょうは頭を振る。 「いやいや。こういった積み重ねで基礎的な技術も磨かれていくのだろう。地道な努力が大切だ。全ては、素敵な殿方と夫婦になった時の為に!」 ぐっ、と握った拳。自己完結しておのれの目標を改めて握り締める。が、突っ込みはなされた。 「りょうさん!」 「な、なんだ、佐羽殿」 「忘れてた……! ついお菓子に目がくらんでて、あたし。 お菓子も大事だけど、ごはんも大事だよ……! 次はごはん作ろう、ごはん!」 佐羽の料理魂に火がついたらしい。綴が当たり前のように予定を立てた。 「そうねぇ……、クリスマスのご馳走が妥当かしら」 今回のが始まる前に、なぜか次回の話に飛躍していた。 部屋分けは、キッチンとリビングに分けておこなわれた。客間はいらなさそうだし、人数も多くはないのでのびのびと好きなだけ自分のスペースを確保できる。希望のあった柚乃と、こまごまとした作業が多い真夢紀、いろいろ学びたいカチェや佐羽、りょう、それから一人で黙々と作業するのが得意な和奏(ia8807)が振り分けられる。 「わからなかったら、こちらに顔を出してね」 そう言う綴はリビングだ。作業に不安のあるマルカや、ヘルプが得意な未楡、学ぶ名目で興味は紅茶のほうにあるフラウ、数を作る手伝いのティアがリビングチームになった。 ●チームキッチン 頭をつきあわせていたのは、佐羽とカチェだった。 「何からしようか」 「クリームと生地の両方を作って、作り方を覚えたいです。 余裕が無かったら、クリームだけ覚えて、生地は何とかします」 カチェの言葉に頷き、佐羽は他の面子に視線をとめた。 「柚乃さんは?」 「お茶請け菓子の種類を増やしたくて。 あ、お店に来て下さるお客様にお出ししている物ですっ」 看板娘だという柚乃の、ささやかなおもてなし。きっと可愛いがられる看板娘さんなんだろうな、佐羽はほんわかした。 「わぁ、なんか素敵。おいしく作んなきゃねー。真夢紀ちゃんは?」 「まゆは芋羊羹と芋ケーキ、それから干し芋です」 「レシピを教えてもらえますか?」 「カチェちゃん、あたしもあとで写させて」 料理の同時進行はできても、同時にメモをとるのはむずかしい。わかりました、頷くカチェに佐羽はほっとした。 栗を買ってきた和奏は、よく手を洗ってから栗きんとんを作る。焼き芋もおいしいが、今回は栗きんとんにさつまいもを入れることにした。 さつまいもを入れるのが正しいものなのかどうか、それは和奏にはわからない。ただ、レシピには載っていたので問題はないのだろう、と判断したのだ。 まず栗とさつまいもを蒸す。蒸しあがった栗を裏ごし器で地道に裏ごししていく作業。繊維を取り除きなめらかな口当たりにするため必要な作業だが、なかなかどうしてめんどうくさい。しかし、もとよりそういっためんどうな作業に適正のある和奏は、コツコツ淡々と作業を繰り返していった。栗が終わればさつまいもも裏ごしする。 タルトについては一度簡単に綴が手ほどきをしていったため、各自生地の材料をそろえる。 「すごく美味しそうです。ちゃんと覚えて、カチェも作れるようになりたいです」 見本として置いていった綴のタルトに、カチェは意気込む。ちなみに、芋類は品種やできばえで材料を調節する必要があるので、あらかじめいくつか焼いてあった。 「時間もちゃんとあるし、まずは生地からつくろうよ。材料もいくらでもあるからさ」 バターと砂糖をすり混ぜ、溶き卵を加えてまた混ぜ、小麦粉を入れて木べらで混ぜる。 「これを混ぜればよいのだな。――む、粉っぽいぞ」 「材料が混ざりきってないからなんだって。ポロポロ崩れるくらい粉っぽかったらダメだけど、逆にべちょべちょしてても失敗だから……、まあ、粉っぽかったら卵とかバター、水っぽかったら小麦粉足せばいいだけらしいけど」 わりとどうにでもなるモノ、それがタルト生地だ。パイ生地だとこうはいかない。 「佐羽さん、そろそろ大丈夫ですか?」 「うん、真夢紀ちゃんお願いー」 何度か作った佐羽は、ぱぱっと生地をまとめると布巾でくるむ。 「氷霊結いります?」 「助かるよー」 他人のスペースをじゅうぶんにあけて、真夢紀の作った氷のそばに置いておく。そしてクリームに使うさつまいもを蒸かすため、火にかけた。 「芋羊羹からいきましょうか。下ごしらえがいりますから。 まず寒天を水につけておいて、芋の皮を剥いて輪切りにして、水にさらしておきます」 「おっけー」 「あと、干し芋用に蒸しておきましょう。数日晴れますよ」 「あ、それは村でもやってたなぁ。丸ごとでいいよね? 蒸すの」 「大丈夫です。その間に芋ケーキを作ります。皮剥いて賽の目に切ってください」 「はーい」 てきぱき切って、それを茹でる。熱いうちにつぶしてバターを混ぜる。 「卵を割り泡立てて、砂糖を加えて牛乳を加えて、最後にさつまいもを加えます」 「了解ー」 あとはケーキ型に入れてオーブンで焼くだけ。次に蒸しあがったさつまいもの皮を剥き、縦に切って笊に並べる。風通しのいいところで――むろん夜間は取り込む――三日干す。 「しっかり干せば一冬持ちますが犬猫虫に注意です」 「裏に干してくるよー」 ぱたぱた佐羽が出て行く。タルトを作る三人も生地を作り終え、裏ごし作業に入っていた。いち早く終わった柚乃がクリームを作り上げ、生地を型に敷き、フォークで空気穴をあける。そこへクリームをしきつめ、バターを塗ってさつまいもケーキと入れ替わりにオーブンに入れた。こちらはものの数分で焼き色がつくので次々と焼けるだろう。 (型とかあるかなー) 残った時間で、クッキーを作りたい。リビングに行くと、綴は頷いた。 「クッキー型ですか? もちろん、いくらでも」 嬉々として綴が引っ張り出したのは、星だのハートだの人物だの動物だの……、挙句の果てには文字もあれば武器まで、ありとあらゆるクッキー型が山ほど入った箱だった。さすが趣味人である。 「もふら様型のさつまいもクッキーを大量に作りたいなー」 ひとつひとつ確認しつつ、柚乃は型を探す。これは犬、これは牛……、あった。 大中小、しっかり揃ったクッキー型。いつも味見をしてくれる八曜丸によく似たそれを、大事に取り上げた。 クッキーの生地は、タルト生地とさほど変わらない。こだわらないならまるで同じ分量で作ったって構わないくらいだ。それにさつまいもを混ぜ込めば、さつまいものクッキーになる。 戻ってきた佐羽は、真夢紀が茹でて潰してくれていたさつまいもを受け取った。 「あは、ありがとー。さすがに裏ごしとか多くて」 「時間かかりますからね。寒天も火にかけときました」 「じゃ、あとはお砂糖と……ここでお芋入れちゃっていいの?」 「はい。熱をしっかり取らないといけませんから、あとはまゆがやっときます。冷やして固めるのは普通の羊羹と同じですし……佐羽さんは大丈夫ですよね?」 「うん、ごめん、助かるよー。じゃ、あたしタルトの裏ごしに戻るね」 「カチェさんは大丈夫ですか?」 カチェとりょうは思わず顔を見合わせた。 一度に三つ……四つの料理を平行作業? 無理だ、無理。なんであれができるんだ。 「……なんとなくです。最初にレシピ聞いてなかったら、全然わからなかったと思います」 その答えに、ふと柚乃は思い出した。 「開拓者になる前は家事とかさせて貰えなくて、料理なんかさっぱりだったな……」 箱入りに育った柚乃は、自分で料理、などなじみのない分野だった。それは黙々と裏ごししていく和奏も同じ。こちらは「男子厨房に立ち入らず」の家庭で、やはりもともと馴染みのない世界だ。和奏の場合は、生来器用なたちなので苦労はない。……ただ、オリジナリティを求められても無難かついまいちな仕上がりになりがちだけれども……そんなところが、彼の個性なのだろう。 「そうなのか……」 今のところ、まだそんな主婦必須の技能を身につけていないりょうには縁遠い世界だ。 「でも、今は人並みにならできるようになりました。 味見はね、もふらの八曜丸の役目なの」 今はいない相棒の名前を、柚乃は口に乗せる。このころには、和奏も裏ごしを終えていた。さつまいもと栗を混ぜ合わせ、砂糖で味をととのえ、梔子の実で着色。発色も鮮やかに黄色く色づいたものを、清潔な布巾で絞っていく。 りょうも寝かせていた生地を取り出し、引き伸ばしていく。カチェは型に敷いた生地に、フォークでぷつぷつと空気穴をあけていった。 それぞれの作品が形になりはじめていた。 ●チームリビング 「じゃあ、まず生地を捏ねましょう」 綴の言葉に、それぞれ材料をそろえて捏ね始める。もとより料理はお手の物、なフラウに未楡、それからティアは、ささっとバターに砂糖をすり混ぜていく。マルカも気をつけつつ、白い粒子をバターに投入してすり混ぜた。 「お料理に慣れていないうちは、泡だて器より木べらがいいですよ。空気をあまり含ませてはいけませんから」 未楡が木べらを渡してくれたので、それで作業した。それから卵を溶く。割ったのはいいが、溶くのに妙に力が込めてあり、中身が吹き飛んだ。 「あっ」 「あらあら……そこはこうすると簡単に出来ますよ」 白身を切るように、手早く。ふわふわの卵料理を作るときは空気を含ませ柔らかく溶くが、なめらかな舌触りが必要なとき、空気はむしろいらない。 「やってみますわ」 その後も二度ほど中身を飛ばしていたが、三度目になんとか溶ききった。少しずつ卵を入れて混ぜ、小麦粉も小分けして入れる。 マルカがそんなことをやっているうちに綴はさくさく散らかったものを片付け、未楡とティアは数を作るために量産体勢に入っていた。生地を作ってはキッチンにある真夢紀の作った氷のもとへ持っていく。未楡はそのついでにキッチンチームの進歩具合を確認し、助言することも忘れない。 「まとまってきたら、押し付けるようにしていきます。しっかり練りこめばかたい生地に、切るようにまぜていけばさくさくした生地になりますよ」 フラウも作業をしつつ、念入りに手を洗い、蒸かしたさつまいもを鍋ごと持ってきた綴に質問をする。 「このタルト生地って、パートシュクレのレシピですよね。生地にバニラエッセンスは入れないんですか?」 「基本の作り方だから、今回はそのほうがいいかしらって……。アーモンドの粉末を入れて混ぜ込んだり、基本をおさえていれば応用がききますから」 ちらりと綴の視線がキッチンに向かったのを見て、なるほどと納得する。洋菓子初心者があちらには多い。 「あ、じゃあ……」 疑問を投げかけながら、裏ごし作業に入った。ティアも鼻歌交じりに木べらで裏ごししていく。裏ごし器の下に受け皿を置き、網の上に皮を剥いた蒸かし芋を少量乗せる。木べらに手を添え、ぐいと体重をかけて押しつぶす。それから一定の力をかけて木べらを引き、漉していく。 「そろそろ取り替えましょうか」 途中、未楡は別の裏ごし器を差し出した。 「ありがとうございますわ」 微笑んで受け取る。網目に繊維が絡むので、あまりえんえんと同じ裏ごし器を使い続けるのは非効率的なのだ。 そんな作業をしていると、実家のことが思い出された。母は料理の苦手な人で、そのぶんまでティアが作っていたこと。窓から差し込む、明るい日の光。色の深い薔薇の飾られた部屋。 「ふふふっ。 こんな素敵なお庭のお宅で、皆さんと一緒にお料理したり、お茶をしたり……。 ほんとに楽しいですわ」 ティアの感想に、綴が微笑む。 「よかった。佐羽ちゃんが喜びます」 笑みを交し合う。そこへ、ごりごりと音がした。 「まあ……削れちゃっていますね」 どこか感心したような、のどかな未楡の苦笑。ティアと綴の笑みが、少し困ったようなほほえましいような、そんな柔らかさを増した。 裏ごしを終えたさつまいもに、砂糖、バター、生クリーム、卵黄を加えてよく混ぜる。まだ暖かなさつまいもが、ふわりとバターや生クリームの香りも含んでやさしい匂いをただよわせていた。なめらかになるまでよく混ぜ、バニラエッセンスを数滴垂らして練りこんだ。 そこまで仕上げたら、次は休ませたタルト生地を取ってくる。円形になるようにのし棒で引き伸ばしていく。少し硬い、ひびが入らないように少しずつ伸ばす。型より一回り大きくなったところで終了。タルト型をおおうように乗せた。 隅をしっかりと型に沿わせていき、一周したら軽く形をととのえる。のし棒をまた取って、型の上を転がした。きれいに余分な分がカットされる。 「じゃあ、これはまとめて次に回しますわね」 ティアはそれをひとまとめにして氷のところへ戻した。大量に作るときのコツでもある。 フォークで生地に穴をあけていった。ここで少し冷やして休ませる。その間に次の生地を別のタルト型に敷いていくのだ。 マルカもまた、転んだり汚れたり……ちょっと……だいぶ? ぼろぼろになりながらも、表面にバターを塗るところへこぎつけていた。 ●試食、という名目のお茶会。 紅茶に期待を馳せたフラウに、綴は少し申し訳なさそうに眉尻を下げた。 「季節が季節だから、オータムナルになってしまうけれど……」 「ぜんぜん大丈夫です!」 きょとん、と佐羽が首をかしげる。気付いた綴が説明をした。 「紅茶はね、確かに保存のきくものだけれど、あまり長々と保存しては味も風味も落ちてしまうの。薬草をいくら乾燥させたからって、一年以上前のは使ったりしないのと同じです」 「それに摘んだ時期で味がけっこう変わるものなんです。今の季節はアッサムもダージリンもオータムナル。品質はセカンドフラッシュに劣りますけど、風味が強いのでミルクティーに向くんです」 フラウが引き継いで説明してくれる。 綴はオータムナルをよい紅茶、として出すには少し抵抗があるらしい。それに見合った飲み方をするぶんには充分なのだが、彼女なりのこだわりがあるようだ。 「年を越してしまえば、ディンブラなんかが旬になるのだけれど」 「あ、あの、本当にぜんぜん気にしてませんから!」 「そう……? 夏にいらしてくれたら、セカンドフラッシュをご馳走するわ」 ダージリンのフラワリー・オレンジ・ペコーとか。また佐羽にとっては耳慣れない専門用語が飛び出したが、田舎娘はとりあえずスルーしておいた。これ以上詳しい話をされても、覚えていられる気がしない。詳しく聞くのは今度にしよう、と心に決める。 タルトやケーキ、羊羹を切り分け、ケーキスタンドに乗せていく。紅茶は辞した和奏以外、引き続きアッサムのミルクティー。 「カチェの知らないお菓子がたくさんです」 好きなだけ各自取り分けて自分の皿にのせる。口の中に広がる素朴な甘さ、なめらかな舌触り。さくりとした食感の生地。つめたい羊羹の口当たり。 ゆっくりと味わい、それぞれの甘味を楽しむ。 「美味しいお菓子ばかりで、カチェは幸せです」 そんなカチェの向かいで、マルカは自分の作ったタルトと向き合っていた。何かあったらいけない……、そのへんの自覚はしっかりある少女は、みずからひと口食べ……あまりの味に悶絶した。 「〜っ」 にがい、おそろしくにがい。しかも激しく辛い。なんでお菓子がこんなににがくて辛いだと問いただしたくなるくらいにがいし辛い。これは既にお菓子の領域を突き破った何かだ。 察した佐羽は、無言で濃く甘く淹れたミルクティーをさしだす。やはり無言で、マルカはそれを飲み干した。 「……がんばったね、マルカさん」 「……また……また家事全滅の精霊にっ……」 「どこで間違えていたのかしら……?」 見守っていたはずの目を潜り抜けて絶妙な失敗を重ねていたマルカは、ある意味天才かもしれない。なじみのない綴はとてもまずかったのだろうな、とあたりをつけるが、なぜそこまで、という理由までは察せられないでいた。 そんな惨事の横で、フラウとティアは自分の作ったタルトの味をたしかめる。 「他のも食べてくださいねー」 「はい。ありがとうございます」 りょうの皿にケーキを取り分けながら、佐羽が言う。礼を述べてフラウもケーキスタンドの上から取り分けた。 「ティアさんもどうですか?」 「では、いただきますわ」 「お茶のおかわりはいかがかしら」 「ありがとうございます。お願いします」 フラウの礼をうけて、綴が紅茶を注ぐ。 紅茶に浸る女性陣とはかわって、和奏は丁寧に緑茶を淹れていた。おいしいお菓子には苦いお茶。 (お手前を習って良かった〜) こちらも茶葉の品質は上々。文句なしに好みの味を引き出した和奏は、嬉しくなった。 ちなみになぜ綴の家にそんなものがあるのかというと、ブレンドティーやフレーバーティーによく合うのだ、緑茶が。綴的にお茶の和洋折衷はアリなのである。抹茶もお菓子の材料にストックしてあるくらいだ。……まあもっとも、茶器はないので陶磁器のティーポットに白磁のティーカップなのだが、淹れかたに大差はない。和奏は戸惑わず、みごとなお手前でそれを淹れた。 柚乃も持ち帰るぶんを包み、たくさん作ったうちから試食用に取り分けたクッキーを分けていた。カチェがさくりと齧り、おいしいですと伝える。いただこう、うむ、なんと美味な。りょうの率直な感想。そんな和やかな様子に微笑んで、未楡は佐羽へ口を開いた。 「この間助けて下さった自警団の方々にもお礼かねがねお届けしましょうね」 「……あっ」 忘れていたらしい。えへへ、と照れ笑いしてごまかした佐羽だった。 ●空っぽの小瓶、あってはいけない容器 「えっと……本日はお集まりいただき、ありがとうございました! たくさん作ったし、いくらか包むからおみやげにしてください。あ、もちろんみんなが作ったぶんは好きなだけ全部持ち帰っても大丈夫です。えっと、今後ともよろしくお願いします」 明るく、少しぎこちないながらも佐羽が締めくくる。口々に挨拶を交わして帰路についた。佐羽もいくつかの包みを持って玄関に立つ。 「ちょっと届けに行ってきますね、綴さん。すぐ帰ってくるので」 「急がなくてかまいませんよ」 「じゃあ……行きましょうか、佐羽ちゃん」 片付けの途中だが、あまり長々と未楡を引き止めるのも何か違う。そんなわけで、二人して連れ立っていくのを綴が見送った。 戻ってくる間に、軽く片付けてしまおう。そう思った綴はキッチンに避けただけの材料を見回して、ふと違和感に気付く。 「……あら?」 空っぽになったバニラエッセンスの瓶。なんでだろう……? それに、どうしてお塩の容器がここに……? 一瞬疑問に思うが、次の瞬間はっとした。 普段はけっこうしっかりしているのに、料理をはじめたらとたんにそそっかしくなった少女。食べたとき、なんとも言いがたい表情をしていた。 気付いてあげればよかった。バニラエッセンスというのは、その甘ったるい香りに反してとてつもなくにがいシロモノなのだ。そう、ちょっと詐欺ではないかと思うくらいに。 瓶一本入ったタルト……、しかも、たぶん砂糖と塩も間違えたのだろう。想像するだにおそろしい。 「……塩辛くて……そしてにがかったのね……」 |


