タイトル:【JB】シルバー狂想曲マスター:風亜 智疾
| シナリオ形態: イベント |
| 難易度: 不明 |
| 参加人数: 3 人 |
| サポート人数: 0 人 |
| リプレイ完成日時: 2009/06/19 03:18 |
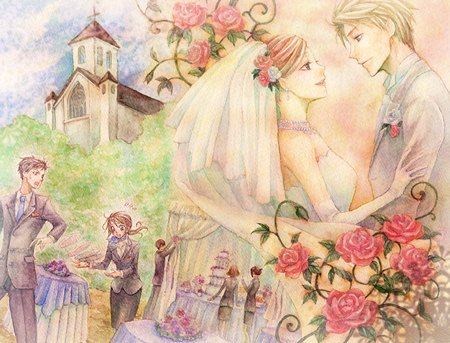
●オープニング本文
6月は、幸せな恋人達にとって特別な意味を持つ月である。それは、恋人達が地球を守る能力者であっても変わる事はない。しかし。
「‥‥つまり、6月の結婚式は禁止、と言う訳かな?」
UPC管理局からの通達を、カプロイア伯爵は読み返した。正確には、LHからの呼び出しに3時間以内で応えられる場所で行うべし、との事だ。たかが式典、されど式典。島内での実働が2000人以下の状況で、結婚式1組で50人の能力者が動くと考えればバカにならない。
「縁起物ですから。良い日取りに集中して行われると、LHの即応能力はが大きく落ちると思われます」
「仕方が無いのは理解した。しかし、LHに式場などあっただろうか?」
ホールの類は無くは無い。しかし、足りるはずも無いと秘書は言う。
「LHから3時間以内、か‥‥ふむ」
今一度、文面を読み直す伯爵。LHの予定停泊位置から程近い無人島が差し押さえられたのは、暫く後の事だった。
「何も無い場所だがね。建物は急いで手配したまえ。交渉が上手くいけば、移築も視野に入れるように。利用者の意見も聞いて、だね」
「‥‥それ以前に、安全を確認すべきかと」
何かの間違いでキメラがいないとも限らない。これから忙しくなりそうだ、と言いながらも伯爵は常より楽しそうだった。
□■□■□
「‥‥浮かびませんわ」
社長室でポツリと呟いたセブン・アンド・ジーズ社の女王様は、手元にあった上質な紙を、ぐしゃぐしゃと丸めてダストボックスへと放り投げた。
綺麗な弧を描いてシュートされるか、と思われたのだが。
既に備え付けの小さなダストボックスは同じ状態になった紙で一杯になってしまっていて、何というか「もう入りません!」と強烈な自己主張を行っていた。
哀れ、ぽとりと落ちた紙には、黒のペンシルで『あるもの』のデザインが描かれていた。
――そう。それは、6月の必需品。結婚式の記念品として特別に作る『銀食器』のデザイン案。
「と、いう訳ですの。毎年違うデザインの品を提供しておりましたけど、私とした事がどうやらスランプに陥ってしまった様で」
会社の定例会議でそう言ったオレアルティアに、集まった社員達は驚きを隠せなかった。
何せこの女社長の口から、スランプなどという言葉が出て来たのは、就任して初めての事だったのだから。
「ですから、貴方達にも案を出して頂きたいと思いましたの」
微笑みながら言ってくれるが、そんな簡単に「はい、こんなのどうでしょう」なんて言える訳もない。
「なぁ、社長。そんなすぐに『案を出してくれ』とか言われても、俺等はデザインなんてした事ねぇから無理だって」
一番若い役員であるレグズィスの言葉は、その場に集められた社員の代表といえる一言だったが。
(「よくやった!」)
なんて思う、まだ社長の恐ろしさを知らない若い社員と。
(「あーあ、言っちゃいけない事を‥‥」)
なんて思う、社長の恐ろしさを骨の髄まで知っている社員とに分かれてしまった。
レグズィスの一言に、S&J社の女王様は、ピクリと笑みを別のものに変えて、こてりと首を傾げてみせる。
「レグズィス? 私、耳が遠くなってしまったのかしら。貴方、今何て言いましたの?」
会議室の温度が一気に氷点下に変わった。
(「社長、怖い!!」)
(「メッチャ怖い! 笑ってるのに怖い!!」)
集められた全員が、たらりと冷や汗を流す。
それだけオレアルティアが怒ると(表情はあくまでも微笑んでいるのだが)怖いのだ。
「私の嫌いな言葉、貴方はご存知よね?」
いつもよりほんの少しばかり低い声音で、あくまでも優しく問い掛けるのだからこの社長はある意味恐ろしい。
「で‥‥『出来ない』『無理』『不可能』‥‥デス」
「結構。ではもう一度伺いましょう。レグズィス、貴方、何て言いましたの?」
片言でしか喋れなくなってしまった哀れ営業担当レグズィスに、その場に居合わせたメンバーは手を組んで祈る事しか出来なかったのだった。
「じゃあ、こうしたら?」
社長による笑顔の『お仕置き』が一通り終了したのを確認して口を開いたのは、こちらも会議に参加していたヴォルフガンクだ。
ちなみに。間違いのない様に言っておくが、見た目は正反対でもレグズィスとヴォルフガンクの2人は後者の方が年上である。
「社長はスランプでデザインが浮かばない。僕らは食器のデザインをした事がない。でも、お客には満足して欲しい。そういう事だよね」
「えぇ。その通りですわ」
普段の微笑みに戻ったオレアルティアに、小柄な科学者は淡々と言葉を続ける。
「だったらいっそ、お客自身にデザイン案を提出してもらったら? それなら僕らもお客も満足すると思うけど」
と、いう事で会議は無事終了した。
社長のスランプと社員の平安(社長が怒ると怖くて、仕事が手に着かない)。そしてお客の満足度。
その全てをくるっと丸めて解決させる案として、ヴォルフガンクの『お客のデザイン案』が採用されたのだ。
しかし、いつの時代も幸せ一杯のカップルがいれば、当然それを妬む者もいるわけで。
兎にも角にも、本年度のジューンブライド用銀食器デザインという狂想曲(カプリッチョ)が、ここに開幕したのである。
●リプレイ本文
●社長の思いつき「今日は貴方がたにも、協力して頂きますわよ?」
にっこり笑顔のオレアルティアは、全従業員を大きく2班にわけ、其々に白と黒の腕章を配り始めた。
「社長、これは?」
「見ての通り、腕章です。本日のイベントは理解してますわよね?」
「え、えぇ。それはもちろん。ジューンブライド用のシルバーデザインの受付日です」
黒の腕章を受け取った社員が、コクコクと頷いたのを確認して、社長は結構。と微笑んだまま頷き返す。
「白は純粋派。黒は妨害派。貴方たちの班分けに使用したのは、既婚者か未婚者かです。白の腕章を受け取った既婚者は、弊社にいらっしゃる『純粋派』の方々を支援して下さい。黒の腕章を受け取った未婚者は、その反対『妨害派』の方々を支援して下さい。いいですね?」
にっこり笑顔の社長が、自分の腕につけた腕章は『灰色』だ。
どちらにも属さないつもりなのだろう、社長の笑顔が、何故だろう。
とてつもなく、怖い。
「さあ。今年のジューンブライドも、楽しくなりそうですわね」
恐らく。
純粋に楽しんでいられるのは、オレアルティアだけの気がすると、社員は思ったのだった。
●受付開始
受付担当の社員だけは、腕章をつけていない。
ここだけは公平に、という社長の方針である。
「あ、受付ってここか?」
最初の登場は紅月・焔(gb1386)だった。
「はい。S&J社へようこそ。本日のイベント参加者様ですか?」
「あぁ。紅月・焔だ。妨害派に参加させてもらうぜ」
受付担当社員はスラスラと名前を書き付けると、焔へと一枚の紙と黒い腕章を差し出した。
「はい。ではこちらの腕章をお付け下さい。妨害派の方は黒、純粋派の方は白となっております。社屋内でも、その腕章が目印になりますので、絶対に外さない様にお願いします。そして、こちらはデザイン案の記入用紙です。あちらのテーブルでご記入下さい」
受け取った腕章を左腕に取り付け、用紙に目を通しながら焔はふと、疑問に思っていた事を尋ねる。
「ところで。今日の妨害についてだが、一体どの程度までなら許可されるのか確認しておきたいんだが」
「妨害の程度、ですか?」
首を傾げた受付担当社員に、焔はにぃっと口角を上げて。
「あぁ。どの程度までならいいんだ?」
瞬間。受付担当社員の背筋に冷たい何かが落ちた。
「い、一応社屋の破壊、人への甚大なる被害は避けて頂ければ‥‥」
嫌な予感が、受付担当社員の脳裏を駆け巡る。
「あの! くれぐれも。くれぐれもお願いしますから、命の危機を迎える様な事だけは避けて下さいねっ!?」
「常識だろ。それくらいはわきまえてるって。んじゃ、徹夜で考えたデザインを書いて、社屋に入るか」
用紙をひらひらさせながら、デスクへと向かっていく焔に、受付担当社員は半ば悲鳴の様な声で注意事項を叫んだのだった。
そのちょっと後。
「零さん。一緒に考えたデザイン、採用されると良いですね」
「そうだな。こういう時期だし、記念にいいだろう」
受付にやってきたのは、赤宮 リア(ga9958)と漸 王零(ga2930)だ。
「ようこそ、S&J社へ。本日のイベント参加者様ですか?」
若干引きつった笑顔で受付担当社員が尋ねれば、2人はお互いに視線を合わせた後、こくりと頷いた。
「今日はよろしくお願いします。赤宮 リアと申します」
「漸 王零だ。よろしく頼むよ」
2人の名前をサラサラと書き付けて、受付担当社員は念の為にと口を開いた。
「お2方は『純粋派』参加者様でよろしかったですか?」
もう一度、同じ様に頷いた王零とリアに、受付担当社員は其々白い腕章と用紙を差し出した。
「では此方を腕に着用して下さい。本日のイベントでは純粋派の方は白い腕章。妨害派の方は黒い腕章をつける事となってますので、外さない様にお願いします。こちらがデザイン案の記入用紙です。あちらのテーブルをご使用下さい」
腕章と用紙を受け取った王零が、ふと声を上げる。
「すまないが、用紙をもう1枚ずつもらえるだろうか」
「え? えぇ、構いませんが‥‥」
余分な用紙を取り出して渡せば、王零は小さく礼を告げた。
「デザインが複数あるのでしょうか? それでしたら、1枚の紙に複数書いて頂いても‥‥」
「いや。そうではなく。妨害にあった時の為の予備が必要だからな」
成程。と頷く社員に、王零とリアはもう一度頭を下げてから、お互いに腕章を付け合ってテーブルへと向かっていったのだった。
●妨害派のターン
「ふむ。社屋の内装は大体把握出来た。後は、其々担当を決めて、配置するだけか」
焔は社屋の見取り図を広げながら、周囲に集めた妨害派(というか、無理やりその派に所属させられている従業員)を集めて口を開いた。
「あ、そこのあなた。悪いが、エスカレーターの速度は変えられるか?」
指を指された従業員が、戸惑いながら首を横に振る。
「い、いえ。速度は変えられません。安全装置の関係で‥‥」
「なら、全てを下りに変更してくれ。あ、それとそこのあなた。ついでに、各階のエレベーターフロアに『清掃中・使用禁止』とかの看板を掛けておいてくれ」
てきぱきとまるで戦場の指揮官の様に指示を飛ばす焔に、1人の従業員がおずおずと手を上げた。
「あのー‥‥。それだと、純粋派以外の人にも、結構負担がかかる気がするんですけど‥‥」
その言葉に、焔は一瞬見取り図から視線を上げて、それこそ不思議そうに首を傾げ。
「あ? 純粋派? 誰それ? テロ? テロっすか? そんなん知らねぇっすよ」
事も無げに言い放った。
「いえいえいえ! 一応、僕たち妨害派も、社屋内にいるわけですよ? 移動とか、エスカレーターもエレベーターもまともに使えないなんて、そんな状態じゃあ絶対疲れますから!」
「あー。だいじょーぶだろ。うん。‥‥多分」
最後の『多分』は物凄い小声だ。
「だいじょーぶ、じゃないですよー!! 俺たちは一般人ですよ!?」
「だいじょーぶだって。あなたたちなら出来る! ‥‥多分」
だから、多分の部分が小声過ぎる。
その場にいた妨害派所属の従業員たちは、残念ながら今回一番の被害者となる事であろう。南無。
「んじゃ、後は手筈通りに。A班は玄関前にGO!」
指揮を執る焔。
非常に、楽しそうである。
●純粋派のターン
「2人で考えたデザイン。見直しても素敵ですよね」
にっこり笑うリアに、王零は頷き返してデザインの記入された用紙を見やった。
――袋越しに。
デザインの描かれた用紙は、防水対策用の密閉された袋に入れられていたのだ。
早くも、ここから戦闘は始まっている。
「こちらも、囮のデザイン用紙が出来上がった。予備のデザイン用紙も完了だ」
「一先ず、これで騙されて下さればいいんですけど‥‥」
「しかし、我等純粋派がいれば、当然妨害派もいるだろう。まぁ‥‥実力行使で行かせてもらうが」
袋に入れられた本命を仕舞いこみ、リアと王零は聳え立つ社屋を見やった。
「さて。それでは行くか、リア」
「はいっ! 零さん!」
残念ながら、社屋内にしか腕章をつけた従業員はいない。
彼等は社屋内までは、孤立無援という事になってしまうのだった。
●カプリッチョ、演奏開始!
「あのー。こちらA班。玄関前に到着しました。前方からお客様が2名、いらっしゃってます」
何とも気の抜けた無線(という名の、社内連絡用携帯)会話である。
「客? 腕章は何色だ?」
別の階から、同じく無線で連絡を聞いていた焔が問いかけると、顔の見えない妨害派所属の社員が。
「腕章は白ですね。純粋派の方々の様です」
確認をして、答えた。
「よし。ならA班は玄関前でスクラムを」
「‥‥は?」
突然の指示に、素っ頓狂な声を上げる社員。
まぁ、当然であろう。
玄関前で、スクラム。
何だそれは。新手の虐めだろうか。
「スクラム、知らねぇか? こう、ラグビー‥‥あぁ、イギリスではフットボールってんだったっけか。全員でこう、がっちり体を組んでだな」
「いや、それは知ってますよ。そうじゃなくて、何でスクラム?」
ごもっともな疑問である。
しかし、哀れ妨害派所属の従業員の疑問は、次の一言で片付けられてしまったのだった。
「通せんぼ。以上」
ブツリ、と切られる無線に、玄関前のA班(焔命名)メンバーは涙を流すしかなかった。
一方、社屋へと入る為、玄関前にやって来た王零とリアは、一瞬目を丸くして摩訶不思議な光景を見つめていた。
「あの、零さん。あれは‥‥何なんでしょうか?」
若干、引き気味のリアに、ふむと顎に手をやって王零は眼前に立つ彼らを見やる。
「スクラム、組んでるな。しかも涙目で」
「スクラムは分かるんですけど‥‥何で、こんなところで、しかも涙目でスクラムを‥‥?」
リアの言葉に、王零はこくりと頷いて。
「腕章は黒。妨害派だな。恐らく、我等が入れない様にと誰かが指示した、という所だろう」
さて、どうするか。
相手は一般人。しかしいかんせん、スクラムを組んでいる数がそこそこ。
「すみません。通して頂くわけにはいきませんか?」
一応、とリアが問い掛ければ、普段接客を行っている社員たちは反射的に『いらっしゃいませ!』と通しそうになってしまうが。
「駄目なんです! 僕たち、一応妨害派ですから〜!」
男が群がってスクラム。しかも涙目。
はっきり言って‥‥あまり好んで見たい光景ではない。
「仕方がない。リア、我が先に突っ込む。後に続いてくれ。怪我はせぬ様にな」
「分かりました」
覚悟を決めた2名は、王零を先陣にスクラムに突っ込んでいった。
「メーデーメーデー! こちらA班! 何かよく分かりませんが、突っ込んできましたけど!!」
「奴らは敵だ! なぎ払え!」
「何を無茶な事言ってくれるんですか! 僕たちは一般人です社員です! お客様にそんな事できるわけ‥‥ぎゃあーーー!!」
「どうした!? おい、A班! ‥‥ちっ、やられたか」
移動しながら、途切れた無線をジトリと睨んで、焔はフロアを駆けるのだった。
「さて。無事社屋には入れたな」
「あのー、皆さん、大丈夫ですか?」
ロビーに入って、王零はちらりと背後を確認した。
リアが声をかけるその先には、打ちひしがれた表情で倒れこんでいる妨害派の従業員たち。
「うぅ‥‥何でこんな事に‥‥」
遂に本格的に泣きが入りだした従業員たちに、一先ずご苦労様と声をかけて、天井を睨みつける。
正しくは、上。最上階にあるという、社長室を見据えたのだが。
「いらっしゃいませー。お客様方は純粋派ですよね? こちらへどうぞー」
上を眺める王零と、従業員たちに頭を下げているリアに向かって、何処からか小さな声が。
声の先を見れば、そこには白い腕章を取り付けた純粋派従業員たちがいた。
何故か、物陰に。
「あ、社員の方々ですか? 今日はお世話になります」
ぺこりと頭を下げたリアに、同じく頭を下げる純粋派の従業員たち。
「で。 『あれ』は一体何だったんだ?」
王零が軽く指差す先には、倒れ伏した元スクラムの黒腕章ズ。
「えぇと、社長の指示で私たちも本日、純粋派と妨害派に分けられていまして。彼等は妨害派だったわけですが」
「妨害派の指揮官様に、そこでスクラムを組んで進入を阻止しろ、と命ぜられていた様です」
従業員たちの言葉に、王零は小さく溜息を吐いた。
「子猫は何を考えているんだか‥‥」
実は王零。
別の場所で数度、オレアルティア社長と会話をした事があるのだ。
自身を『子猫』と言って悪戯を仕掛けようとしていた、お祭り好きの社長を知っているだけに、今回のこの社員総出の事態をある程度理解出来てしまった。
「指揮官はこ‥‥いや、社長か?」
尋ねる王零に、いいえと首を振ったのは別の純粋派従業員である。
「社長は本日『灰色』です。指揮官は別の、能力者の男性でした」
「零さん。私、念の為にエスカレーターとエレベーターを見てきますね」
頷いた王零を確認して、リアがトコトコと目的の場所へと向かっていく。
「そういうわけですので、私たちはお2人のサポートをさせて頂きます」
「各階に、私たちと同じく純粋派の従業員がいますから、何かありましたらお声をかけて下さい」
「それは助かるな」
王零の言葉に、従業員たちが小さく笑って携帯を差し出した。
「これは、社内連絡用の携帯です。お貸ししますので、何かありましたらコールをどうぞ」
「成程。相手もこれを使って連絡しているわけか」
「零さーん!」
背後から、エスカレーターとエレベーターを確認に行っていたリアの声が響く。
「今行く。‥‥ところで、その背後で伸びている者たちは一体どうしたんだ?」
言われて、純粋派従業員たちは視線を逸らして、ポツリと呟いた。
「妨害派の指揮官に、突入早々やられたメンバーです」
「目を回しているだけですので、お気になさらずに」
どうやら元スクラムの社員たちより前に、脱落者がいたらしい。
「‥‥健闘を祈る」
呟いて、リアの元へと走り出した王零へと、純粋派のメンバーは。
「お気をつけてー!」
「お幸せにー!」
エールを送る以外、する事がなかったのだった。
「1階のエスカレーターは全部下りに設定されてますね。多分、この様子だと全フロアこの状態でしょうから」
リアの言葉に、頷いて王零はエレベーターへと視線を向けた。
「エレベーターにも期待は出来んな。まぁ、ちょうど1階に停まっている事だし、全てのフロアのボタンを押しておいて、階段を使う事にしよう」
言いながら、エレベーターを開いた瞬間。
ざばーっ。
頭上から、水が降ってきた。
咄嗟に身を翻した王零とリアは、水に濡れる事はなかったが、その場とエレベーター内は水浸しだ。
「‥‥階段で、決定ですね」
「あぁ。そうだな」
頭上に仕掛けられていたバケツを睨みつけてから、王零はエレベーター内に滑り込み、全てのボタンを押す。
そのまま外に出て、リアの手を引いて階段を目指すのだった。
「そろそろ来るか‥‥」
「あのぅ。これ、一体どういう意味があるんでしょうか?」
眼前に広がる茶色を見やって、呟いた妨害派従業員に、焔は胸を張って答えた。
「事件現場にテープを貼るだろ? あれの応用だ」
「はあ‥‥」
1階から2階へと上る階段の踊り場。
そこを塞ぐ様に貼り付けられているのは、ガムテープだ。
「それじゃ、B班はここで待機。テープの直ぐ後ろでスクラムな」
「またですか!?」
悲痛な妨害派従業員の声が、踊り場に響いた。
「‥‥これは‥‥」
「ガムテープ、だな」
焔が次の仕掛けへと向かった頃、リアと王零は階段の踊り場へと到着していた。
眼前に、まるで「KEEP OFF」とでも書かれていそうな勢いで貼り付けられているガムテープ。
そして、その隙間から見える向こう側には、またも涙目でスクラムを組んでいる黒い腕章をつけた人間たち。
「いくらお祭り騒ぎとはいえ、物の無駄遣いだと思うんですけど」
思わず小さい声で突っ込んだリアに、苦笑して王零がガムテープをびりり、と破りだした。
「とりあえず、このテープを破らない事には先に進めないからな」
「苦労して貼ったんですよー!?」
「社内のガムテープ、全部かき集めてきたんですよー!?」
向こう側の妨害派従業員が、スクラムしながら叫び声をあげる。
が、この際そんなものは無視だ。
「うぅ。手がベトベトしますね」
「一体どれだけガムテープを貼ったんだか」
ビリビリビリビリ。
ガムテープを破るリアと王零。
悲鳴を上げる妨害派従業員。
やがて、全てのガムテープを破り終わり、その向こうのスクラムたちがはっきりと見えてきた。
「さて。我等を通してもらえるかな?」
「出来れば、手荒な事はしたくありませんから、お願いします」
王零とリアがそう言うものの、妨害派従業員たちはスクラムを組んだまま、全く同じタイミングで首を横に振るばかり。
2人は顔を合わせて溜息をひとつ吐くと。
「では、実力行使で行かせて頂きます!」
玄関前の悲劇、再びである。
「指揮官ー! 踊り場、突破されましたー!」
「ちっ。早いな。もう少し時間稼ぎが出来ると思ってたんだがな」
「ちょ、まっ! ぎゃあーーー!!」
再び途切れた会話に、焔は次の仕掛けを仕込む事に専念するのだった。
ガムテープの次は、画鋲。
時々スクラム。
その次はワックス。
そしてまたスクラム。
稚拙な妨害がエンドレスで踊り場に展開されていた。
そんな妨害が続けば、いくら温厚な人間でも苛立つのは当たり前だ。
「一体どれだけこういうトラップがあるんでしょうね。零さん」
「我には分からんが‥‥いい加減、うんざりしてくるな」
溜息を吐きながら、それでも最上階へと辿り着いたリアと王零の眼前に。
不思議な光景が飛び込んできたのだった。
白い腕章の、純粋派従業員たちがブルブル震えていた。
「あの、一体何が‥‥」
問いかけたリアの死角から、にょきっと飛び出した筒。
「リア!」
声を上げて、筒とリアの間に割り込んだ王零へと。
びしゃっ。
物凄い勢いで、どす黒い水が降りかかった。
「零さん!」
驚いて筒の先へと視線を向けるリアと、相手を睨みつける王零の視線を受けるのは。
「はぁ。何で僕が支店にまで来て、水鉄砲なんか‥‥」
「仕方ないだろー? お前の発案なんだからさ」
明らかに、今までの従業員とは格好が違う人間が2人、水鉄砲を構えていた。
「おめでとさん。ここが最上階だぜ」
にかっと笑いながら、水鉄砲の銃口を王零へと合わせる若い男が声をあげる。
「上の人の命令だから、悪いけど今日は妨害派なんだ。面倒だけど」
同じく、こちらは水鉄砲の銃口をリアへと合わせ、だぼだぼの白衣に黒の腕章を取り付けた女顔の男が面倒くさそうに呟いた。
「社長室は、このフロアにある部屋のどれか。あんたたちはここに辿り着いた2組目のお客さんだ」
「2組目? 私たち以外にも、このフロアに着いた人がいるんですか?」
リアの問い掛けに、こくりと頷いた白衣の男。
「ん。1人いる。今、多分社長と会ってるよ。ここから先は、今までとちょっと違うルールでいくから」
水鉄砲を構えたままの2人に、王零とリアが緊張した面持ちで言葉の続きを待つ。
「ロシアンルーレットの、部屋版。フロアにある部屋の中から、社長室を見つけられたらあんたたちの勝ちだ。ただーし、間違う度に」
若い男が、言いながらもう一度水鉄砲のトリガーを引いた。
瞬間、回避した王零は、何とか水の攻撃から逃げられたが、若い男はにかっと笑うばかりだ。
「今は逃げても構わねぇけど。部屋を間違う度に、あんたたちには水鉄砲の攻撃を食らってもらうぜ」
「因みに。中身は僕特製のコーヒー。美味しいよ」
「無駄遣いだな」
溜息を吐いた王零とリアに、若い男が小声で「ここだけの話」と耳打ちする。
「こいつの作るコーヒー。普通の人間には殺傷力バツグンの激苦だから。間違って口に入ったら最後、あんたたち1週間は寝込むぜ」
「殺傷力のあるコーヒーって、それはまた‥‥」
僅かに引きつりそうな顔を、一生懸命笑みにしようとするリアに、健気さを覚える王零だったが。
「とりあえず、最初の部屋を選んでよ。話が進まないから」
空気を読む事を一切しない、白衣の男がばっさりと切り捨てたのだった。
●カプリッチョ最終フレーズ
王零とリアが、2人の男と対峙していた頃。
焔は一人の女性と対面していた。
「ようこそ。私が社長のオレアルティア・グレイです。黒の腕章、という事は、妨害派の方で御座いますね」
「あ、どうも。俺は紅月・焔っす。デザイン案を持ってきました」
小さく頭を下げた焔に、微笑みながらソファに座る様促すオレアルティア。
ふかふかのソファに腰を落ち着けた焔の前に、紅茶が置かれた。
「お疲れでしょう? よろしければどうぞ」
「いえ、お気遣いなく」
そう言って、焔は懐から1枚の紙を取り出した。
それは、受付で渡された、デザイン案記入用紙だ。
「これが、俺のデザインです」
「拝見しましょう」
意気揚々とテーブルの上に置かれたその用紙に記入されていたデザインを見て、次の瞬間、オレアルティアはカチンと動きを止めた。
「御覧下さい。食器の至る所にこれでもかと無造作に描かれた髑髏! そして中央に大きく割れたハート! 今後2人で歩む人生への不安感と、ストレスをこれでもかと醸し出します!」
そのデザインは、何というか、こう。
幸せとは正反対の方向を突き進む、そんな内容だったのだ。
固まったオレアルティアにお構いなく、焔は楽しそうに解説を続ける。
「また、裏に書かれている浮気、離婚、ローン等の文字の羅列が不信感を煽り、精神に揺さぶりをかける! きっと幸せになると思います! 俺が!」
ジューンブライドの銀食器デザインだというのに、幸先悪い言葉がツラツラツラツラ。
言い切って、焔は自信満々に胸を張った。
「どうでしょう! 俺のデザイン!」
そこで、ようやくオレアルティアに動きが見える。
「ふふ。紅月様は、斬新な発想をお持ちですのね。私、色々な意味で尊敬致しますわ」
微笑を浮かべながら、席を立つオレアルティアの向かう先には、何故か籐籠に入れられた赤い果実。
聖書でアダムとイブが口にした、という知恵の実。
林檎があった。
「いえいえ、それほどでも」
嬉しそうにそう言った焔へと、林檎を持ったオレアルティアが振り返る。
表情は、微笑んだままだ。
が、何故だろう。
空調を操作した動作もなかったのに、社長室は先ほどよりも空気が冷えていた。
「それでは、1番に到着した紅月様に、私からご褒美を差し上げましょうね」
そう言いながら、オレアルティアは、焔へと手にした林檎を手渡す。
「林檎、ですか?」
「えぇ。これから、その林檎を使ってご褒美を差し上げますわ。お手数ですけれど、その林檎を頭に乗せて、壁際に立って頂けますか?」
微笑んでいる。変わらずにオレアルティアは微笑んでいるのだ。
だが、何故だろうか。
非常におどろおどろしいオーラが漂っている様に感じられる。
「これを頭に乗せて、壁際?」
焔は言われた通りに林檎を頭に乗せ、壁際に立った。
「はい。結構です。ではそのまま、動かないで下さいませね? ‥‥でないと、面白い事になりますから」
そこで、焔はオレアルティアが何処からともなく銀色の銃を取り出したのを見て、絶句した。
「えーと、社長サン? その手に持った銃は一体‥‥」
「あら、動いては駄目ですわ。違う場所に風穴が開いてしまいますもの、ね」
微笑で照準が自分に合わせられる。
そして、次の瞬間。
フロア全体に、焔の絶叫が響き渡った。
「‥‥」
「‥‥‥‥」
その頃、最上階のフロアにいた王零とリア、そして2人の男が、響き渡った絶叫に、其々顔を見合わせる。
「やっちまったな、社長」
「大丈夫じゃないの。あの人も一応、わきまえてるだろうし」
水鉄砲の銃口を下ろして、妨害派従業員のラスボス(みたいな存在)だった男2人。
ヴォルフガンクとレグズィスは溜息を吐いた。
「今の絶叫で、どの部屋が社長室なのか分かったよね」
「はい。あの部屋、ですよね?」
ヴォルフガンクの問い掛けに、答えたのはリアだ。
「ふむ。子猫が何を仕出かしたのか、何となくだが分かった気がするが」
王零がそう呟いたのを耳にして、レグズィスは苦笑しながら絶叫の元である部屋を指差す。
「ま。バレちまったらしょうがないだろ。あそこが社長室だ。気をつけてな」
それだけ言って立ち去っていくヴォルフガンクとレグズィスを見やって、王零とリアはもう一度顔を見合わせた。
「‥‥とりあえず、行くか、リア」
「そうですね」
軽いノックに、入室を許可する声が響く。
ノブを回しドアを開いた王零とリアの目に飛び込んできたのは、今回最大の不思議な光景だった。
「オレアルティア。汝は何をしているんだ?」
王零の問い掛けに、にっこり笑ったまま口を開いた社長が、驚愕の一言を告げる。
「あら漸様。何かおかしな事でも御座いますか?」
「おかしな事、と言いますか‥‥あの、どうして部屋の片隅で三角座りをした方がいらっしゃるんですか?」
戸惑いながら問いかけるリアへと、オレアルティアは微笑のまま三角座りをしている人間。
ブルブルと震えながら、ぶつぶつと。
「風穴が‥‥俺が林檎で、林檎が俺で‥‥」
そう呟いていた焔がいた。
「あらまぁ。紅月様? 新しいお客様が困っていらっしゃいますわ。さ、どうぞ此方へいらして下さいな」
「林檎が俺で、俺が林檎で‥‥」
オレアルティアの呼び声にも応えない焔に、小さく溜息を吐いて、社長は微笑んだままそっと歩み寄る。
そのまま身をかがめて、ポツリ、と耳元で口を開いた。
「紅月様? そのままでは、本当に別の場所へと風穴が開きましてよ?」
「いや、あの、本当‥‥調子こいてすんませんでした‥‥出来心なんです‥‥」
思いきりよく、それこそスライディングでもしそうな勢いで土下座をする焔を見て、オレアルティアがあらあら、と頬に手を当てる。
「本当に、何をしたんだ‥‥。相手は、仮にも客だろう、子猫」
「今までのトラップが可愛らしく思えるのは、何ででしょうね」
王零とリアは、今回で一番の冷や汗を流す事になってしまったのだった。
コホン、と咳払いをひとつ。
場を仕切り直す様にそんな仕草を見せてから、オレアルティアはもう一度にっこりと微笑んだ。
「改めまして。私が社長のオレアルティア・グレイで御座います。無事のご到着、何よりですわ」
「久しぶり。漸 王零だ」
「はじめまして。赤宮 リアと申します」
白い腕章を確認して、オレアルティアはぱちんと両手をあわせ。
「まぁまぁ! 漸様と赤宮様は『純粋派』ですのね。という事は、デザイン案をお持ち下さったのですわよね」
促されるままにソファへと腰掛けた2人を確認して、オレアルティアはちらりと焔へと目配せをする。
「紅月様も、よろしければこちらにお掛け下さい」
自分の横のソファを軽く手で促して、ダラダラと冷や汗を流し続けていた焔もぎこちなくソファへと身を沈めた。
全員分の紅茶を用意し、其々の前に置いてから、オレアルティアはそれでは、と口を開く。
「早速ですが、お二方のデザイン案を拝見してもよろしいですか?」
「あ、はい! これです」
リアが、まるで壊れ物を扱うかの様に、丁寧な手つきで防水用の袋から、一枚のデザイン案記入用紙を取り出した。
「他の囮は、コーヒーだの水だので駄目になってしまったが、社屋に入る前に本命はしっかり対策を施していたからな。全くの無傷だ」
同じく、防水用の袋の中から自身のデザイン案記入用紙を取り出し、王零はテーブルへとそれを置く。
テーブルの上に置かれたデザイン案を見つめて、オレアルティアは王零とリアへと視線を戻した。
「では、このデザインのコンセプトをリア様からお願い致します。拝見したところ、とても可愛らしいデザインですが」
「はい。取っ手の天使の翼は、幸せな未来へと向かって羽ばたいていくイメージです。スプーンの先は、愛情の形であるハート型にしてみました」
微笑みながらも、一生懸命に説明するリアを微笑ましげに見つめるオレアルティアと王零。
「素敵なイメージですわね。それでしたら‥‥スプーンとフォークで、比翼にするのも良いかもしれませんわ」
手近にあった書類の裏側へと、ペンを走らせて、オレアルティアが告げる。
そこに描かれたのは、リアのデザイン案を元に、社長が少しアレンジを施したものだ。
「スプーンとフォークで、一対の翼になる様にしてみました。これなら、ハートは変更せずに、翼のイメージも強調されるかと思いますわ」
そのデザインに、笑顔で頷くリアを見ながら、オレアルティアは益々笑みを深める。
「赤宮様は、本当に漸様をお好きですのね」
にっこりと笑いながら告げられた言葉に、一瞬で赤くなってしまうリア。
そんなリアの頭を軽く撫でながら、口を開いたのは王零だ。
「子猫。あまりリアをからかわないでくれるか?」
「あら。からかっているつもりは御座いませんわ。幸せなのは何よりですもの」
笑顔の社長と、苦虫を噛み潰した様な表情の王零。
若干、このほのぼのとした空気に似合わない光景ではあったが。
「まぁ、今回は引きましょう。それでは漸様。漸様のデザインコンセプトをお願い致します」
先に諦めたのは社長だった。
「拝見した所、実用性には欠ける様ですが」
「実用性より、記念品としてのデザインだな。外縁部はブルースターと他数種を模し、その内側には花の草を編みこむ形で冠を作る。網目の間の空間は穴を開け、中央部は太極紋を模した形に」
説明を受けながら、相槌を打つ社長。
「白と黒で着色した部分にはそれぞれ、新郎新婦の彫刻を施し、皿の裏側に結婚日時と新郎新婦の名を入れる」
「成程。記念品向きの、良いデザインですわね」
王零の説明を一通り受けてから、オレアルティアはサラサラと先ほどリアのデザインを元にアレンジを施したデザイン案の横に、何かを書きつけていく。
「ナイフをブルースターの装飾にするとして、ナイフとフォークは同じデザインでよろしいのでしょうか?」
その言葉に、王零は顎に手をやって暫く考えた後。
「花で統一するとして、そうだな‥‥それ以外の、花の選択か‥‥我等の場合は、ルビナスとサルビア、なんてどうだ? サルビアはリアを表し、ルビナスは我にとってリアがどういった存在かを表すといった感じで」
「そうすると、デザインとしては‥‥」
言いながら、簡単にラフを仕上げていくオレアルティアは、先ほどまでのお祭り好きの女性から、銀食器メーカーの社長としての表情を見せていた。
「この様なデザインは如何ですか? 漸様とリア様のデザインを取り入れて、取っ手の上部を翼に。ナイフの取っ手中央部から皿部分にかけてはブルースター。フォークをルビナス、スプーンをサルビアにしてみました」
王零とリアのデザインを混ぜ、それでいて繊細なデザインに仕上げてみせたオレアルティアに、王零とリアは顔を見合わせて頷きあった。
「こちらでよろしければ、採用して早速オーダーメイドの銀食器を作らせましょう。もちろん、今回の依頼料とお祝いとして、無料で、ね」
微笑んで告げたオレアルティアは、2人が頷いたのを確認して、早速製造を行わせるべく、社員を呼びつけたのだった。
「何だ。この妙な敗北感」
ポツリと呟いたのは、王零とリアのデザイン案を眺めながら何も口を挟めなかった焔だ。
何せ、余計な事を言えば最後、オレアルティアがまたも銀色のヤツを取り出しそうだったからだ。
「折角ですから、紅月様のデザイン案のものも作らせますわ。オーダーメイドですから、取り消しは不可ですけれどね」
にっこり笑顔で、最後までぐっさりと刺す辺りが、オレアルティア・グレイが若い女性であっても社長である所以だろうか。
何はともあれ。
社長のスランプから始まった今回のジューンブライド用銀食器デザイン狂想曲は、一部を除いて『めでたしめでたし』で終曲を迎えた。
●後日
デザイン案提出に参加したメンバーのもとに、其々が提出した、この世でたったひとつの銀食器セットが届いた。
ある者たちには幸せを。そしてある者には若干のトラウマを運んだその品は。
銀食器メーカー『S&J社』からの、心ばかりの贈り物となったのだった。
END
