タイトル:【JB】甘く切ない‥‥マスター:ドク
| シナリオ形態: イベント |
| 難易度: 易しい |
| 参加人数: 9 人 |
| サポート人数: 0 人 |
| リプレイ完成日時: 2009/08/02 04:02 |
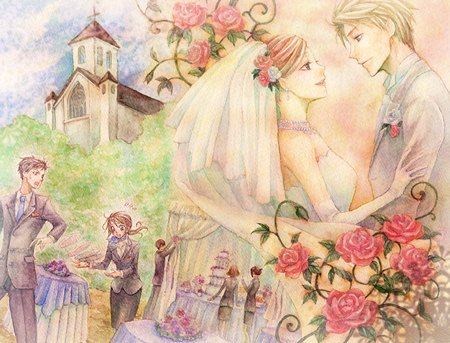
●オープニング本文
太平洋上の無人島は、多くの手により急ピッチで調査が進んでいた。仲間達が幸せな結婚式を行う、そのための準備だと思えばやる気も増そうと言う物だ。
「ふむ。思ったよりも快適な場所のようだ。これならば、心に残る祝典が行えるだろうな」
報告を聞いたカプロイア伯爵は、満足げに頷く。北側に見つかった入り江は遠浅で、泳ぎにも向いていた。海岸で迎えてくれる南国風の植生は明るく、当日の気分を盛り上げてくれるだろう。島中央の静かな湖畔は、ムードのある式を行いたいカップルにうってつけ、だ。
「島内の安全はまだ確認中です。崖などの危険な場所も調査中ですが‥‥」
手付かずの森や海が見える草原といった安全そうな地点でも、キメラが見つかっている。とはいえ、花の咲き乱れる一角などは、安全さえ確保できればロマンチックな一日に文字通り華を添えそうだ。
「崖には、洞窟のような場所もあるそうだね」
「はい。危険があるかどうか、そちらも報告待ちとなっています」
執事は、そう淡々と続ける。
「安全確認が終わったら、次の段階へ進もうか。そろそろ、人や物を動かさないとね」
まだ空白の目立つ地図を、伯爵は楽しげに見た。
「‥‥休暇、ですか?」
ある日、ミツルギ大佐の執務室に呼ばれたエリシアは、彼からの提案に首を傾げた。
「――そうじゃ。嬢ちゃん、ここ最近働き詰めじゃろう?
じゃからそろそろリフレッシュが必要かと思っての」
鷹揚に答えるミツルギ――彼の言う事は事実であった。
新設部隊設立に関する報告書の作成、その得点稼ぎのための相次ぐ出撃、訓練兵達の教導――ここ数ヶ月のエリシアは、まともに睡眠はおろか、休息すら忘れて働き続けているのだ。
「しかし、アメリカ大陸の情勢もきな臭くなってきていますし、休んでいる暇ははっきり言って無いのではないかと思いますが‥‥」
「‥‥相変わらず頭が固いのう」
一切の迷いも無い表情のエリシアに対して、ミツルギは思わず頭を抱えた。
一つ溜息を吐くと、ミツルギは手にしていたペンをエリシアに突きつけながら言う。
「――だからこそ、じゃよ。確かにアメリカで大規模作戦が発動する事は確実じゃ。
じゃが、まだはっきりとした日時は発表されておらん‥‥つまり暫くは本格的な攻勢は無い。
どうせ始まったら、戦力の少なくなった欧州戦線を守り抜く役目が回って来るんじゃ。
その時、貴重な戦力であるお前さんに倒れられちゃ、ワシの信用問題にも関わって来るんじゃ」
――分かるじゃろ? とミツルギは念を押す。
流石のエリシアも観念したのか、渋々と言った表情で敬礼する。
「――了解しました。エリシア・ライナルト大尉、本日より三日間、休暇を取らせて頂きます」
「――うむ、宜しい」
半分脅しに近いが、このぐらいの事を言わないと休もうとしないのだから仕方無い。
そして背を向けて出て行こうとするエリシアに、ミツルギは今回の本題を切り出した。
「ちょいと待った――休暇ついでに、これを頼まれちゃくれないかのう?」
ミツルギが取り出したのは、一枚の手紙――そこには、カプロイアの紋章が燦然と輝いている。
――普通の蜜蝋の筈なのにそう見えるのは、その差出人の性格の成せる業と言えるだろう。
「それは――?」
「ああ、何でもカプロイアの若旦那がのう‥‥」
ミツルギは、カプロイアが行おうとしている一大結婚式イベントについて話し始めた。
「‥‥そんな訳でじゃな、嬢ちゃんにはこのイベントで使うウェディングケーキを作るのを手伝って貰いたいんじゃよ」
これは知人ならば誰もが知っている事だが、エリシアは大のケーキ好きだ。
美味しいケーキを前にすれば、冷徹な指揮官然とした彼女も我を忘れて乙女の表情に変わる。
――と、同時にケーキ作りの腕前も相当なものだった。
もし軍人という道を選んでいなければ、菓子職人として名を上げていただろう――ミツルギは贔屓目無しに本気でそう考えていた。
「‥‥しかし、軍上層部の意向としては‥‥」
「――そんなの関係ないわい。これはワシの完全な独断じゃ」
大体な‥‥と、ミツルギの眼が歴戦の軍人の光を帯びる。
「‥‥戦場っちゅうんは、何時死ぬかも分からんこの世の地獄じゃ。
そんな所に送り出される前に、愛するモン同士を結ばせたいと思うのは人の情というものじゃ」
能力者――異星の侵略者、バグアと戦う力を持った者達。
彼らは誰もが戦う事を定められ、誰もが戦場へと向かう――自分達軍人のように。
ミツルギはエリシアに背を向け、窓から外を眺める。
――そこには、いつもと変わらない欧州の抜けるような空があった。
「――嬢ちゃんと『あいつ』を強引にでも連れ合いにしなかった‥‥今でも後悔しとるよ」
その表情は普段のお茶らけた好々爺では無く、バグア来襲前から軍に身を置き、戦う事に疲れ果てた老将のものだった。
「じゃからな嬢ちゃん‥‥お前さんもこれを機に今からでも――」
「おじ様」
ミツルギが続けようとした言葉を、エリシアが穏やかながら有無を言わさぬ口調で遮る。
その顔は怒るわけでも、悲しむ訳でも無く、ただ優しく微笑んでいた。
「――私は結婚はしません。大体そんな歳ではありませんし‥‥」
――そっ‥‥と、左目の眼帯を撫でる。
そこには分厚い眼帯の上からでも分かる、醜い傷痕。
「‥‥こんなモノがあっては、殿方というのは寄っては来ないでしょうから」
「嬢ちゃん、ワシの話を――!!」
「――それでは、私一人では流石に苦労するでしょうから、この件は私から傭兵に依頼を出させて頂きます」
「嬢ちゃん!!」
――バタン。
ミツルギの言葉を無視して、エリシアは静かにドアを閉めて去っていった。
一際大きく溜息を吐き、ミツルギは椅子に深く座り込んだ。
「――あんなエエ女‥‥滅多におらんのじゃぞ‥‥?」
机の鍵付の引き出しを開け、その中にある一枚の写真を手にし、そっと撫でる。
――そこには、泥だらけになりながらも、楽しげに笑う兵士達の姿がある。
その中心には、まだ左目を失っていなかった頃のエリシアと、朗らかな笑みを浮かべる繊細そうな青年が仲睦まじく寄り添っていた。
「‥‥そんな嬢ちゃんを置いていきおって‥‥お前は何処までも罪な男じゃのう」
それは、イタリアの戦場で花開いた遅咲きの恋。
――本当ならば、彼らもまたチャペルで結ばれる筈だったのだ。
「――のう、バレルよ」
バレル・ガーランド軍曹――イタリア戦線において死亡し、キメラに改造され、能力者達によって倒され、埋葬された男。
それが、かつてエリシアと将来を約束しあった男の名であった。
――エリシアによってケーキ作成の依頼が張り出されるのとほぼ同時刻。
ミツルギから傭兵達にもう一つの依頼が届いた。
『――穣ちゃんを、少しでもいいから元気付けてやってくれ」
言葉こそ短いが、そこには万感の想いが込められていた。
●参加者一覧
/ リディス(ga0022) / 幡多野 克(ga0444) / 紅 アリカ(ga8708) / 佐倉・拓人(ga9970) / エドワード・リトヴァク(gb0542) / 美環 響(gb2863) / レオン・マクタビッシュ(gb3673) / 冴城 アスカ(gb4188) / 天原大地(gb5927)●リプレイ本文
結婚式が行われるという無人島――その港には八人の能力者達が集っていた。彼らの今日の目的は、エリシアと共に合同結婚式に使われるというウェディングケーキを作る事であった。
「まさか、エリシアさんとケーキを作る日が来るとは‥‥」
佐倉・拓人(ga9970)が最初に出会った時自らが抱いていた、エリシアを怖いと思う気持ちを思い出し苦笑する。
今では彼女の厳しさというものも、確かに必要なのだと思えるようになっていた。
慣れというものは凄いものだと改めて実感する。
「自炊期間は長いんだが、菓子作りはあんまり経験ねえもんでな‥‥」
天原大地(gb5927)が少し不安げな表情を浮かべた。
だが、佐倉が安心させるように肩を叩く。
「今回はケーキだけじゃなくて、色々と作業が必要ですから‥‥」
「おう、俺はそっちを担当させてもらうぜ」
佐倉の言葉に、天原は白い歯を剥き出しにして微笑んだ。
「去年の戦い以来だな‥‥大尉になったのか」
まるで自分の事の如く嬉しそうに微笑むのは、エドワード・リトヴァク(gb0542)。
今日は久しぶりの再会と、昇進祝いも兼ねての参加だ。
「‥‥元気が出るように、美味しいの作れるかな」
――だが、彼を始めとした能力者達の心を占めるのは、エリシアのものとは別の、もう一つの依頼。
「エリシア大尉‥‥聞いた話によると大分お疲れのようなので、心配です」
美環 響(gb2863)が物憂げな表情を浮かべて呟く。
――その手にはレインボーローズが燦然と輝いている。
普通ならばキザったらしく見える佇まいも、彼がやると妙に似合うから不思議だ。
「辛い過去っていうのは簡単には忘れられないわね‥‥」
冴城 アスカ(gb4188)は先日聞かされたミツルギの言葉を思い出していた。
エリシアにはかつて恋人がいた事、そしてその恋人をバグアに殺され、キメラに改造されてしまった事‥‥。
‥‥そして、醜悪な姿となった想い人を、討伐した傭兵達と共に自ら葬った事。
それは聞くだけで胸が締め付けられるような内容であった。
「――あの人が‥‥大尉の‥‥? 単なる仲間だと‥‥思ってた。
霊園に埋葬する時‥‥どんな気持ちだったのか‥‥」
幡多野 克(ga0444)はいつもなら無表情な顔に、驚きを浮かべていた。
彼は仲間と共に、その「元人間」のキメラを屠り、埋葬を手伝った傭兵の一人なのである。
だから、彼女の事は他人事とはとても思えなかった。
――せめてエリシアの心の平穏のために、自分にやれる事を出来たら‥‥。
幡多野はそう考えていた。
‥‥無論、同じ甘党として彼女に親近感を持っている事も理由のひとつであるが。
――ちなみに、彼と同じ依頼に参加した経験があり、エリシアとも親しい紅 アリカは、今回急用のため不参加となっている。
(「ジューンブライド‥‥か。大尉や、その彼にも同じような日が来たんだろうか?」)
エリシアと同じく、かつて一兵士として欧州戦線を戦ったレオン・マクタビッシュ(gb3673)も、戦場で様々な出会いと別れを経験した。
――もしかしたら、自分は知らない内に彼と出会い、肩を並べて戦っていたんだろうか?
そんな思いがレオンの胸に過ぎり、知らず表情が固くなる。
それを見たエドワードが、少し心配そうに顔を覗き込んだ。
彼らはかつて士官学校で教官と生徒という間柄だったため、口調も少し砕け気味だ。
「‥‥どうしたんですか教官?」
「――いや、済まんなエド。少ししんみりとしてしまった」
――その場の空気が重くなろうとした時、ぱんぱんと軽快に手を打ち合わせる音が響いた。
「そこまでにしましょう。折角幸せな方々の門出を祝うものを作ろうという時に、暗くなっていてはいけないでしょう?」
リディス(ga0022)が元気付けるように皆に向かって呼びかける。
「‥‥そう‥‥だね」
「確かにリディスさんの言う通りです」
「これ以上、私達がしんみりしていたって解決するようなものでもないでしょうしね」
彼女の言葉に能力者達は頷き合い、エリシアが待つ集合場所へと向かった。
軍の施設の中にある食堂の厨房――そこにエリシアはいた。
休暇という事もあって、活動的なブラウスとスカート、そしてエプロンという出で立ちだ。
「良く来てくれたな諸君。軍‥‥というより大佐の都合でわざわざの足労済まない」
加えて挨拶も、いつもの敬礼では無くスカートを摘みながらの一礼だ。
彼女の挨拶に応じ、初対面の能力者達が次々と自己紹介を始める。
「初めましてエリシア大尉。傭兵の冴城 アスカよ。よろしくね。
あ‥‥今は休暇中だからエリシアさんって呼んでもいいかしら?」
「是非も無いさ。今後とも宜しく頼むぞサエギ・アスカ」
にっこりと笑みを浮かべながら差し出された冴城の手を、エリシアは快く握り返した。
続けてリディス、天原も同じように握手を交わす。
「お久しぶりですエリシアさん。KVトライアスロン以来ですね」
「――そういえば、あの時は入賞の祝辞を忘れていたな‥‥改めておめでとう、ミタマ」
美環の挨拶を皮切りに、元々エリシアと顔見知りだった面々も挨拶に加わって行く。
「それと、ハタノにサクラ‥‥エドワードにレオンも息災のようで何よりだ」
「――ああ、今日は精一杯努めさせてもらうよ」
「‥‥頑張り‥‥ましょう‥‥」
挨拶を終えたエリシアは、早速作業に取り掛かろうと皆を厨房に案内しようとするが、それを天原が止めた。
「ところで、エリシアさんに俺達から受け取って欲しいモンがあるんだよ」
「――む?」
彼の言葉に怪訝そうな顔を浮かべたエリシアだったが、その答えは後ろから現れたリディスの手の中にあった。
「皆でエリシアさんのために作ったケーキです‥‥ちょっとしたサプライズにと、ね」
それはショートケーキや、以前エドワードがエリシアへ送ったダンディケーキなど、エリシアの好物ばかりを並べたものであった。
「これ、練習がてら作って来たんだけど‥‥良かったら食べて下さる?」
はにかむような笑みを浮かべて、冴城がエリシアにケーキを手渡す。
――それは、エリシアと死んだ彼女の恋人‥‥バレル軍曹へ向けてのものだった。
‥‥無論、それをわざわざ伝えようとはしなかったが。
「‥‥済まない、ありがとう諸君。では、これは作業が終わったら打ち上げとして頂くとしよう――無論、皆でな」
エリシアは能力者達を見渡し、改めて感謝の言葉を言った。
「――それじゃあ、先の楽しみも出来た所でケーキ作りと参りましょう」
美環の言葉で、エリシアと能力者達は一斉に作業を開始した。
「――まず一つ目は、王道として生クリームと沢山のイチゴを使ったものにしましょう」
作業が始まると、傭兵達の中で最も熟練した菓子作り技術を持つ佐倉の指示の元、今回作るウェディングケーキの基本形が決められていく。
通常は結婚するカップル達の要望などが取り入れられ、オーダーメイドとなるのだが、今回デザインやデコレーションなどは傭兵達に一任されていた。
‥‥自由、といえば聞こえは良いが、決してミスやセンスの悪いものを作って出す事が出来ないある意味最も厳しい条件である。
そして、この場に集まった者達は、ウェディングケーキ作りの経験の無い者が殆どのため、認識の齟齬が無いように綿密な打ち合わせと、意思の伝達が必要不可欠だ。
「――では、克さんや大地さん、それにレオンさん達はケーキの土台と骨組を作っていって下さい」
「‥‥うん‥‥まかせて‥‥」
「おう!! 力仕事なら自身があるんだ」
「悪いが、俺も菓子作りはあまりやった事が無いからな‥‥精一杯作らせてもらうよ」
四人が頷き合って、作業台へと向かって行く。
今回は四段重ねのウェディングケーキ――それだけの大きさになると、デコレーションもかなりの重さとなるため、スポンジだけではケーキの形を支えきる事が出来ない。
そのため、アクリル板で土台を作り、支柱でそれを繋げる事で基本的な「型」とし、それに合わせてケーキを作り組み立てていく形となる。
それに分割して作る事も可能なため、作る手間だけで無く、保存や輸送などもやり易くなるのだ。
「エリシアさん、今回使う材料はそろってるのかしら?」
「――既に用意してある。あらかじめミニチュア版を作ったが、重量やバランスなどは合格点と言えるだろう」
「わぁ‥‥ミニチュアを昨日の内に? 凄いな‥‥」
冴城に答えるエリシアの発言を聞き、エドワードが思わず感嘆の声を上げる。
大きなウェディングケーキを作る場合、いきなり原寸大のものを作るのでは無く、何分の一かの縮尺を施したミニチュアを作り、材料の大体の分量やデザイン、重心などを決めて行くのが一般的だ。
――確かエリシアの休暇は一昨日の夜から。
エリシアは僅か一日と半のうちに、ミニチュアとは言え、本番に作るケーキと同じものを一人で作って見せたのだ。
しかも、本番で作る量に合わせてしっかりとした分量の調整も出来ているようだった。
エリシアの用意の良さにひゅうっ、と口笛を鳴らす冴城。
「――了解、じゃあ楽しいお菓子作りの開始と行きましょ」
「‥‥こういうのを作るのは久しぶりですね」
「ふふ‥‥飾りつけは僕に任せて貰いましょう」
「それは少し気が早いのではないかミタマ?」
リディスが、少し嬉しそうな表情で微笑み、美環が気障にポーズを決めると、エリシアがそれに突っ込みを入れる。
ウェディングケーキ作りは、和やかに始まりを告げた。
「‥‥一段目の土台の型‥‥出来たよ」
「どらどら‥‥お、いいんじゃねぇか?」
「良し、じゃあ手早く組み立てるとするか」
幡多野と天原、レオンの三人は手分けしてアクリル板を、出来上がるケーキの形に合わせて丁寧に切って形を整えて行く。
これによってケーキ全ての重心やバランスなどが決まるため、非常に繊細さが要求される作業である。
――だが、そこは流石に普段KVや銃など、細やかな作業が必要となるモノを扱っている能力者。
工具などを使って、ウェディングケーキ四個分の土台となる四角形の板が次々と型取られていく。
作業は今の所順調と言えた。
「厨房の方がどうなってっかな‥‥」
天原の心配をよそに、不意に廊下から蕩ける様な甘い香りが漂ってきた。
どうやらあちらもスポンジケーキの焼成に入ったようだ。
「‥‥ああ‥‥美味しそう‥‥」
幡多野が物欲しそうな顔をしながら呟く。
‥‥彼は厨房に行ってつまみ食いしたい衝動を、どうにか抑える事に必死になっていた。
「――早くお目にかかるためにも、こっちを早く片付けないとな」
幡多野の様子に苦笑しながら、レオンは型を組み立てる手を早めた。
――オーブンのタイマーが音を立て、蓋を開けると甘い香りと共に黄金色に焼かれたスポンジケーキが姿を現した。
それを色々な角度から見回した佐倉は、満足そうに頷く。
「――良し、中々の出来ですね‥‥後は――」
「一つ目の土台、出来たぞー」
それとほぼ同時に、厨房の扉を開けて天原が入って来た。
その手にはアクリル板の中心に、同じくアクリルの支柱が繋がったケーキの土台であった。
大きさは一抱えと言った所か。
「――ご苦労様です。さて、早速型合わせと行きましょう」
リディスが土台を念入りに消毒してから、ケーキを崩さないように持ち上げ、慎重に支柱に通していく。
中心に穴の開けられたスポンジケーキは、寸分違わずすっぽりと土台に収まった。
「うん、中々いい塩梅ですね‥‥じゃあ、デコレーションしていきましょう」
「材料の方は、僕が責任を持って切らせて頂きました‥‥無論美しく」
満足げなエドワードの言葉に、美環が前髪を跳ね上げながらポーズを決める。
その動作はともかく、彼の言葉通り挟み込むフルーツたちは、飾り付けとして申し分の無い美しさであった。
スポンジとクリームを層にしながら、その間に桃やミカン、ブルーベリーなどのフルーツをサンド。
それが終わると、周囲に生クリームを塗りたくってコーティングしていく。
「えっと‥‥クリームの分量はこんな感じでいいのかしら」
「ふむ‥‥少し多いな。デコレーションの分も含めると少々口当たりがくどくなりそうだ」
「なるほど。じゃあこれで――」
冴城がエリシアや仲間達に話しかけながら、ムラの無いように全体にクリームを馴染ませていく。
飾りの要素が高いものの、ウェディングケーキは最終的に式場内の人々に振舞われる。
――そのため、佐倉やエリシアだけでなく、この場にいる全員が味に決して妥協しようとはしなかった。
シロップ漬けにされた無数のイチゴが、表面に幾何学模様を作り出し、白一色のケーキに色を添える。
「――これで‥‥良し、と‥‥」
佐倉がクリームで複雑で美しい文様を描いていく。
四角いケーキの四隅には、まるで神殿の柱のような装飾が施され、絢爛さを演出させる。
――菓子職人に匹敵する腕前を持つ佐倉の、面目躍如といったところだ。
「――もう少し飾りが欲しい所ですね。」
「安心してくれ、その点はしっかりと考えてある」
そして、エリシアが自ら作ったシュガーフラワーを添え、その上からシュガーパウダーが振り掛けられ、とうとう一段目は完成した。
「では、この調子でどんどん行きましょう」
まだまだ作業は始まったばかり――能力者達は次なる作業へと移っていった。
――一段目でコツを掴んだ能力者達は、二段目、三段目と次々に作り上げていった。
そして数時間後には、誰に見せても恥ずかしくない、立派な四段重ねのウェディングケーキが厨房の一角に鎮座する事となった。
記念すべき一個目の完成だ。
「‥‥なんつーか、こうやって見ると感無量って奴だな」
「ちょっと気が早いけど‥‥同感ね」
天原と冴城が羨望の眼差しで、自分の目線とほぼ同じぐらいの高さになったケーキを見つめる。
他の仲間達も、まずは一つやり遂げた事への充足を感じていた。
(「‥‥俺も、いつかは彼女とあんな‥‥い、いやいやいやいや!!」)
中にはエドワードのように、愛する寡黙で何処か甘えん坊な少女と自分の事について考えてしまい、顔を赤らめる者や、
「‥‥ホント、綺麗で‥‥美味しそう‥‥だよね‥‥」
幡多野のように、口の端から思わず涎が垂れそうになる者もいた。
「おいおい、つまみ食いなんかしたら大尉に叱られ――」
レオンが苦笑しながらエリシアの方にちらりと視線を移す。
――瞬間、彼の表情が僅かに凍りついた。
「‥‥綺麗だな‥‥本当に――」
エリシアは、厨房の台に乗ったウェディングケーキを微笑みながら見つめていた。
けれど、その瞳には、笑みには‥‥例えようも無い悲しみが宿っていた。
美しいアイスブルーの隻眼は、老人が童を見るような、重病人が窓から走り回る童を見るような‥‥疲れきり、何かを諦めたような‥‥そんな深い色を湛えていた。
――それは、軍人としては儚すぎ、乙女にしては危うすぎる光。
「――エリシア」
それが見るに耐えられなくて、レオンは無意識の内に強く、彼女の名前を言っていた。
その言葉に、エリシアがはっとして振り向く。
「――あ、ああ‥‥何だレオン?」
「いや、大分『酷い』表情をしていたからな」
「大丈夫? 大分疲れてるんじゃない? エリシアさん、一番働いていたし‥‥」
冴城がエリシアに歩み寄り、エリシアの肩を優しく揉み解す。
「エリシアさん‥‥辛くなったら無理しなくてもいいのよ?
思いっきり泣いてもいいし‥‥貴女は軍人である前に一人の女なんだから、それぐらいのことはしても大丈夫なのよ?」
――それに今は休暇中だしね、と悪戯っぽい笑みを浮かべる冴城。
「ああ‥‥ありがとうサエギ」
自分でも、自覚はあったのだろう――冴城の忠告に素直に頷くエリシア。
だが、その表情はあまり晴れやかとはいい難かった。
「大分、重傷みたいですね‥‥」
美環が人知れず呟く。
それはこの場にいる能力者達の思いを代弁するものであった。
二個目のケーキは、一個目の応用としてチョコクリームを使用したものにする事となった。
基本的に工程は同じだが、流石の能力者達の顔にも疲れが見え始める。
――無理も無い。
彼らはかれこれ半日近く、ケーキ作りに専念しているのだから。
「――おっ‥‥と!!」
フルーツを飾り付けていた佐倉の手元が狂い、デコレーションが終わっていた場所に落ちてしまう。
――何度目かのやり直しだ。
エリシアと共同しているとはいえ、仲間達に指導しながら繊細な作業を続けていた彼の疲労は、今やピークに達していた。
「大丈夫かサクラ‥‥あまり無理はしないでくれ」
彼を嗜めるエリシアだが、彼女の動きもまた疲労で緩慢になりつつあった。
それを見たエドワードが、全員に呼び掛ける。
「皆さん、そろそろ休憩しましょう。
流石にこのまま作業を続けていたら、どんなミスがあるか分かりません」
「‥‥同感ですね。では、幡多野さんたちにも伝えてきましょう」
彼の提案に従って、リディスが作業班の三人の所へと伝えに行く。
――能力者達はしばしの休息に入るのだった。
――集合した時には東天にあった太陽は既に落ち、辺りは淡い月明かりに照らされた闇に包まれていた。
軍施設の裏口に一人、エリシアは座っていた。
「――私とした事が‥‥未練だな」
先ほど能力者達の前で晒してしまった醜態に、思わず苦笑する。
だが、その表情は重い――まるで心が泥沼に沈み込むかのような錯覚を覚える。
「こんな体たらくの私を見たら‥‥君は何と言うだろうな、バレル?」
目を瞑れば今でも思い出す‥‥彼の笑顔、彼の勇姿、彼の――体。
はっきりと覚えているからこそ、尚更その思い出がエリシアの胸を締め付けていた。
そして最後の思い出は、一夜にして二個中隊が壊滅した悪夢の夜。
片目を抉られながらも撤退しようとしない彼女を定員ギリギリの装甲車に押し込め、バレルと、小隊の仲間達は殿として戦場に残った。
『お嬢、てめえは駄目だ。片目になった奴なんざ、足手まといだからな』
豪快に笑いながら、迫るキメラに腹を貫かれた隊長。
『――エリシア‥‥幸せになって下さい‥‥幸せに――』
装甲車の扉を閉める間際、囁くように告げられた別れの言葉。
――気の良い仲間達の全員が死に、自分だけが生き残った。
そして愛しいあの人は、異形のキメラとなって帰ってきた。
――傭兵達によって屠られ、息絶えた彼はとても穏やかな顔で‥‥。
「――!!」
エリシアは慌てて自らの思考を遮った。
これ以上は駄目だ――きっと何かが止まらなくなる。
「――エリシアさん、こちらにいらっしゃいましたか」
「うっす、姿が見えないんで皆心配してるぜ?」
その時、彼女の背後から声がかけられる。
それは缶飲料を手にしたリディスと天原の二人だった。
エリシアに缶コーヒーを手渡し、リディスと天原はエリシアの側に腰掛けた。
「悪ぃな、一人でゆっくりしてる所をさ」
「いや、構わんよ‥‥大方、大佐――おじ様に頼まれたのだろう?」
「あ、ばれてたか」
「おじ様のお人よしは、物心ついた頃からの付き合いだからな」
事ここに至り、天原はもう隠そうとはしなかった。
だから、リディスと共にエリシアに自らの言葉を伝えにきたのだ。
「エリシアさんとは前からゆっくりお話したいと思っていました。
‥‥同じ匂いを感じて、とでも言いましょうか?」
「同じ匂い‥‥?」
リディスの言葉に、エリシアは首を傾げる。
すると、リディスは柔らかな笑顔で星空を仰いだ。
「エリシアさんの事は報告書でしか知りませんが‥‥私も前に同じような経験を二度ほど‥‥ね。しかも一度は極最近の事です」
「――!!」
エリシアの瞳が驚愕に見開かれる。だが、敢えて口を開こうとはしない。
ただ黙って、耳を傾けた。
「‥‥まぁ道ならぬ思いでしたし、相手はそのことを気付きもしなかったでしょうからしょうがないかもしれませんが」
――一瞬だけ、リディスが俯く。
その表情は長い髪に隠れ、窺い知れなかったが、すぐに笑顔で続けた。
「――それでも、そのことを後悔したことはありません。
その想いは本物で、そしてまだこの心に生きているから」
それが心の底から大切なものと分かるような口調と仕草で、リディスは自らを抱き締める。
その心だけは、決して離してなるものかと。
「――だから、大尉が恋人さんの事を想い続けてるのは、悪い事じゃないと思うぜ?」
リディスに続いて、天原が口を開く。
彼の心にも、十字架が存在する――それは、自らの無謀が引き起こした取り返しのつかない出来事。
「‥‥ちょいと昔、流石に改造までされた訳じゃねえが、俺もダチと幼馴染を失ったよ。
‥‥俺自身のせいでな。
大尉とは似たような痛み‥‥持ってんのかもなとは思ってる」
彼は決して同情している訳では無い。
――ただ不器用に、己の考えを懸命に伝えようとしているのがひしひしと伝わってきた。
「何しろ初対面だ。経歴を知ってるわけでもねえし、どうこうしろって言うつもりはねえけど‥‥死んだ大尉の恋人さんが、今の大尉の現状を望んでるとも全ッ然思えねえ。
彼を忘れろってんじゃねえ、引き摺れっつうことでもねえ。
‥‥恋人さんへの想いを捨てられないならそれでもいい、代わりを探せってことでもねえ。
『前へ』進んで欲しいと、ただ、俺はそう思うんだ」
天原の真剣な眼差しを見つめ、エリシアはふっ‥‥と微笑んだ。
(「若いな‥‥」)
天原の若く、ひたむきな思いを感じ、心底羨ましく思う。
――何処か達観してしまった自分には無いものを天原は持っている。
自嘲するように、エリシアは手に眼帯を当て――ようとして、リディスにそっと止められた。
「――私はエリシアさんの傷、綺麗だと思いますよ?」
「――な!?」
「どんな理由があれ、それを抱え生きるエリシアさんは綺麗だと思いますから。
きっとそういう人は他にもいる筈です。その傷も、貴女の魅力の一つですから」
エリシアが眼帯に触る時――それは、その醜さと、過去に捕らわれる自分への嫌悪の発露である事に、リディスが気付いていた。
だが、それは己を否定する事と同じ。
だからリディスは止めた。
「‥‥美しい、か。
そう思える時は、そう思ってくれる人は、来るんだろうか? いるんだろうか?」
不安げに、けれど心なしか上を向いた目でエリシアが呟く。
リディスは、彼女の手をそっと取った。
「私も‥‥これから探し直しです。だから、一緒に頑張ってみませんか?
きっとまた心から笑い合える相手がいる筈ですから」
「――ああ‥‥そうだな」
リディスと天原はそろそろ厨房に戻ろうとエリシアに提案したが、彼女は「もう少しだけここにいる」と言ったので、彼らは先に行く事にした。
その道中で、リディスは深い溜息を吐いた。
「‥‥? どうかしたのか?」
「いえ‥‥ね――少しばかり自分の言った事に呆れてしまいまして‥‥」
困ったように眉根を寄せ、何処か遠い目つきでリディスが呟く。
「――道ならぬ想い、ですか。自分で言ってどうかと思いますね。本当に。
直接対峙したのも一度だけ、しかも命を奪い合う真剣勝負の場面で。
だからこそ狂おしい程に惚れてしてしまったのでしょうか。
もう届きませんけどね。サムライの彼には‥‥」
それに対して、天原は何も言おうとはしなかった。
彼もまた、自らの過ちを澱の如く心に溜めているからこそ、彼女のやるせなさが人の言葉でどうこう出来るものでは無い事は分かっていたから。
(「‥‥やりきれねぇよな‥‥勇人‥‥瑠衣‥‥」)
今は無き親友と思い人の名前を心の中で呟き、天原は溜息を吐いた。
リディスと天原が去った後、エリシアはただぼんやりと夜空を見上げていた。
そして先ほどの彼らの言葉を反芻する。
(「彼らの言葉は正しい‥‥だが、前に進めるんだろうか?」)
エリシアは既に決して若くは無く、軍人としての生き方しか知らない。
――自分がこのまま一歩を踏み出せないのではないか?
――踏み出せたとしても、受け入れられずに終わってしまうのではないか?
そんな思いが、彼女の中に去来しては消えて行く。
「――エリシアここにいたか。佐倉さんがそろそろ作業を始めようと言っているんだが‥‥」
「ん――? ああ、済まない。すぐに行く」
通用口から顔を出したレオンに応じ、エリシアは彼の後を追うように歩き出す。
――暫し、二人は無言で廊下を進んだ。
その途上、エリシアは意を決したように口を開いた。
「‥‥なぁレオン‥‥キミは、私のこの傷の事をどう思う?」
特に意味は無い、気紛れの問いだった。
だが、聞かれたレオンは立ち止まってエリシアの事をじっと見つめ、真剣な眼差しでそれに答える。
「俺は、今のエリシアは綺麗だと思っている。十分素敵だよ」
「――!!」
そう言って柔らかく微笑むレオンに、エリシアは驚きの顔を向けた。
予想はしていたかもしれない‥‥だが、それを面と向かって言われた事に動揺する。
ある童話に書かれていた――幸運の青い鳥は、ごく身近な場所にいる。
自分がこれから探していこうとしていた己の醜い傷痕を綺麗だと思ってくれる相手‥‥それはエリシアにとってこんなに近い場所にいたのだ。
「くくっ‥‥ははははっ!!」
思わず笑みが零れ、大きな声で笑い出す。
それは豪快で、見たものを明るくするような高らかな笑い声。
自分はこんな風に笑えたのかと、エリシアは内心非常に驚きながら笑う。
「――? どうしたんだいきなり?」
「いや‥‥何、自分のネガティブさに少々呆れてしまったのでな」
当のレオンは最初こそ呆気に取られていたが、エリシアの顔を見てどうでも良くなった。
その顔には憂いや悲しみ‥‥一切の負の感情が消え、彼女本来の美しさに満ちていたから。
「さて、急がなくてはな‥‥花婿と花嫁たちが、私達の作るケーキを心待ちにしているからな」
「ああ、頑張ろう」
かくしてウェディングケーキを作る作業は再び始まった。
能力者達は再び過酷な菓子作りの作業に没頭して行く。
――だが、彼らはその作業に例えようも無い満足感のようなものを抱いていた。
何故ならこれは、一生で最も幸せな瞬間の一つを迎えようとしている者達の餞であるから。
だがそれ以上に――、
「サクラ!! ここのデコレーションは任せたぞ!!
私はシュガーフラワーの仕上げに入る」
「はい!!」
「ミタマ!! エドワード!! サエギ!! 卵白を攪拌してくれ!!
程度が分からなかったら私に聞け!! アドバイスくらいは出来る!!」
「「分かりました!!」」
「まかせときなさい!!」
先ほどとは見違えるように精力的に動き回るエリシアの姿を見たせいでもあった。
彼女の表情には最早暗さは無く、ただ幸せを迎える人々への祝福だけがそこにある。
彼女のこんな姿を見せられて、弱音を吐ける訳が無い。
(「‥‥どうやら、もう大丈夫みたいですね」)
(「ああ、そうみてぇだ」)
彼女の姿を見て、リディスと天原はそっと耳打ちをし合って微笑んだ。
作業は二日に渡り、二日目の夜――とうとう四つのウェディングケーキは完成した。
そして、最後の仕上げにかかろうとした佐倉を、エリシアが止めた。
「――最後は、私にやらせてくれ」
その手には、ルビーのように輝く飴細工のバラがあった。
エリシアは慎重に、それをケーキの最頂部に飾り付ける。
「――綺麗ですね‥‥これで、正真正銘の完成という訳ですか」
「皆さん!! お疲れ様でした!!」
誰とも知れずに鳴り出した拍手が、厨房の中にいつまでも響いていた。
彼らが作った四つのケーキはすぐに無人島の各地へと送られ、そして新たな門出を祝った。
その美しく、美味しいケーキたちは、新婚夫婦たちとその参列客たちを大いに満足させたのだった。
そしてその数日後、UPC欧州軍のオフィスに眼帯を外し、傷痕を臆面も無く晒したまま職務に就くエリシア・ライナルトの姿があった。
けれども、それに対して不快さを漏らすものは皆無であった。
――そんなモノが気になら無い程、エリシアの表情は輝いていたから。
その日を境に、彼女へ夕食の誘いを入れる男性兵士が増えたが、エリシアはその全てを鎧袖一触とばかりに断り、彼らに対して「弛んでいる!!」と活を入れた。
例え憂いが無くなっても、やはり彼女は彼女であるらしい。
